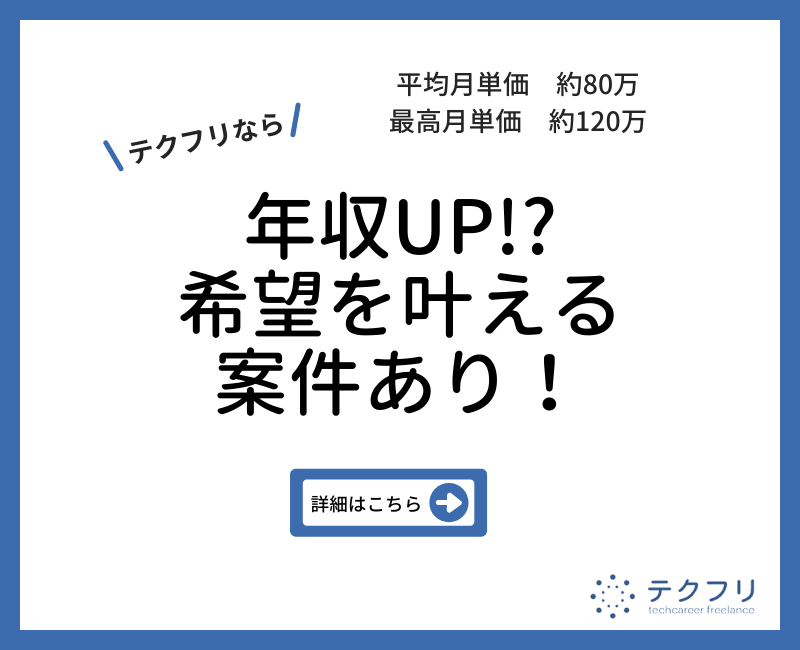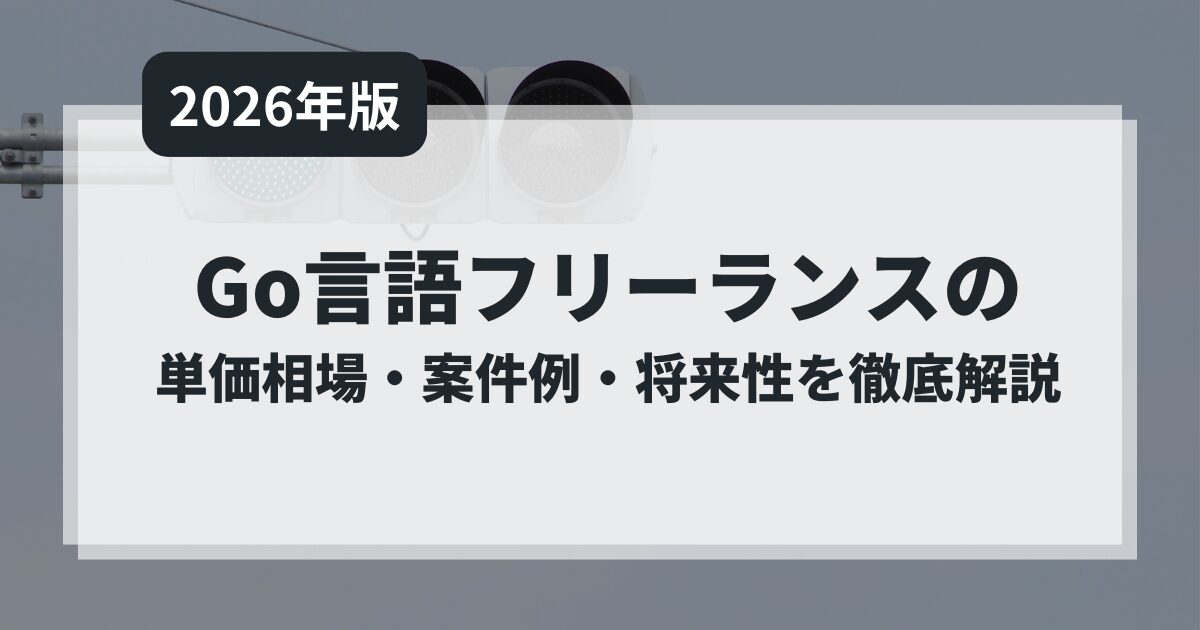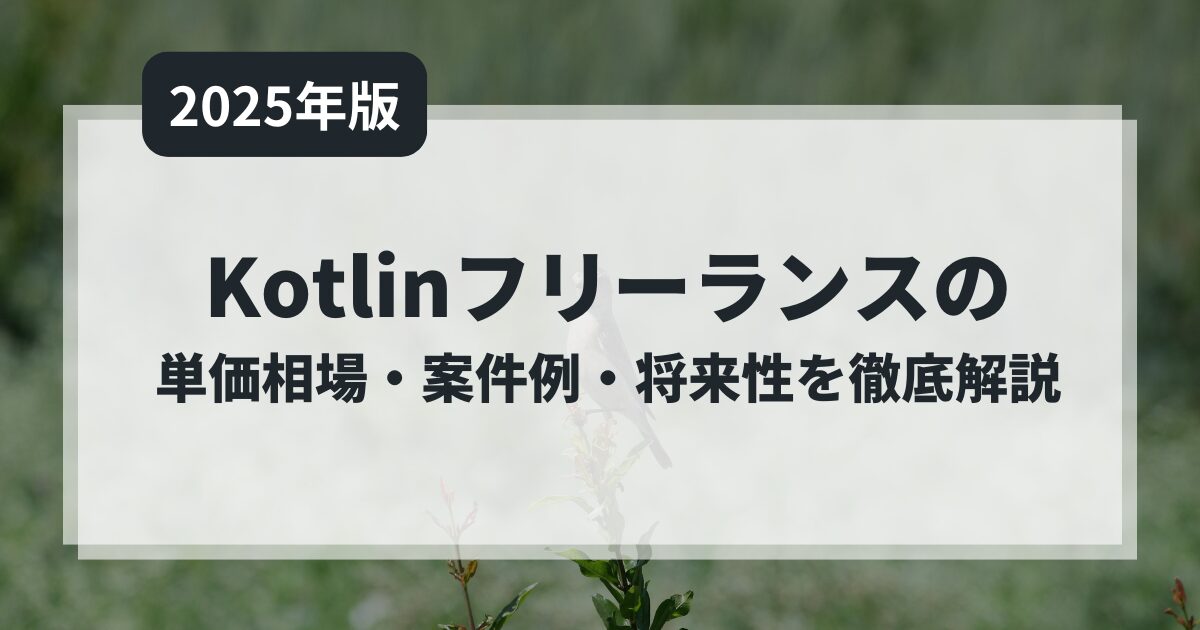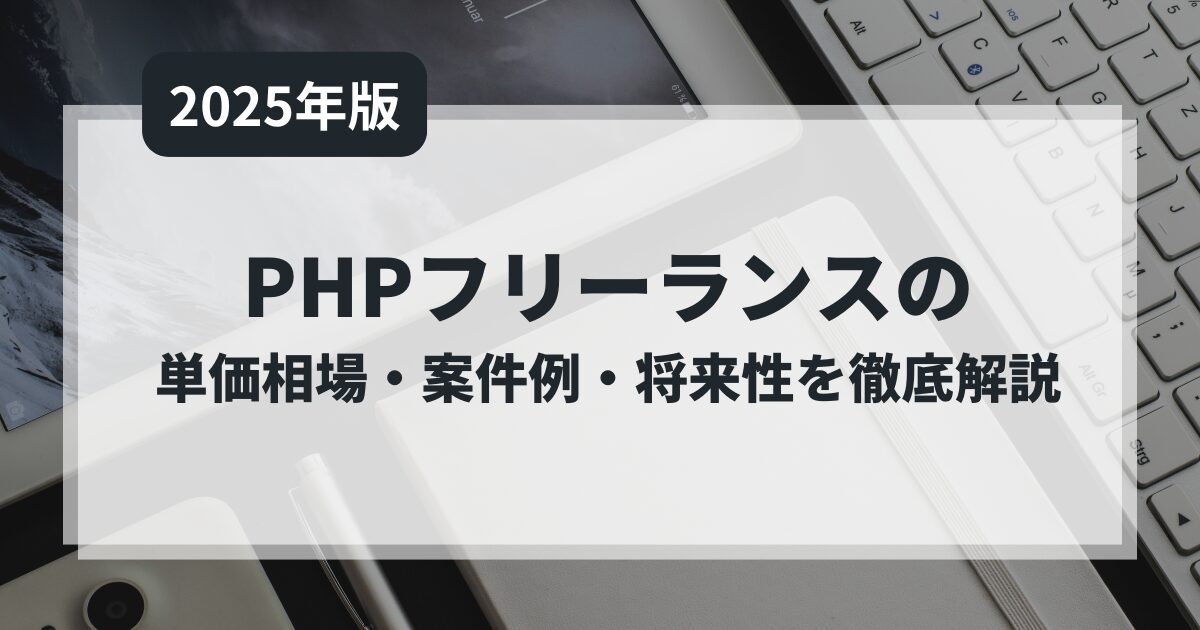日本CTO協会が主催を務め、2025年7月15日に開催された「Developer eXperience AWARD 2025」。「開発者体験と生成AI活用に関する技術広報のリアル〜エンジニアに選ばれる組織づくりとは〜」をテーマに、その知見・経験の共有のためのトークセッションが行われました。
本記事では、登壇者の紹介とテーマ1:「2025年度受賞の感想と1年の振り返りの様子」をお届けいたします。
登壇者紹介
トークセッション登壇者
・日本CTO協会 理事 長沢 翼
株式会社LIFULL / 執行役員 CTO
2008年LIFULL入社。「LIFULL HOME’S」のWeb/iOS開発、API基盤の刷新などをした後、事業系システムのクラウド移行を責任者として実行。2017年にCTO就任し、事業系・社内情報システム領域を担当。また、ベトナム・マレーシア2社の開発子会社の取締役として、国内外含むエンジニア組織を統括し、技術力向上及び組織力強化・開発生産性向上を推進。現在は「LIFULL HOME’S」副本部長として、プロダクトと新規事業を管掌している。
・株式会社LayerX 柴山 嶺
株式会社LayerX CTO室
LayerX CTO室にて技術広報を担当。エンジニアリング組織の成⻑と技術ブランディングに携わり、採用戦略から技術情報発信まで幅広く手がける。東京高専卒業後、スタートアップの創業を経て複数の事業会社でバックエンドエンジニアとして従事。前職ではEM/VPoEとしてプロダクト開発組織をマネジメント。その後LayerXにHRとして入社し、現在はエンジニアリング組織の対外発信と技術コミュニティとの架け橋役を務める。
・さくらインターネット株式会社 長野 雅広
さくらインターネット株式会社 クラウド事業本部 副本部⻑
ミクシィ(現MIXI)、ライブドア(現LINEヤフー)、メルカリなど、複数のWebサービス企業において、信頼性の向上やパフォーマンス改善に従事。ISUCONの創設やSRE組織の立ち上げにも携わる。2021年にさくらインターネットへ入社し、現在は「さくらのクラウド」のガバメントクラウド本認定や、サービスの発展を目指し、開発組織およびソフトウェアエンジニアリングのリードを担う。
・合同会社DMM.com 大久保 寛
合同会社DMM.com VPoE
新卒でSIerに6年勤務。その後、2005年にカカクコムへ入社し、約12年の在籍期間でエンジニアとして同社が運営するサービスをほぼ経験、事業責任者や子会社CTOを歴任。その後、メディア系ベンチャーにてCTOとCFOを兼務。2019年より合同会社DMM.comに参画。
現在は、VPoEとして「人・制度」の領域を主に担当し、社員のパフォーマンス最大化に向けて制度や仕組みの整備を行う。
Developer eXperience AWARD 2025受賞の感想と1年間の技術広報活動の振り返り
株式会社LayerXについて

柴山 嶺(以下、柴山):LayerXは2022年に15位、2023年も15位でしたが、昨年は11位、そして今年は5位と、少しずつ順位を上げています。本当にありがたい限りです。
この1年で特に力を入れてきたのは、イベントの運営です。以前のオフィスにはイベントスペースがなく、執務室とつながった一角で、10人から20人ほどを招いた小規模なイベントを細々と行っていました。そのため、エンジニア社員をはじめ、さまざまな方から「イベントがやりにくい」という意見がありました。
しかし、昨年の春に新しいオフィスへ移転し、数百名が入るほどの大きなイベントスペースを新設しました。それ以降、技術イベントだけでなくあらゆるイベントを毎週のように開催しています。
その結果、多くの方と直接お会いする機会も増え、発信の場もこちらから積極的に作れるようになりました。
長沢 翼(以下、長沢):日本CTO協会でもLayerXさんの会場をお借りしてイベントを開催させていただいていますが、あのようなイベントが毎週のように行われているということなのでしょうか?
柴山:そうですね、毎週のように行っております。単独主催のイベントもありますし、Developer eXperience AWARD 2025 表彰式にいらっしゃるような企業さまとの共催も何度もさせていただいております。
長沢:イベントをやられていて、技術広報陣はすごく大変だと思うんですけど、何人ぐらいでイベント運営されているのですか?
柴山:専任という意味では僕一人ですが、イベントには開発現場のメンバーを巻き込むことが多いです。当日の設営や運営だけでなく、企画の段階から現場のメンバーが関わってくれることも多くあります。
むしろ、僕から発信するというよりは、「こういうイベントをやりたいんだけど、どうかな?」といった相談が現場から自然に上がってくることが最近は増えてきました。
なので、私ひとりで進めているというよりは、それぞれの技術領域ごとに、現場のメンバーと一緒に取り組んでいる感覚に近いですね。
長沢:そうなんですね。やはり意識しているのは、現場を巻き込みながらたくさんイベントを開催していくというところですか?
柴山:はい、そうですね。ただ、率直に言って大変ではあります。
長沢:集客は困らないですか?
柴山:困るケースはもちろんあります。集客に困らないよう企画の内容を尖らせるなどの工夫はしていますが100発100中というわけではありません。思うように集まらないときには、多くの方に集客のお手伝いをしてもらい、なるべく当日を盛り上げられるように頑張っています。
長沢:今この話を聞いてくださっている企業さんは、比較的知名度のある企業が多いと思いますが、そうではない企業の場合、やはり1社の知名度だけでは発信しにくい部分もあると思います。そういった場合に、コラボイベントが開催されることもあるのでしょうか?
柴山:そうですね、共催させていただくことは結構あります。テーマに応じてコラボイベントも積極的に行っています。特に大切にしているのは、参加されるエンジニアやプロダクト職の皆さまに、どんな学びや価値を届けられるかという点です。シャープな切り口や独自の新しい視点・観点を持つ会社さんや、そうした取り組みをされている会社さんと共催ができると嬉しいです。
さくらインターネット株式会社について

長野 雅広(以下、長野):この1年間取り組んできたのが、「採用」です。採用活動を進めるうえで、自分たちでモメンタムを作り出すことが、とても大事だと考えています。
例えば、誰かを採用したら、その方の紹介記事を1週間から1か月以内に出すようにしています。「こんな人が入社したんだ」という話題を作ることで、注目が集まり、また次の採用にもつながっていく。そうしたループを意識的に回してきました。
入社してくれたメンバーの中には社員の紹介で来てくれた方もいます。中には、10年や20年前に一緒にサービスを作っていた仲間もいて、そういった信頼できる方々が再び集まり、モメンタムを生み出してくれています。そうした動きを見た人たちが「自分も入ってみようかな」と思ってくれて、最近はその流れでどんどん人が集まってきている実感があります。
一方で、私たちが取り組んでいる「ガバメントクラウド」には、17の大きなカテゴリがあり、合計で300件ほどの要件をすべて満たさなければなりません。まだまだ緊張感があり、安心できる状態ではありませんが、そこにも真剣に取り組んでいるところです。
長沢:ありがとうございます。今回、Developer eXperience AWARD 2025 7位の受賞コメントでも長野さんは触れていましたが、「これまでランキングで名前がなかったところから、一気にランクインできた」という点が印象的でした。実際にアンケートを集計している立場から見ても、「さくらインターネットさんの名前は、今年本当によく耳にしたな」と感じています。去年あたりから耳にするようになった印象があったので、今年の結果には「やはり来たか」と感じました。採用面では頑張って発信をしていたというお話もありましたが、発信を積極的にやっていこうという呼びかけは、意識的にされていたんでしょうか?
長野:なかなか「やろうよ」と言ってすぐにできることではないと思っています。歴史のある会社で、様々なレイヤーのエンジニアがそれぞれの業務に向きあってきており、行動を起こすにもすぐにできることとできないことがあると思います。
でも、新しく入ってくださった方たちが少しずつ周りを変えていく存在になっています。実際、この2年ほどで入社した方が全社員の中で多数になっており、そうしたメンバーが会社の文化を少しずつ変えながら、情報発信にも積極的に取り組んでくれています。
その姿に影響を受けて、これまで長くいたメンバーも「じゃあ自分もやってみようかな」と発信を始めるようになってきました。そうした前向きな流れが、少しずつできてきていると感じています。
長沢:それは非常にいい流れですね。それこそ、LayerXさんがお話されていたようなイベントは積極的にやられているんですか?
長野:すごく積極的にやっているかと言われると、そこまでではないかもしれません。
ただ、外部のイベントへの協賛はかなり積極的に行っています。例えば先週は「SRE NEXT」、その前には北海道の「OSC(オープンソースカンファレンス)」などと言ったイベントに協賛しています。そのような場に、弊社のエンジニアがどんどん参加している状況です。
長沢:協賛してきたイベントに対する反応はいかがですか?
長野:最近はさくらインターネット株式会社に興味を持って話しかけてくれる方が増えてきたと感じています。以前はサービスの話で終わることが多かったです。しかし最近では、ブースを出していなくても、自分が発表したあとに「どうやってサービスを作っているんですか?」といった質問をもらうことがあります。このように話をする機会が増えたこともあり、だいぶ状況が変わってきていると思っています。
長沢:なるほど、ありがとうございます。
合同会社DMM.comについて

大久保 寛(以下、大久保):正直、今回の結果について「まさか自分たちが取れるとは思っていなかった」というのが率直な感想です。というのも、特に何か特別なことをしたわけではなかったからです。
ただ改めて振り返ってみると、コロナ禍と呼ばれた状況が通常に戻り、リアルイベントなどが再び活発に開催されるようになったことが大きかったのではないかと思います。開催数が0の状態と比べると増えたように見えるかもしれませんが、コロナ禍の前の水準に「戻った」という表現の方が適切だと感じています。
一方で、昨年は採用活動に力を入れており、「自分たちで掲げた目標は必ず達成しよう」と強く言っていました。
結果として、昨年の採用はかなり頑張れたと感じています。
長沢:なるほど、ありがとうございます。今おっしゃっていた「採用を頑張ろう」というお話ですが、これはエンジニアマネージャーの方々に向けてのメッセージでしょうか?それとも、エンジニア全員に向けての呼びかけでしょうか?
大久保:全体にも声はかけていますが、基本的には部室長以上のメンバーに対して、継続的に声をかけることを意識しています。また、特殊な取り組みとして、僕自身はエンジニアを直接探しに行くというよりも、ビジネス側の方を探し、その方からエンジニアを紹介してもらうという動きをしています。
長沢:それは具体的にどのような取り組みでしょうか??
大久保:正直なところ、普段はあまり業務時間外にエンジニアと話す機会が無いです。むしろ外に出て経営者の方と話していることが多いかもしれません。さまざまな人と話していると、エンジニアの方々とは考え方が全く違うと感じます。そうした方々と仲良くなって、「面白そうなエンジニアいない?」といった形で紹介してもらうことが多いです。
長沢:ビジネス側の人たちに、今までつながりのあったエンジニアを紹介してもらって、その紹介経由で実際に採用が決まることは頻繁にありますか?
大久保:本当に少ないです。ただ、すごく優秀なエンジニアは採用できています。
長沢:合同会社DMM.comさんは、2年前にランキングに入っていて、去年は入っていなかったけれど、今年はまたランクインされたという流れかと思います。採用活動で、特に目立った取り組みはありましたか?たとえば情報発信やイベント、あるいは協賛を強化するといった動きがあったのでしょうか?
大久保:特に大きな動きはないですね。ただ、去年の年末ごろにテックブログを会社の公式ブログから分離したことは、影響があったかもしれません。以前は発信内容が全部混ざってしまっていましたが、現在はエンジニアが見たい情報だけが掲載されているブログになっています。そのような変化はあったと思います。
長沢:なるほど、テックブログはエンジニアにとって情報が探しやすいという特徴がありますよね。ありがとうございます。
Developer eXperience Day 2025 イベントレポート一覧
エンジニアが選ぶ1位の企業は!?【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.1
LayerX・さくらインターネット・DMM.comが語る1年間の技術広報【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.2
開発者体験を高める技術広報と生成AIの活用方法とは?【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.3