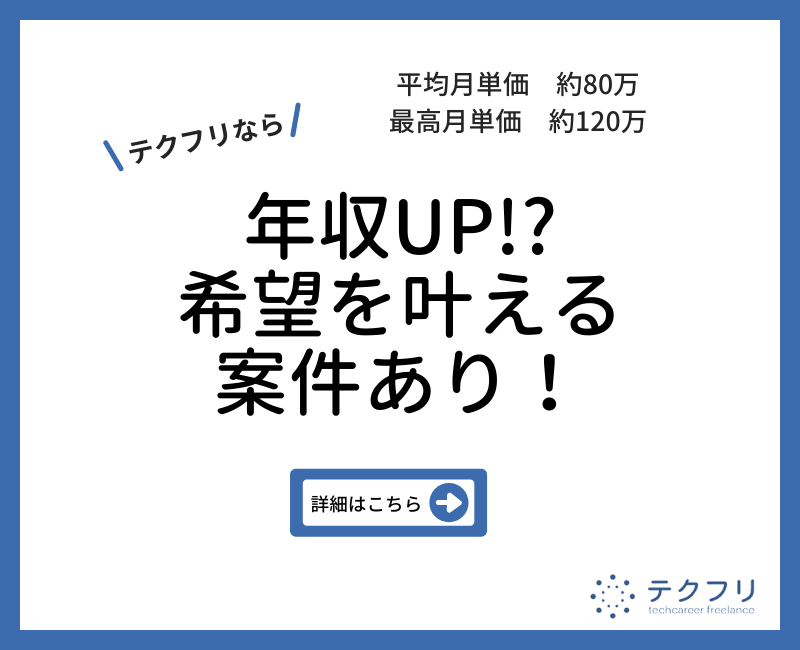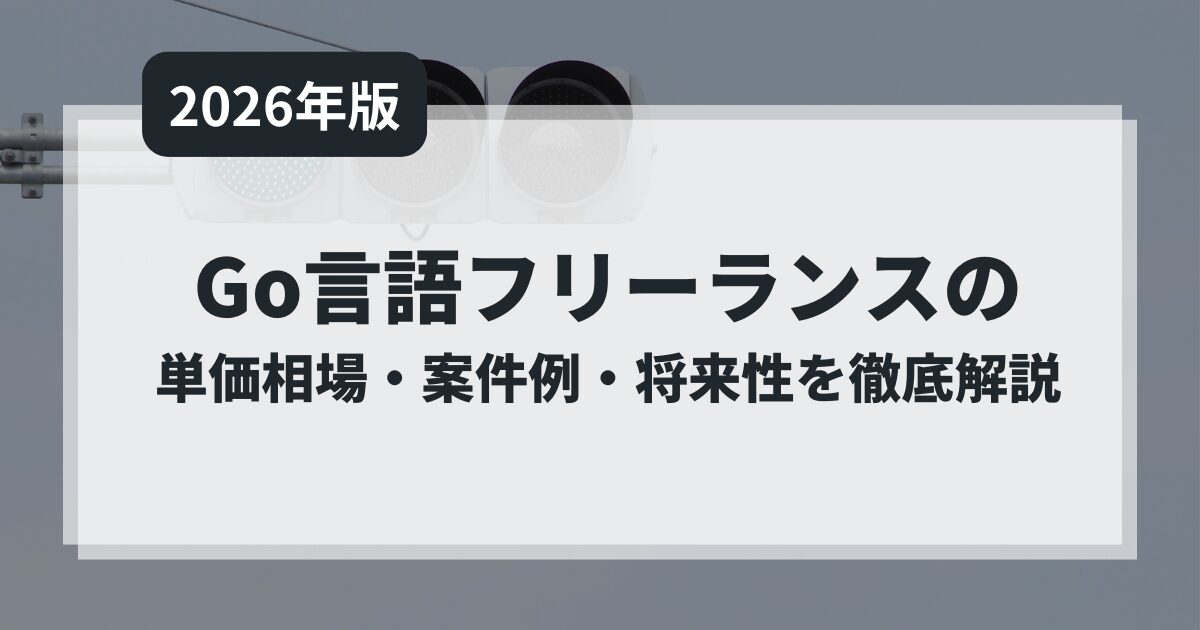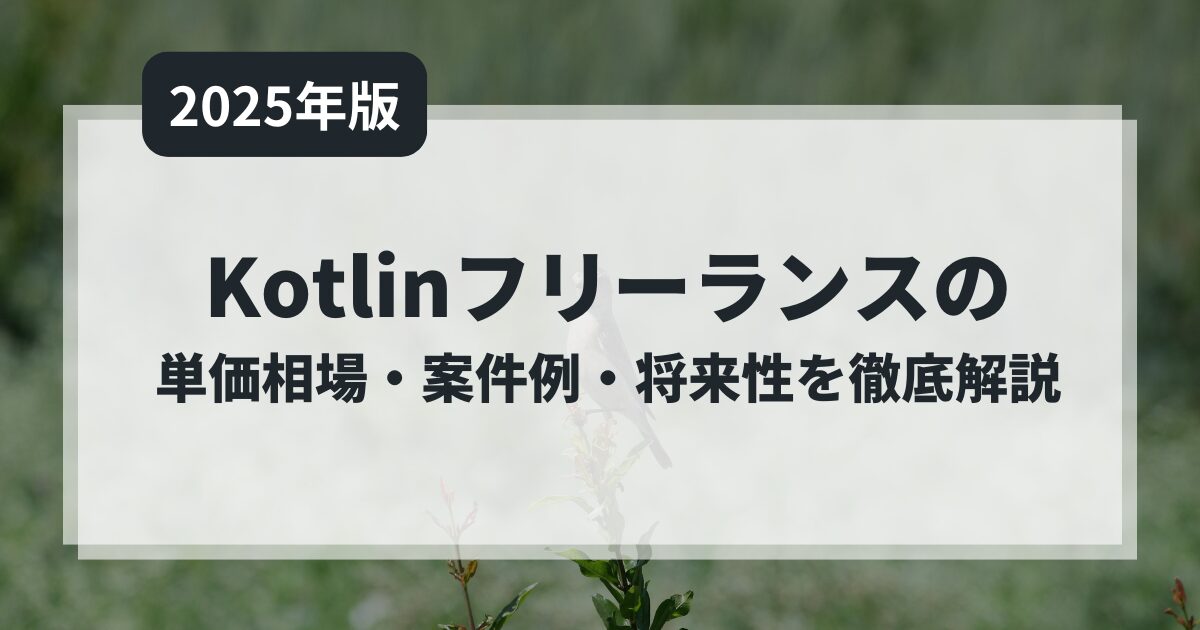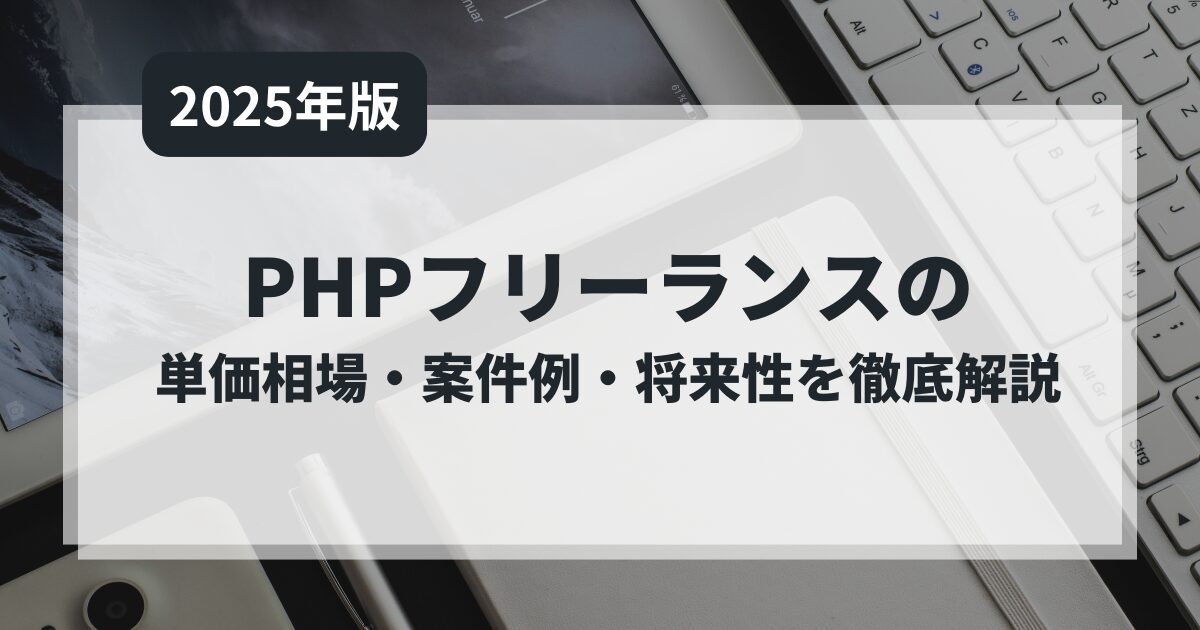日本CTO協会が主催を務め、2025年7月15日に開催された「Developer eXperience AWARD 2025」。「開発者体験と生成AI活用に関する技術広報のリアル〜エンジニアに選ばれる組織づくりとは〜」をテーマとし、その知見・経験の共有とそれに関わる方々のコミュニケーションのためにトークセッションが行われました。
本記事では、「トークテーマ2:開発者体験と技術広報の実践」の様子と「トークテーマ3:生成AI×開発者体験」の様子をお届けいたします。
トークセッション登壇者のプロフィールについては「LayerX・さくらインターネット・DMM.comが語る1年間の技術広報【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.2」をご確認ください。
トークテーマ2「開発者体験と技術広報の実践」
長沢 翼(以下、長沢):開発者体験の向上と技術広報をどのように結びつけているのか、またエンジニア発信者になるためにどのような取り組みを行っているのか伺います。さらに、発信の設計や計画はどのように立てているのか、技術広報活動をKPIや定量的な指標でどのように評価しているのかについても深掘りしていきます。まずはエンジニアの発信をどう促進しているのか教えてください。
大久保 寛(以下、大久保):発信する人が限定されることはよくあることだと思いますので、すでに発信している人に働きかけ、そこから次に発信してくれる人を増やす取り組みを行っています。
これを制度にするとあらぬ方向に進んでしまう可能性があると思うので、「登壇や発信は怖くないよ」「発信したらいいことあるよ」ということを見せて、やってみようと思える文化づくりを意識してます。ただ、社歴の長い方が発信に消極的になりがちになることは答えが出ていない今の悩みです。
長沢:「発信したらいいことあるよ」というのは、何かインセンティブを設定をしているのですか?
大久保:会社としてではないですが、発信した人を称賛することや、「そういえばあれ良かったね」といった話をすることを意識しています。
長沢:人によっては何も反応がないとなかなかモチベーションを保つのは難しいですので、社内から反応がもらえることは結構大事ですよね。ちなみに能動的に発信しているのは何割ぐらいですか?
大久保:1割とか2割とかだと思います。
長沢:LayerXさんはいかがですか。
柴山 嶺(以下、柴山):弊社は、最近エンジニアブログの更新頻度が高まってきています。各事業部やプロダクトチームの中で、持ち回り制で書く取り組みを、部長やテックリードなどが旗を振ってくれています。そのサイクルが複数同時に回っていることで、1週間に3〜4記事、比較的コンスタントに出ています。
弊社には元々、能動的に発信したいエンジニアが多く、自分の中に溜まっている暗黙知を、登壇や技術ブログで言語化していくプロセスをポジティブに捉えています。そのため、背中を押せば「書きます」と言ってくれる人が大半だと思います。
長沢:LayerXさんのエンジニアは特にそのイメージが強いですね。
採用基準に何かを発信しているという条件が入ってるわけでもないですよね。
柴山:カジュアル面談をすると、「発信していないと入社できないのですか?」と聞かれることもありますが、全然そんなことはないです(笑)。
周りのメンバーが自然と発信をしている姿を見て自分も!という気持ちになってくるようで、入社前はほとんど発信していなかったメンバーも自然と発信が増えていくケースを何度も目にしています。
登壇のお声がけをいただくこともあるのですが、どうしても登壇者が偏ってしまいますので、個人的には分散して多くの方に登壇機会を作りたいと思っています。こういうテーマであればこの人も話せるんじゃないかなど、テーマに沿って適切なメンバーを逆提案させていただくこともあります。
長沢:登壇者を選ぶ際、ある程度外からの認知を獲得している人を戦略的に選んで行っているのか、それとも満遍ない形で行っているのか、どちらが多いですか?
柴山:どちらかというと戦略的に行っている部分もあります。会社として「◯◯という領域で◯◯という認知形成を行いたい」とした際に、適切な人選をすることで、より高い効果を狙うイメージですね。
長沢:そこから認知を取っていきたい領域と、外部から登壇依頼が来る領域が違う可能性もあると思います。
例えばアプリエンジニアを採用したいけど、フロントエンドの依頼ばかりくるなどの場合は、アプリエンジニアに関する登壇を取りに行ったり、作りに行ったりという活動もしますか?
柴山:まず、前提として登壇依頼をいただけるだけでもありがたいと思っています。基本的にはなるべくお受けするようにはしていますが、業務の兼ね合いでお受けできないときもあります。会社として別の領域の認知を取りたい時、例えばモバイルアプリのところを認知取りたければ、自分たちでイベントを企画して、他社さんに登壇のお願いをする動きもしています。
長沢:登壇者を誰でいこうというのは社内のどこの人たちと相談しながら決めるんですか?
柴山:起点としてはエンジニア採用の担当者やハイアリングマネージャーと相談して決めることが多いです。
採用の観点で「この分野の認知を取りたい」という相談から始まり、「だったらこんなイベントはどうか」という流れになります。その後、現場のエンジニアとこんな話があるけどどうかなと言うような感じでふわっと始まり、企画ができるといった流れです。こうしたラインが複数並行して走るイメージです。
長沢:さくらインターネットさんはこの領域を取りたいから、ここの認知を取りに行きたいと言う動きを計画的にやられたりしますか?

長野 雅広(以下、長野):そこまで長い期間の計画はまだ、立てられてはいません。
どちらかというと、協賛するイベントや参加するイベントでそのイベントでどういう方が登壇すると良いのかという点を重視しています。コミュニティによって登壇者を社内で選ぶ際は、基本的にそのコミュニティに合わせることを前提に、すでに名があるエンジニアを中心に、チャンスがあればこれから認知を図っていきたい別のメンバー、今採用に力をいれたいチームにお願いしています。
また弊社では、認知をさらに広めるため、外部で発表したものをエンジニアブログで記事として二次利用する事が多いです。
長沢:発信者のお話でいくと、新しく入ってきた人は結構発信するけど、長く在籍している人はなかなか腰が重い方もいるというお話がありました。エンジニア全体で見ると、発信する人としない人の割合はどのくらいですか?
長野:半々ぐらいです。最近入ってきたメンバーは発信や自分でイベントをやっていくことに非常にモチベーション高くやっていただけますし、以前から長く弊社にいる方に対しても声をかけお願いすると社内外のイベントを含め、実はやっていただける方が多いです。
長沢:発信していく空気を作っていくのは非常に重要だなと聞いていましたが、社内で「なんで発信が大事なのか」というような話をされるんですか?
長野:今、私たちの大きな課題は採用にあります。そこで自分たちに必要な仲間は自分たちで取りに行こうとは言っています。各個人に採用目標を持たせているわけではないですが、仲間を自分たちで採用していくためにも、情報発信をみんなでやっていこうという感じです。
採用時に関しても、意識して発信してくれるような人を積極的に採用しているわけではないですが、最終的に仲間を増やすということについて、「自分たちごと」としてできるかという点をなんとなくイメージとして持っている方が多く入社されていると思います。
長沢:なるほど。
またかなり難しい質問だとは思いますが、自社での成果の測り方や独自の数値・ブログ本数など、参考指標として見てるものはありますか?
長野:弊社の場合は応募の観点を見てますね。どういうところを通って応募して来てくれたのかというところは、人事と定期的にミーティングを行いその数値を追いかけています。
2年前はエージェントからの応募も非常に多かったのですが、今はリファラルが多くなり、徐々に直接応募が多くなっているという変化もあるので、その数字を追いかけています。
長沢:理想的な形になっているんですね。
LayerXさんはありますか。
柴山:特にKPIを追いかけているわけではありません。採用エントリーいただく際に「何のメディアを見たことがありますか」というアンケートを取得しています。技術的な発信数は毎月「技術広報月報」を社内向けに公開していて、今月は何十件の発信、何件の登壇があったというのをグラフで追いかけられるようにしています。視覚的に傾向も見えるため、貴重な参考指標としています。
長沢:ちなみに部門ごとに数字を出すんですか?
柴山:部門ごとではなく、会社全体の技術発信数で見ています。最近はコンスタントに月間で数十件、単純計算すると1営業日に2件ぐらい何かしら技術的な発信が出ているようになっています。
長沢:ちなみにXで強力なパワーを持って運用している社員の方も多いと思いますが、ポストを見ていたり、何か参考にしていますか?
柴山:個人としてフォローはしていますが、それを見てこういう発信をしようとかは言いませんし、今後も言うつもりはありません。「メンバーは今、何に興味があるのかな?」と。話は逸れますが、会社の公式Techアカウントの運用は約一年半前から始めたのですが、僕が9割5分ポストしています(笑)。
長沢:何か運用していて気づいたことがありますか?

柴山:まずは思った以上に大変ですね(笑)。世の中の「中の人アカウント」は努力の上に成り立っているなっていうのを日々痛感しています。また、どういう切り口で何を伝えるかは結構難しいです。バズ狙いのポストはせず、着実にフォロワーを増やしていきたいのですが、SNS運用の難しさを感じています。
運用で工夫をしている点としては、LayerXの技術発信情報が届くというところはもちろん、中の人の様子が見えることを意識をして、ポストの仕方とかを少し変えています。
最近はClaudeに、テックブログのURLを渡すと、投稿案を自動で3つ考えてくれるようにしたりして、結構楽になってきています。
長沢:きっと各社がやっていそうですね(笑)。
DMM.comさんでは技術広報活動のKPIだったり指標といった部分はいかがですか。
大久保:数字を追いかけると、それが目標になってしまうところがあるので、弊社もモニタリングにとどめています。
一方で、外部発信を自ら積極的に行っている方を採用するケースもありますが、40歳以上の方はそのような発信をしている人が少ない印象です。
もしそうした層を採用したいとなったとき、どう接点を持つべきか……そこにまだ明確な答えが見つかっておらず、悩んでいるところです。
長沢:メディアの選定で対応ですかね?
大久保:メディアに発信する以前に、その層はそもそもメディアを見てない人が多い気がします。
年齢で区切って採用をしているわけではないですが、40歳以上の方に、退職までバリバリ手を動かして欲しくなったときに、どのメディアやリーチ方法が有効なのか、模索中です。
長沢:各社、数字自体はいろいろモニタリングだったり観測しているものはあるけど、ガチガチにKPIマネジメントをしながら、数字を追っている感じではない雰囲気ですよね。ちなみに記事を書く中身は大久保さんとかは決めていたりするんですか?それともエンジニアの主体性に任せていますか?
大久保:基本はお任せです。中身を見ていいなと思うものもあれば、もう少し書き直してみようということもたまにあったりします。
長沢:エンジニアブログに関して各社さん、品質チェックやレビューの体制はどういう対応をされてますか。
柴山:弊社の場合、技術発信については原則、マネージャーレビューでOKにしています。誰のレビューも通らずに公開されることは一定のリスクがありますので、マネージャーの目は必ず通してくださいという形でやってます。
そのため、僕が知らない間に公開される記事もあります。
仮に、公開後にもう少し直してもらった方がいいかなと思う箇所があっても、執筆、公開してくれた事が尊いので口うるさくいいたくはありません。次の機会でそこがブラッシュアップされるようになればいいと考えています。
長野:2ヶ月前くらいに、自分で書いたガイドラインには、基本的にそのチームでレビューしてくださいと書いています。
チームで行う意義については、なるべく記事を書いた人を後押しする・チームの発表する人を後押しするために、チームみんなでレビューしていいものにしていきましょうという思いをガイドラインにまとめました。
長沢:ガイドラインにはどういう項目があるのでしょうか?
長野:細かいことは書いてはないです。発信内容のガイドラインとどうやってやるかのガイドラインの2つに分けてあって、発信内容については、機密情報・知的財産に関連しそうな事柄や他社との比較など一般的な注意事項がほとんどです。
どうやってやるかについては、レビューはチームで行いましょう、称賛し合いましょうといったような感じです。
長沢:LayerXさんはガイドラインはありますか?
柴山:ないですね。執筆ブートストラップのドキュメントがありますが、アカウントの接続の仕方でとどまっていて、正直何もないです。作らなきゃいけないと思いました(笑)。
大久保:弊社はガイドラインは明確には示してないです。ただ、内容というより、日本語の表現の問題が結構多いと思っていて、そこを人が指摘するとむっとなっちゃうので、AIに任せようと今思い始めました。
トークテーマ3「生成AI×開発者体験」
長沢:業界としても生成AIの変化が大きい中で、皆様自身、またご自身の会社の中で開発者体験を考えたときに、AIをどのように活かしているのか、社内で使うときに何か工夫している点はあるのかを幅広く聞いていきます。
また、技術広報活動の際に工夫されていることも伺っていきます。
柴山さんはXのポストをするときにAIを活用しているお話もありましたが他の部分、もしくは開発者体験の観点からお話があれば教えてください。
柴山:開発者体験の方に焦点を当てますと、Claude CodeのMAXプランを希望者が使えるようにすることは、比較的インパクトがある意思決定だったと思っています。
トップとボトムの両方から「Claude Codeを使いたい」という声が上がり、それを実現するためのガイドラインが社内で急速に整備されました。その結果、生成AI系のサービストライアル予算の中で、まずは利用を開始しました。
こうした取り組み自体は面白いと思っています。弊社が提供する法人カードサービス『バクラク』を利用することで、ガバナンスを保ちながらスピーディーにサービスの支払いができました。これが導入の意思決定を後押しした大きな要因の一つであり、弊社らしい事例だと思っています。
長沢:利用しているのはエンジニアのみですか?
柴山:Claude CodeのMAXプランは基本的にエンジニアのみですが、最近はプロダクトマネージャーの希望者もAPIキーを払い出して利用しているケースもあると思います。
自分自身の技術広報に関する影響としては、記事を書く時にClaudeを使っていますが、今までの1/8ぐらいのスピードで書くことができているのでとても助かってますね。
長沢:さくらインターネットさんではいかがですか。
長野:弊社はChatGPT Enterpriseを全社で導入していることと、各エンジニアが業務で使うClaude CodeやGeminiの利用料を経費精算ができる取り組みをやっております。ただ、一つ課題だと思っているのが、使う人と使わない人ですごい差ができてしまっていることです。
どんどん使いこなす方がいる一方、そうではない方も一定数いるのではないかと思ってます。、また、エンタープライズ導入したことだけで止まってしまっていて、APIを使うこともまだ社内では出来ていないです。そういう時に、社内のデータを活かして生成AIを使いながらどんどん便利にしていく、本当の意味でのDXを目指していきたいなと思っています。
長沢:どんどん使う人は使ってはいるが、プロダクションコードとかではあまりまだ使っていないということですか?
長野:そうですね。GitHub Copilotまでは業務で使用OKになっていますけど、それ以上はまだ業務では使えないですね。
長沢:個人の裁量というよりは、一応全体のルールでこのツールだとプロダクションコードは触ってもいいけど、このツールはダメっていうような線引きをしながら導入進めている感じなんですね。線引きをするうえでどうやって判断していますか?
長野:それをどうするか・どうしたら良いのかをセキュリティチームと確認しながらやっていくことになるのかなと思います。生成AIツールがどんどん出てくるので判断軸が難しいところかなとは思っています。
長沢:そうですね。ツールが多すぎてどれを使ったらいいかわからないという状況はありますよね。
大久保さんはいかがですか。
大久保:新しいツールを使いたいという声は都度判断しています。ただ、一年前と今とで使ってるツールが変わっていないみたいなのが結構あるので、そこは意識して変えていっています。
開発者体験って言葉自体も多分変わっていくんだろうなと思っていて、どう捉えるか、逆に開発者体験自体がなんか苦痛に感じるようになっちゃう人たちが出てくると思っています。
この点に対してどう向き合おうかみたいな話を最近し始めました。割とAIを使いこなしている方が「今までと違う脳みそを使ってるからすごい疲れるんです」と言うようになっているんです。ただ効率は上がっているので、そうした場合に立場として何をモニタリングするとみんなの健康状態が適切に確認できるんだろうと本当につい最近考え始めたところです。
あとはエンジニア以外の人もどんどん使っていきましょう、というのは常に言っていますね。

長沢:そうですね…AIを使うことによる疲弊に関しては難しいところですね。
ちなみに、もし自社で生成AIで書いた記事が発信されていたら分かりますか?
柴山:なんとなくわかりますよね。たとえば見出しの書き方とか、今までとは異なる文体だと、AIに書いてもらったんだろうなと思うときもあります。
読者体験が大きく損なわれるようなときはフィードバックを行いますが、見出しの部分を生成AIで書いているぐらいであれば、全然いいと思います。そこはAIと人の協働で、模索しながらやっていると思いますし、今後テクノロジーが一定解決するだろうなとは思いますね。
大久保:その点で言うと正しさの確認が結構難しくなったなと思っています。プログラミングとか、システムの正しい正しくないの判断はできると思っているんですけど、ChatGPTとかで出てくるものの、正しさを判断するのは昔よりすごく難しくなった感じはあります。
柴山:コンテンツを作るスピードは上がるが、その正しさを保証するスピードは上がらないのでレビュアーやコードレビューが大変という話もあります。
そういうコンテンツにおいても技術的面になればなるほど、ファクトチェックをどこまでやるかは大変難しいとは思います。
長野:さっきお話しした発表のガイドラインの作成も同じ時間だけレビューはかかってしまいますが、実はChatGPTでチェックと言葉の取捨選択をしながら最終的な文章を作っていきました。
長沢:やはり正しさの判断は難しいですよね。
技術広報周りとか発信周りに関しても、今後もAIの活用が増えてくるので、これが解決策だというのは世の中的にはまだないですが、いずれ解決策も出てくればいいのかなと思っております。
それでは、最後に各社様から一言ずつ最後いただいて、このトークセッションを締めたいと思います。
長野:お客様ときちんと向き合って、お客様の課題を解決できるクラウドを作る必要があると強く思っています。そのためにできる高い技術広報を積極的に発表して、お客様に近づきながらクラウドを作ることにこれからも取り組んでいきたいです。ここにいらっしゃる皆様にも、弊社のクラウドを使っていただけるように、努力していきたいです。
柴山:生成AIの波であらゆる地殻変動が起きていると思っています。コンテンツ生成のコストは大きく下がっていますが、それを消費する人間の時間が増えているわけではありません。どのようなコンテンツを出していくかの質がより問われる時代になってきているように感じています。
外的環境がものすごいスピードで変化していくなか、当然自分たちも変化し続けなきゃいけません。そうしたときこそ、日本CTO協会の皆さんがまとめてくださったレポートを参考にしながら、弊社にはこういう発信が足りないんだなどと考え、アクションを続けたいと思いました。本日はありがとうございました。
大久保:技術広報としては、楽しさが重要だと思っています。楽しそうにしている集団がいたら気になると思うんですよね。それが内部にも外部にも見えるようになったら、応募してみようとなると思っているので、その点を大切にしていきたいです。
特に内部観点としてリーダーとかマネージャーはやりたくないっていう人、けっこういると思うんですよね。
でも、とりあえず『仕事を楽しもうぜ』っていう空気があると、だんだんそういう役割にも興味を持ってくれる人が増えていくんじゃないかなって。
今日改めて、そこはもっと強めていきたいなって思いました。ありがとうございました。
Developer eXperience Day 2025 イベントレポート一覧
エンジニアが選ぶ1位の企業は!?【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.1
LayerX・さくらインターネット・DMM.comが語る1年間の技術広報【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.2
開発者体験を高める技術広報と生成AIの活用方法とは?【Developer eXperience AWARD 2025】イベントレポートVol.3