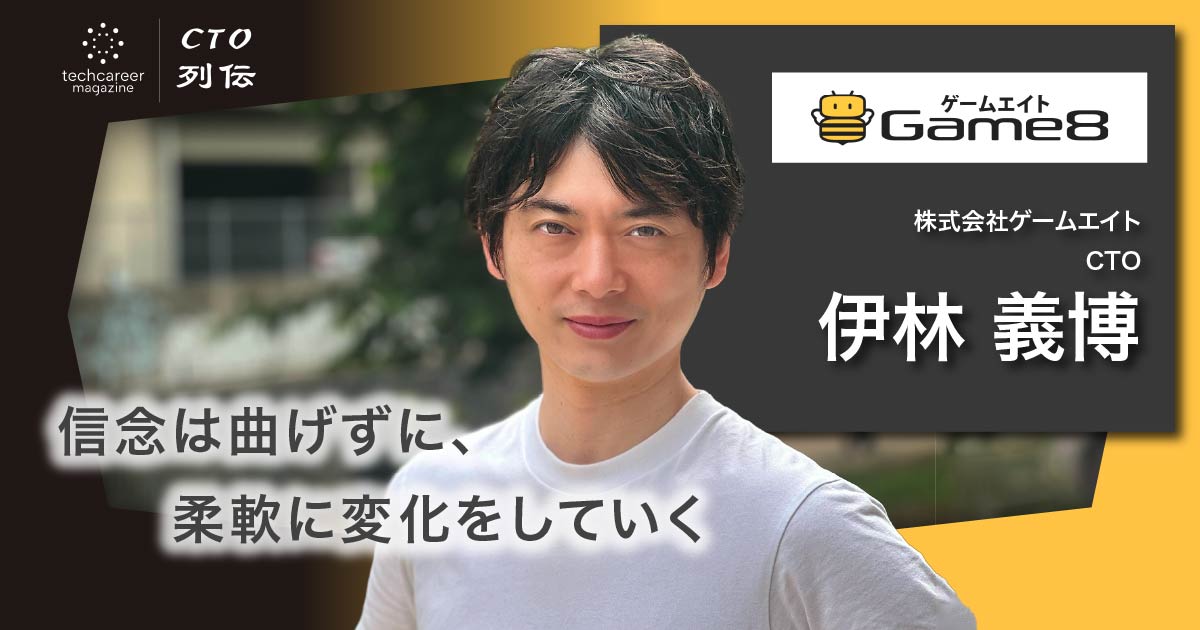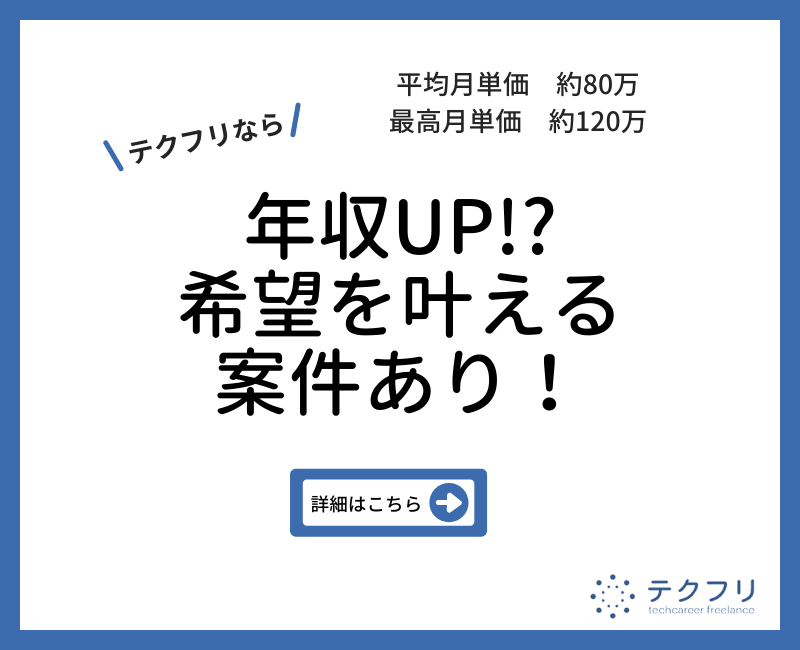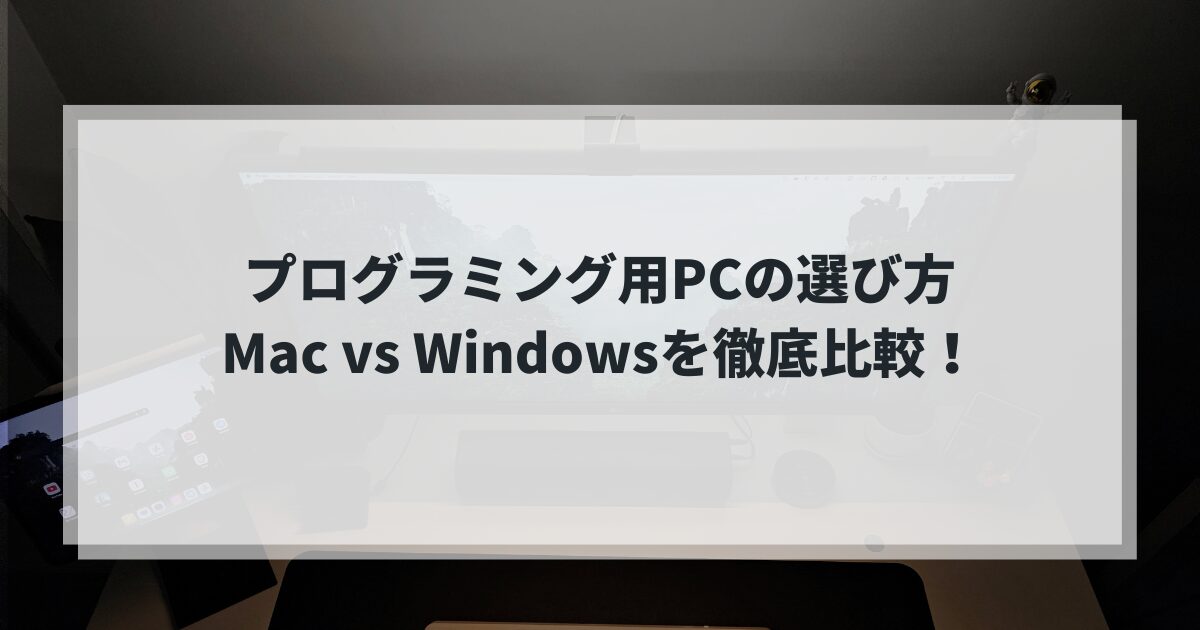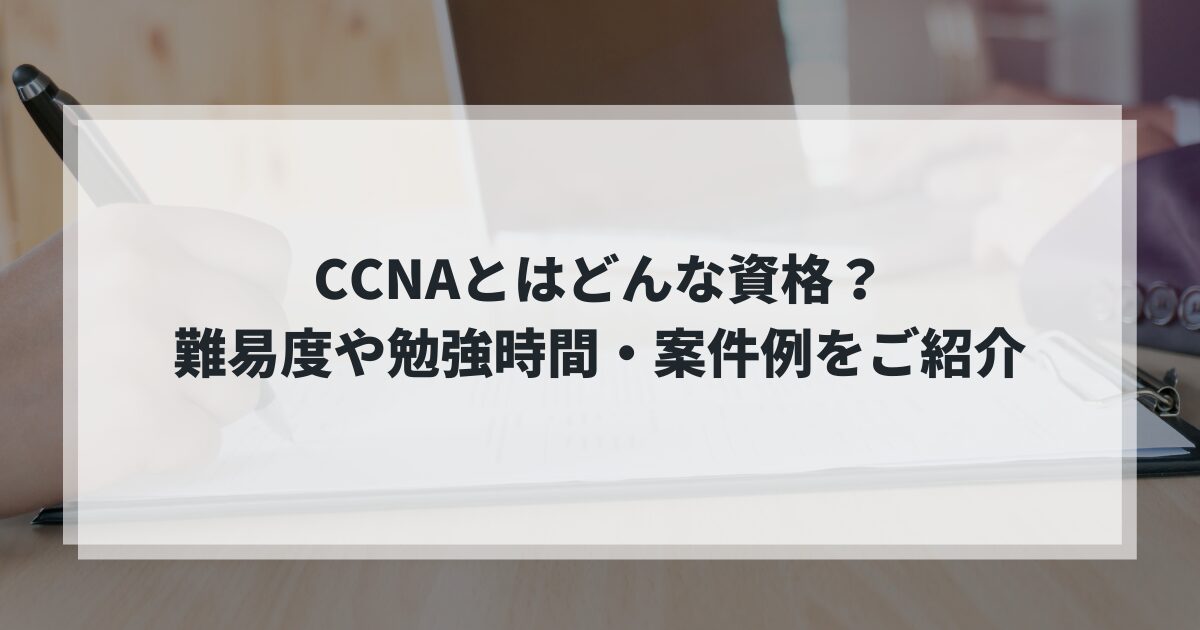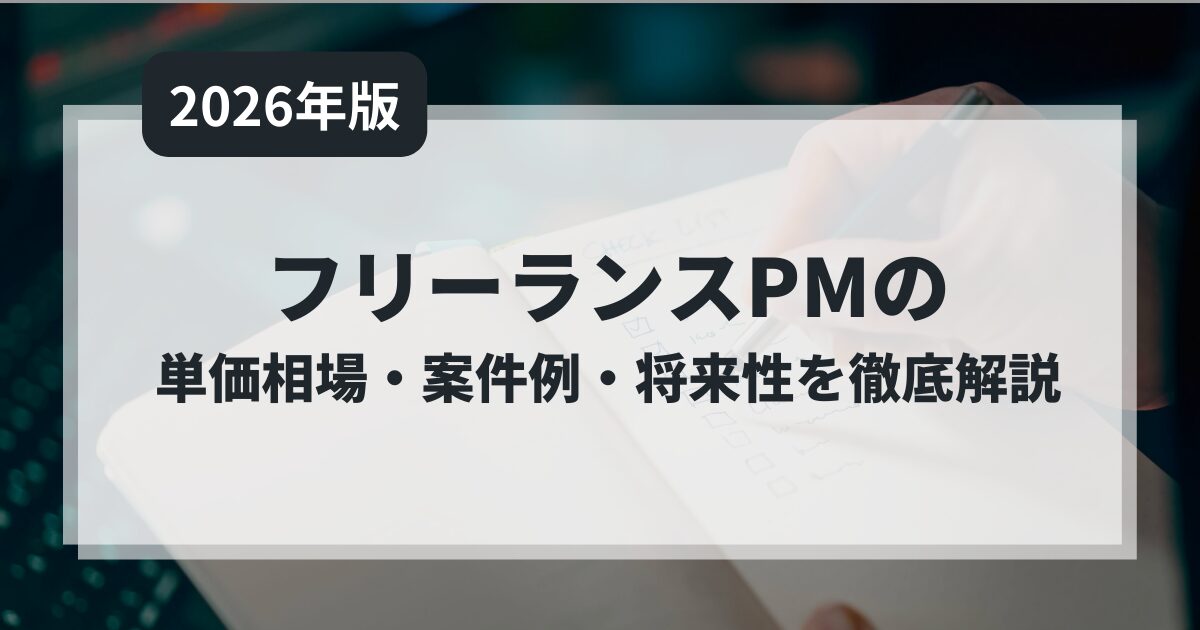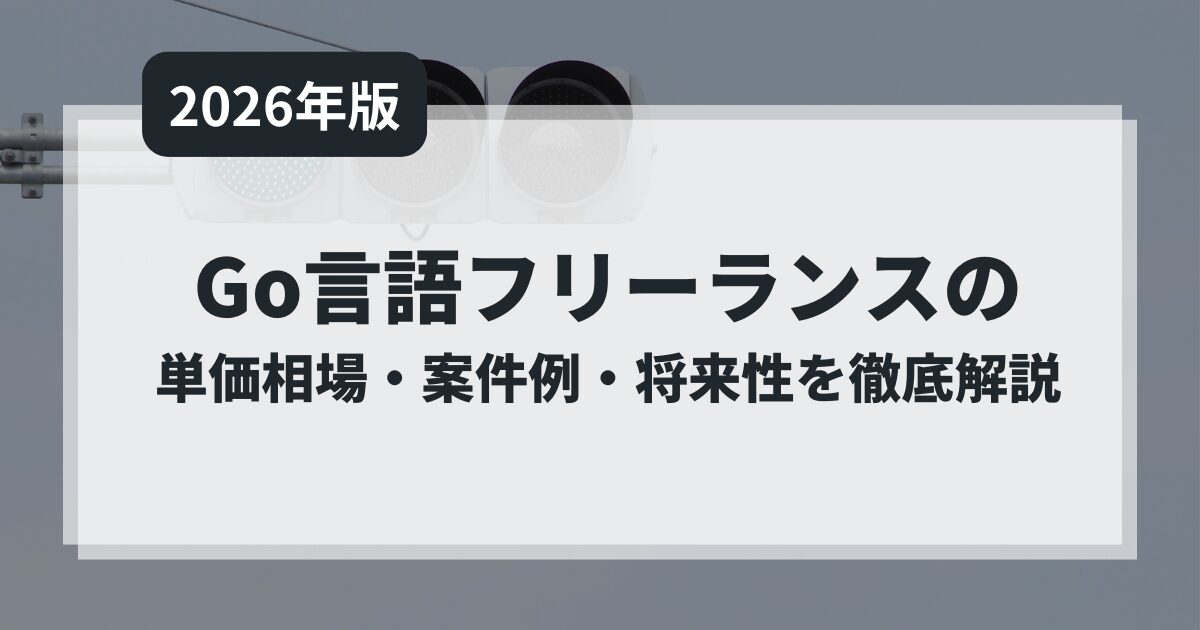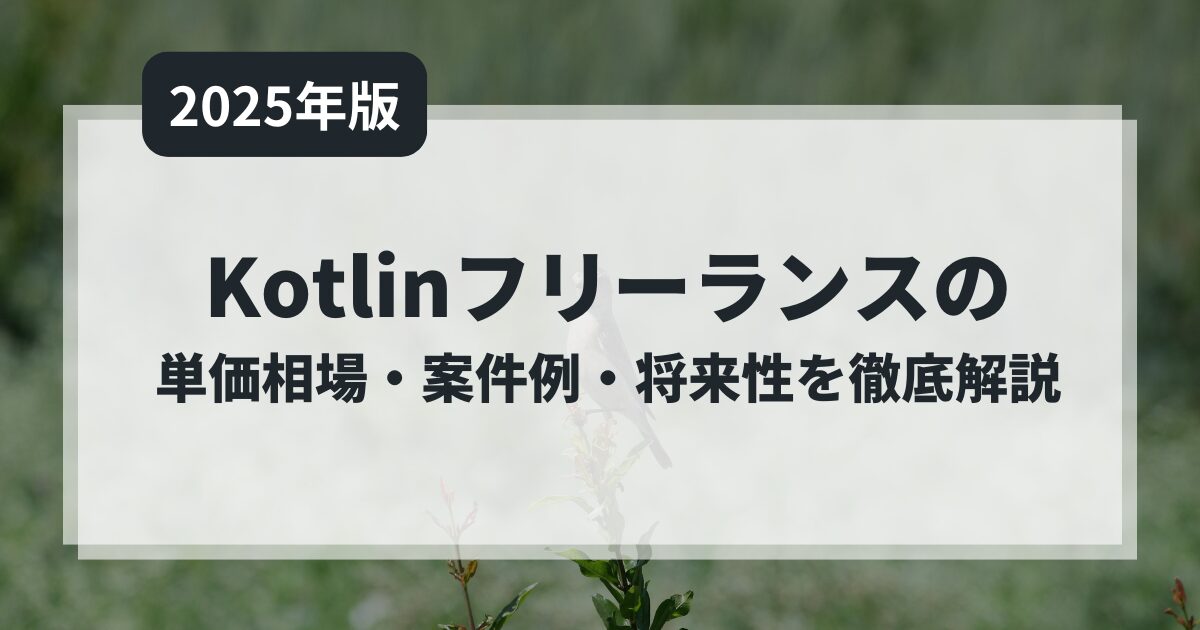今回は株式会社Initial Engineで取締役CTOを務める佐藤 龍太さんのインタビュー記事をお届けします。佐藤さんは、もともと文系出身で、新卒で入社したワークスアプリケーションズでエンジニアの道に足を踏み入れました。その後、株式会社奇兵隊でのグローバルSNS開発、テクロスホールディングスでのCTOアドバイザリー業務を経て、現在はInitial EngineでCTOとして活躍されています。そんな佐藤さんが考える、AI時代のエンジニアにとって必要な要素は、「問いを持つこと」と「コミュニケーション能力」。技術と経営の両面から企業のDXを支援する現在の取り組みや、これからのエンジニアに求められる資質について伺いました。
インタビュー概要
お話を伺った企業さま
会社名 :株式会社Initial Engine
設立 :2024年2月
資本金 :10,000,000円
上場市場 :未上場
代表者 :佃 松三郎
所在地 :東京都新宿区
ミッション :必要とされる場所に、私たちの知恵と経験を。
事業内容 :DXコンサルティング / CTOアドバイザリー / CIO補佐官
URL :https://www.initial-engine.io/
お話を伺ったご担当者さま
部署 / 役職 :取締役 CTO
氏名 :佐藤 龍太
2011年に株式会社ワークスアプリケーションズにエンジニアとして入社。
2015年にグローバル市場を狙うスタートアップ、株式会社奇兵隊に参画。
2017年に取締役CTOに就任し、経営・開発・組織に向き合いながら、さまざまな事業に携わる。
日本CTO協会ではコミュニティWGでディレクターを努め、CTOコミュニティ活動に注力。その後、複数の企業に対して技術顧問や開発サポートを実施し、2023年に株式会社テクロスホールディングスにCTOとして入社し、現職。
キャリアについて
文系学生がプログラミングに触れた学生時代
私はもともと文系学生だったので、昔からエンジニアを目指していたわけではありません。学生時代はバスケットボールに打ち込み、英語に興味を持って海外を放浪していた時期もありました。そして就活時期に初めてプログラミングに出会います。海外への興味から、就活の際にはグローバル志向を重要視して企業を探していました。そんな中、ワークスアプリケーションズの選考を受けた時に、プログラミングの課題が出たんです。Delphiでシステムを作ったのですが、自分で作ったものが目に見える形になったことに面白さを感じました。私はもともと、数学などの理系科目は得意ではなかったんです。しかし、この経験をきっかけにエンジニアの道もありだなと思い始め、ワークスアプリケーションズから内定をもらえたので、入社することになりました。
ワークスアプリケーションズ時代:ゼロからの挑戦
ワークスアプリケーションズではエンジニア職確定というわけではなく、半年間の研修後に、営業・コンサル・エンジニアのいずれかの職種に配属されるというものでした。私は、エンジニアかコンサルを志望していたのですが、たまたまエンジニアリング配属になりました。
初めて担当したプロジェクトは、Javaを用いた勤怠システムのパッケージ開発です。ほぼ未経験だったので、当初はめちゃくちゃ苦労しました。全然わからないことだらけだったので、書籍などを用いてとにかく時間をかけて一つ一つ解決していく日々。自分で考えることを重んじる社風があったので、必死に食らいついていました。
奇兵隊時代:手触り感のある開発を求めて転職
その後、先輩が立ち上げた株式会社奇兵隊に転職しました。転職の動機は、より手触り感を持ってプロダクトを開発したかったからです。前職では大規模なプロダクトを開発していたので、正直、自分の提供価値を感じにくい状況でした。一方で奇兵隊は、立ち上げて間もないスタートアップだったのと、BtoCサービスを提供していたんです。一般的にBtoCサービスはリリースするとユーザーの手元にすぐに届くので、ユーザーからのフィードバックがよりダイレクトかつ早く聞けるという特徴があります。そういった環境であれば、より手触り感を持って開発できると感じ、転職を決意しました。また、グローバル市場をターゲットにしている点も自分としては魅力的でした。
入社後は、海外の友達を作れるSNSの開発に携わりました。ちょうどInstagramが有名になっているタイミングだったこともあり、日本初のグローバルSNSとなるべく取り組みました。私が担った具体的な業務内容は、Android Javaを用いたネイティブアプリの開発です。前職ではずっとJavaで開発していましたが、Android Javaということでまた違った難しさがありましたね。入って1年ほどはプレイヤーとして開発業務を中心に担当。Ruby on Railsなどもこのときに習得していきました。
奇兵隊時代:CTOとしての挑戦と苦労
入社して2年ほどたったタイミングで、取締役CTOを任されることになりました。最初は「CTOって何をすれば良いの?」という状況でした。今でこそ情報はそこら辺に落ちていますが、当時はCTOについて体系化された書籍も少なかったんです。そのため、とにかく他社のCTOと会って話を聞くことにしました。その中でも、AWS主催のCTO Night & Dayはすごく良い経験になりました。CTO Night & Dayとは、CTOが100名ほど集まって1泊2日でディスカッションしたりするイベントです。知り合いが全くいない中で参加したのですが、多くのCTOと話すことができてたくさんの学びを得ることができました。
CTOに就任した当時は、開発チームもまだまだ組織化されていない状況でした。そのため、コードを書くことからマネジメント、評価方法の策定など、多岐に渡る業務をこなす必要があったんです。また、メンバーも外国人メインだったので、コミュニケーションは大変でした。それでもコツコツと取り組み、経営目線を持ちつつ技術的な視点から会社を成長させられるよう努力しました。
Initial EngineのCTOに就任:DX支援でITに悩む企業を救う
奇兵隊時代にたくさんのCTOと知り合うことができました。その中の1人であるテクロスCTOの佃さんと食事に行く機会があり、「新しい事業を構想中だから一緒にやらないか?」と誘われたんです。奇兵隊のCTOとしての経験を活かして十分に貢献できると思い、転職を決意しました。入社後はDX事業部にて、主にスタートアップ〜上場手前の企業のEMや組織構築・マネジメント支援を中心に、エンジニアを対象とした評価プロダクトの開発などに携わりました。
その後、DX事業部をスピンアウトするかたちで現在のInitial Engineが設立されました。現職でもテクロス時代と同様、IT領域で課題を抱える企業様のDX支援を行っています。最近ではコードはほとんどAIに書いてもらっていますが、今でもさまざまなエンジニアリングをしながらマネジメントもやっています。
自分を成長させてくれたのは、手触り感のある開発経験
エンジニアとして一番成長できたと実感したのは、奇兵隊時代の経験です。スタートアップという環境で、ユーザーに近い距離でプロダクト開発ができたことがその理由です。プロダクトをリリースすると、すぐにユーザーに使ってもらえ、フィードバックが返ってきます。自分の知人にも使ってもらっていたので、常にユーザーの顔を浮かべながら開発を進めていました。彼らに良いものを届けたかったので、ユーザーのフィードバックを元に、UX設計から開発までかなり力を入れて取り組んだので、短期間ですごく成長できたと感じています。
人とAIの力で、ITに悩む企業を救いたい
現在の私の目標は、Initial Engineにて1社でも多くのITで悩んでいる企業を救うことです。それに向けて、会社規模をさらに大きくしていく必要もあります。今は人を介したDX支援がメインですが、今後は人に加えてプロダクトの力を活用してやっていきたいと考えています。AIと人間が共存するためにはどうすれば良いかを考えながら、お客様にとって最適なソリューションを提供していきたいですね。
考え方・マインドについて
大切にしている3つのバリュー
CEOと一緒に作った、Initial Engineのバリューが私の行動指針でもあります。
1つ目は「Understand deeply(理解せよ)」です。自分を理解できているから他者も理解できる。他者を理解できるようになると、技術やクライアントの課題も理解できるようになり、より良い価値を提供できると考えています。
2つ目は「Be a giver(与えよ)」です。Takerになっても何も良いことはありません。Giverの姿勢を大切にし、チームとして成果を出すことを重要視しています。
3つ目は「Stay good mood(ご機嫌であれ)」です。全ての源は自分の機嫌だと考えています。不機嫌な時に仕事をしても成果は出ないので、周りにもポジティブな影響を与えられるよう心がけています。
AIに代替されない「問い」と「コミュニケーション」が重要
時代を考慮して、今価値あるエンジニアの条件は2つあると考えています。
1つ目は「問いを持てる人」です。問いを持っていない人は、どうしてもやらされ仕事になってしまいます。「Why」がない時に自分で思考をまわせるエンジニアは、価値が高いと思います。例えば、新しいAIが出てきた時にまず試してみることは大切ですよね。しかし、それ以上に「なんでこれを試しているのか?」といった目的思考で動ける人は、より価値の高いアウトプットを出せる可能性が高いと考えています。
2つ目は「コミュニケーション能力」です。AIの発展により、コーディングなどの技術スキルは今後ますます代替されてしまうでしょう。そのため、エンジニアとしての専門性の価値が低くなってしまうはずです。そのため、AIにはできないマネジメントなどのコミュニケーション能力に、より価値が出てくると考えています。いわゆるPdMやPMなどのスキルが重要になってくるはずです。
フリーランス活用:垣根のない柔軟な働き方
弊社では、フリーランス人材も積極的に活用しています。フリーランスの方々と繋がる方法は、2パターンあります。1つ目はリファラルで、いまのところは私の知り合いが多いです。2つ目はエージェント経由で、比較的ハイレベルなエンジニアにお願いしています。一緒に働いてみて、相性が良さそうであれば正社員への転換も検討させていただいています。また、正社員と業務委託の垣根をなくすために、「フレキシブル」という制度も作りました。組織横断に動けるフリーランスの方を対象に、Slackの全チャンネルへの参加をはじめとした社内情報の共有を行っています。もちろんオンサイトで集まるイベントなどにも気軽に参加していただいています。短期間のスポットで入っていただいている方もいますが、弊社としてはより長くご一緒できる方を増やしていきたいと考えています。
Initial Engineで働きたい方へ
技術と経営の視点を融合したDX支援を提供
弊社は、「必要とされる場所に、私たちの知恵と経験を。」をミッションに掲げ、企業のDXを支援しています。サービスとしては、「DXコンサルティング」「CTOアドバイザリー」「CIO補佐官」の3つです。
DXコンサルティングでは、上流から入らせていただき、お客様のご要望をお聞きしてDXの実現を支援しています。データの活用法やAIの活用法についてアドバイスをさせていただくことも多くあります。「何をするか」ももちろん重要ですが、「誰とするか」がより重要なビジネスですね。
CTOアドバイザリーは、CTOがいない、または存在するがうまく機能していない企業に対して、外部CTOとして支援をするサービスです。技術に関わることだけでなく、組織づくりや経営など、CTOに求められる知見を提供しています。
CIO補佐官では、中小企業以上のCIOをサポートするサービスです。CIOの業務領域にCTOの知見を掛け合わせ、企業のIT戦略とDX推進を支援しています。
これらのサービスを提供する上での弊社の強みは、CTO経験者が複数名在籍している点です。技術と経営を掛け合わせて考えられるので、課題に対する解をスピーディーに出せるんです。口だけで終わるコンサルではなく、現場まで踏み込んで課題解決にあたる点も特徴です。実際に開発も担うので、運用を見据えた開発を一気通貫で提供できます。
働くメリット:フルスタック開発とAI活用
私たちの会社で働くメリットは、大きく分けて2つのスキルが伸ばせることです。
1つ目は、フルスタック開発ができることです。様々なお客様のプロジェクトに入ることができるので、多種多様なプロダクトの技術選定やDevOps設計などに関われます。
2つ目は、AIとデータ関連のスキルを伸ばせることです。自社サービスとして、データ基盤やデータ設計のプロダクトを構想中で、その立ち上げ(0→1)にも関われます。
また、AIツールを自由に使える点やフルリモートで働ける点もメンバーに喜ばれています。
自律的に動けるプロフェッショナルな組織
弊社のエンジニア組織は、DevOps部門とAIデータソリューション部門の2つに分かれています。
DevOps部門では、DevOpsエンジニア(インフラ、アーキテクチャ)が4名います。開発はオフショアや開発会社に依頼することが多く、パートナー企業が3社ほどあります。
AIデータソリューション部門では、AIのイネーブルメントとAIソリューション開発の提供を行っています。ここに関しては、私が責任をもって実際に一番手を動かしながら推進しています。
組織の特徴としては、主体性を持って動ける人が多いです。マネジメントはもちろんするんですが、マイクロマネジメントや育成に力を入れなくても組織が回る状況です。30代以上が多いこともあり、各メンバーがプロ意識を持って自律的に働いてくれています。
求める人材:問いを持ち、AIを自然に使って課題解決できる人
一緒に働くエンジニアに求めることは、「問いを常に持てているか」「適切なコミュニケーションができるか」「主体的に動けるか」の3点です。AI DD(Driven Development:AI駆動開発)を進めているので、新しい情報にアンテナをはってどんどん課題を見つけては解決できる方はあっていると思います。さまざまな分野でAIを使いこなして、お客様の課題を解決できる人と一緒に働きたいですね。興味をお持ちいただけた方は、ご応募をお待ちしています!
取材を終えて
佐藤さんのお話からは、お客様の課題解決に対する情熱を感じました。大企業でのプロダクト開発からスタートアップでの開発、CTOとしての組織づくりなど、あらゆる環境で経験を積まれてきた佐藤さんだからこそ、様々な課題を持つ企業のDX推進を成功させてこられたのでしょう。AIの発展により急速に進むテクノロジーの領域において、技術と経営の両面からDX支援を行うInitial Engineさん。そんな社会貢献性の高い事業に興味がある方は、ぜひ一度お話を聞いてみてはいかがでしょうか?