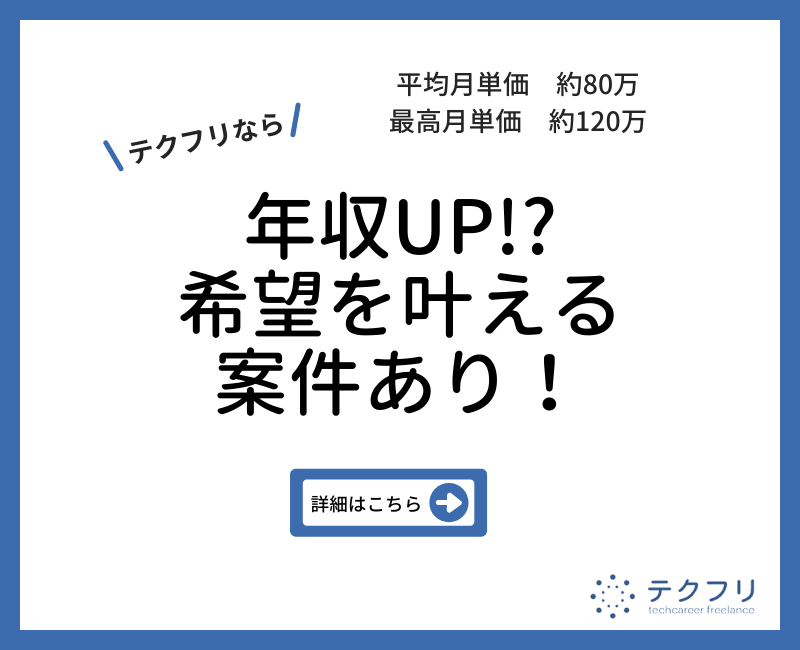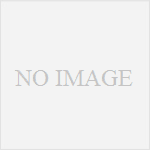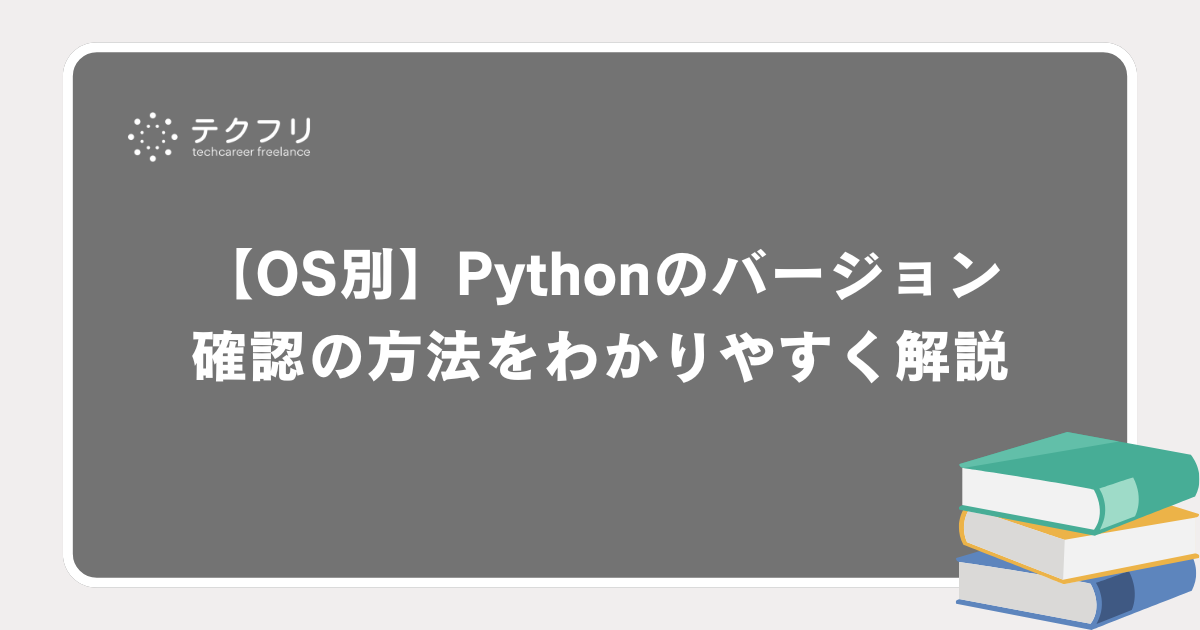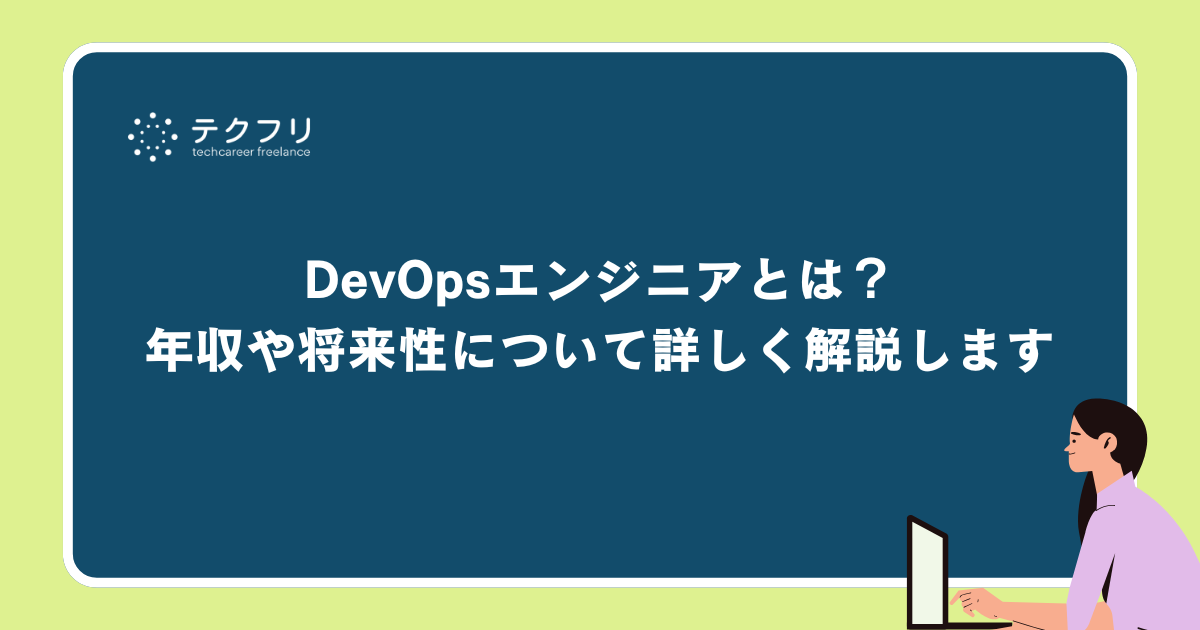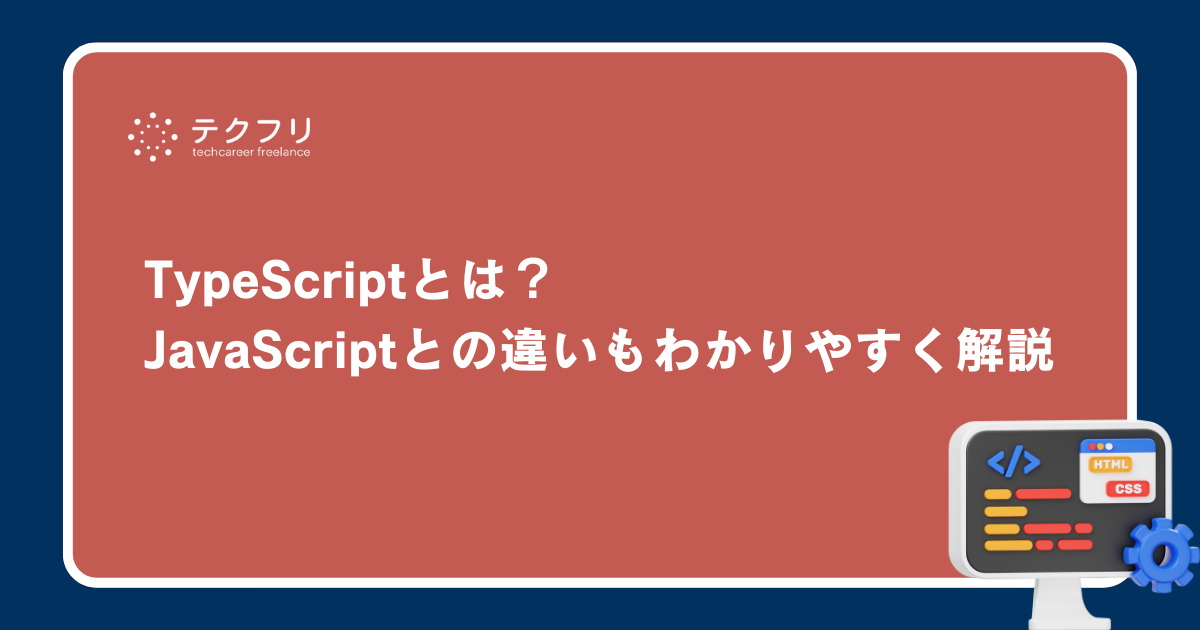今回は、株式会社PKSHA Associatesで執行役員CTO兼CPOを務める、砂塚 紀彦さんのインタビューをお届けします。大学時代、「お客様に価値を届けるための手段」として独学でプログラミングを始めた砂塚さん。新卒での企業勤務を経て、自ら会社を創業し、サービスを立ち上げました。そのサービスでの経験を糧に、株式会社PKSHA Associatesへと活躍の場を移しました。現在は執行役員CTO兼CPOとして活躍されています。今回のインタビューでは、そんな砂塚さんが考える「プロダクトエンジニア」の重要性について、さまざまな角度からお話を伺いました。
インタビュー概要
会社名 :株式会社PKSHA Associates
設立 :2015年3月
資本金 :非公開
代表者 :水野 博隆
所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 宮益坂ビルディング 205
ミッション :ふつうを最高にする。
最高を、ふつうにする。
事業内容 :ソフトウェアの企画・開発・販売、経営およびITに関するコンサルティング
URL :https://asc.pkshatech.com/
お話を伺ったご担当者さま
部署 / 役職 :執行役員CTO兼CPO
氏名 :砂塚 紀彦
新卒で株式会社ワークスアプリケーションズに入社し、不動産管理・購買管理システムの開発に約3年半従事。
その後、BPO領域でスタートアップを創業し、定型業務の自動化技術の開発に取り組む。
2019年よりPKSHA Associatesに参画。現在は執行役員CTO兼CPOとして開発チームを牽引中。
また、過去には趣味として複数のWebサービスの企画・開発・運営も行い、事業売却を経験したサービスもある。
キャリアについて
エンジニアになるきっかけは一つの好奇心
私はもともと早稲田大学政治経済学部に所属していて、小さい頃からプログラミングに触れていたわけでも、エンジニアになるという明確な夢を持っていたわけでもありませんでした。ただ、大学生活を送る中で「世の中にこんなWebサービスがあればいいな」というアイデアがいくつか浮かんでいました。でも、なかなかそのサービスが現れてこない。そんなモヤモヤした気持ちを抱えていた時、ふと「自分で作っちゃえば良いんだ」と思い立って、まずは一冊の本を手に取ったんです。
それがPHPとMySQLを使った掲示板作成の入門書でした。その本を読んだとき、「データを登録・表示・編集・削除できるということは、大体のWebサービスは作れるな」と直感して、本格的に自分でWebサービス作りに取り組み始めたんです。当時はわからないことを全てGoogleで検索するのを何千回も繰り返しながら、体系的な知識はないなりに、まずは動くサービスを作ることに必死でしたね。
インターンと新卒で入社のワークスアプリケーションズ時代
ワークスアプリケーションズの3週間の問題解決能力発掘インターンに参加して、システムの企画から開発まで一貫して行う貴重な経験を得ました。そのままワークスアプリケーションズに入社を決めたのは、インターンでの体験に加えて、当時掲げられていた「20代で圧倒的成長」という理念への共感、そして今も私の芯にある「お客様ファースト」の姿勢に魅力を感じたからです。
また同社に最も驚いたのは、技術をもつ人をエンジニアとして雇うのではなく、お客様のことを考えたシステムを企画できる人にプログラミングを学習させるという方針でした。プログラミングをあくまでも手段として捉えているこの思想は、私がプログラミングを学び始めたきっかけと似ていて、深い親近感を覚えましたね。
入社後は不動産管理システムや購買管理システムの開発プロジェクトを担当して、お客様へのヒアリングからシステム企画・開発・テスト・運用まで、担当機能をフルサイクルで任されました。下流工程だけでなく、開発工程全体を把握できたのは、ワークスアプリケーションズならではの貴重な経験でしたね。
外部から企業を効率化する難しさを知った創業経験
その後、同僚とともにBPO領域でスタートアップを創業することになります。「働く人が輝ける世の中を作りたい」という信念のもと、後回しにしがちな雑務を外注して依頼者が本来やるべき仕事に集中できるサービスを構築したんです。
ただし、このサービスを進める中で「外注すること自体が意外と難しい」という壁にぶつかります。セキュリティの面や金銭面、社内システム面など多岐にわたるポイントで、「意外と気軽に外注ができない」とわかって、DXの本当の難しさを実感したんです。
この経験を通じて、外注ではなく企業の内部からDXを進める必要があることに気づきました。
ただ、創業経験は私にとって非常に貴重なものでしたね。個人開発でも経験してきましたが、サービスの企画からデザイン、開発、運用、さらにはマーケティングやユーザー同士のトラブル対応まで、事業の全体像を俯瞰できるようになったんです。「価値を届けること」をゴールとして、全体での立ち位置を把握できたことで、何を今すべきかという観点で行動できるようになったことは、とても力になったと感じます。
社内からのDX推進へ – PKSHA Associatesでの成長
社外からのDXの難しさを痛感して、事業拡大に行き詰まった結果、会社をたたむ決断をしました。その後、社内からDXを進めていくというミッションに深く共感し、現職の株式会社PKSHA Associates(当時は株式会社アシリレラという社名で、PKSHA TechnologyによるM&A後の2023年に社名変更)への入社を決めました。
当時は社長含め社員数6人の中でエンジニアも2人しかいなくて、まずは何でもやるエンジニアとしてスタートしたんです。市場調査からユーザーインタビュー、開発・運用・問い合わせ対応まで、文字通り何でも担当していました。
入社から1年が経った頃、採用で人数も拡大し、大規模プロジェクトのマネジメントを任されて、EM兼プロジェクトマネージャーに。さらに2年後には執行役員CTO兼CPOに就任することになります。組織の成長とともに、自然と業務上の役割も広がっていき、それに連動して役職も上がっていった形ですね。業務範囲が広がることに抵抗は全くありませんでした。「どんな仕事もより良いプロダクトを作るために必要なこと」という認識だったので、様々なチャレンジを積極的に受け入れています。現在も開発組織のマネジメント、新規事業の立ち上げ、採用、グループ企業横断プロジェクトなど多岐にわたる業務を担当しています。
弊社の特徴として、プロダクトを開発するエンジニアを「プロダクトエンジニア」と呼んでいるんです。いわゆるソフトウェアを作るというミッションじゃなくて、プロダクトとしてお客様に価値提供することにコミットするエンジニアという形で採用しています。プロダクトエンジニアの開発フローは、通常のソフトウェア開発とは違い、社内外にインタビューしながら自分で企画を作成する。そしてα版みたいなプロトタイプを作って、お客様の反応を見て、それを踏まえてβ版を作って、またお客様の反応を見てリリースする。各プロダクトが本当にお客様に使われ、価値を届けられているかを確認しながら、開発・リリースを進めています。
業務自動化の全国普及と未来への展望
株式会社PKSHA Associatesの製品は2500社に業務自動化ソフトを提供していますが、これを今後は日本中の隅々まで広げたいんです。しかも一部の人だけでなく、全社員が当たり前に使える状況を作りたい。
元々RPAでの定型作業自動化から始まって、今はAIを搭載してより幅広い業務を自動化できるようになりました。さらに重要なのは、誰でも使いこなせるようにすることです。最近「AI OJT」と呼んでいるんですが、人にOJTする感覚でAIに仕事を教えることができる。特別なスキルがなくても、AIに仕事を教える体験を通じて業務自動化が使えるようになるんです。弊社の「ふつうを最高にする」という理念のもと、「そんな業務まで自動化できるの?」という驚きを全国の働く人々に届けたいと思っています。
プライベートとしては小さい頃からの夢で、ドラえもんのひみつ道具を作ってみたいですね。最近のAI技術の進化で「これできるじゃん」という気持ちになってきました。
今は仕事の生産性向上に注力していますが、それが効率化された後は、人生の豊かさや楽しみを求める時代が来ると思うんです。その時に、エンタメかもしれないし、コミュニケーションツールかもしれないし、夢があるものを作りたいですね。
暮らしの豊かさに寄与するようなドラえもんのひみつ道具を作っていきたいです。
考え方・マインドについて
機能の数より、使われることが重要
やっぱり「自分は実装しました」じゃなくて、「お客様に価値を届けて喜んでもらえました」にコミットすることが大事だと思っています。
機能が100個あっても、そもそも認知されていなかったり、使いづらくて十分使われていないというのは経験上すごく目にしてきました。逆に機能は30しかないんだけど、便利でちゃんと使われていて、ユーザーが喜んでくれているという方が、むしろ価値を届けられると思うんです。
弊社製品のターゲットはエンジニアじゃなくて、業務部門の現場の人たちです。そういう人たちがRPAを使おうとしたときに、どれだけ機能が存在していても、結局使われておらず価値が届けられないということがすごくあると思っています。だからこそ、機能の多さではなく、実際に使われる体験を重視することが重要だと考えています。
プロダクトエンジニアの5つの行動指針
弊社では価値提供できるプロダクトをつくっていくうえで、プロダクトエンジニアとして大切にすべき5つの行動指針を定めています。
1. Passion
ユーザーや業務課題に関心を持ち、より良いモノを作って届けることにこだわる。個人開発をやっている人を採用しがちなんですが、個人開発は自分の意思で物を作っているので、このようなパッションってすごく大事だと思っています。パッションがないと、異常なレベルで物事を深掘りしようと思わないし、やらされている感覚の仕事になってしまいますから。
2. User First
技術は手段であり、常にユーザーに価値を届けることを最優先にする。コードの綺麗さや機能の高性能化にだけエネルギーが向いていて、使われない機能になっちゃってもしょうがないですから。
3. Deep Dive
業界・業務・ユーザーのことを深く理解し、本質的な解決策を提案する。本当にユーザーがやっている業務の理解も含めて、ちゃんとユーザーにインタビューをして、どういう課題を抱えているのか、それを解決するためには何をしなきゃいけないのかを深く理解することです。
4. Feedback Driven
社内外の声や反応などを取り入れながらプロダクトを磨き上げていく。自分が作ったものが本当にその課題解決をできているのかを、α版・β版で実際に触ってもらって検証するフィードバックサイクルを回しながら、ちゃんと使われるものを作り出していく。
5. Borderless
技術だけでなく、ビジネス・デザインなど全体最適の目線でプロダクトの価値最大化を目指す。最終的に価値を届けるためには、デザイナー、営業、テクニカルサポートや販売パートナーなどと連携しなければならない。そういう広い視点を持って、ボーダレスに関わっていって、最終的に価値を届けるというところから逆算して、ちゃんとチーム連携を図っていくことが大事だと思っています。
詳しくはこちらもご覧ください。
Product Engineerとは?ユーザーへの価値到達にコミットするPKSHA Associatesのエンジニア

AI時代に求められるスキルと3つのフェーズ
今はまさにAI時代で、あらゆる企業が採用時にAIスキルを重視するようになってきています。AIを使うか使わないかで、数十倍から100倍の生産性の差が生まれる時代になっているので、AIへの意識はクリティカルな要素だと思っています。コードを書くのにAIを使っているエンジニアも増えてきていますし、もう「使わない」という選択肢はほぼあり得ないレベルになっています。
その中でエンジニアに必要なことは下記3つのフェーズを理解して、一つ一つ積み上げていくことだと思っています。
フェーズ1:個人の効率化
まずはAIを使いこなして、自分の仕事をいかに自動化・高品質化していけるかを追求すること。
フェーズ2:組織へのレバレッジ
自分の仕事が楽になりました、だけでは不十分で、それを組織に浸透させていくことが重要。例えば企画書作成のAIツールを作ったら、プロダクトエンジニア全員がそれを使えるようにする。自分だけに閉じずに、組織全体にレバレッジを効かせていくのが大事です。
フェーズ3:事業化の可能性
組織での効率化がうまくいけば、「それって世の中に出せばいいじゃん」という話になってくる。ただ、これは事業方針との兼ね合いもあるので、まずはフェーズ1・2を個人と組織レベルでしっかり実践することが、エンジニアにとって現実的で重要だと思います。
開発領域だけでなく、ビジネス領域の効率化も含めて、これだけで何十馬力ものパワーを持つエンジニアになれるポテンシャルがあるんです。
AI時代のフリーランス積極採用
現在、弊社では7名のフリーランスの方に参画いただいています。フリーランス採用については、業界でも「内製化すべきか、フリーランスを増やすべきか」という議論が話題になることがあります。
私たちは積極的にフリーランスの方を採用する派です。その理由は、AIを活用することで1人が何十馬力も出せる時代になっているとき、スキルを持つ人が参画すると当然大きな差がつきます。AIをバリバリ活用できる人には、どんどん参画いただきたいというのが私の考えです。実際、弊社では自社で補いきれない専門スキルを持つ方に参加していただくケースと新規事業のスピードを上げるためにメンバーを集める必要があるケースの2種類で採用しています。比較的高いスキルの方に、できれば長く関わってもらいたいという想いで参画いただいています。
新規プロジェクト立ち上げは会社固有の事前知識として求められる量が減るので、フリーランスの方でも関わりやすい領域です。フリーランスの方は色々な案件を経験されているので、新しいプロジェクトを一定のモダンなアーキテクチャで立ち上げるといったことを素早く行うのが得意な方が多いと感じています。
株式会社PKSHA Associatesで働きたい方へ
現場ユーザーが7割を占める業務自動化ソフト
私たちが開発している「ロボオペレータ」は、いわゆるRPAと呼ばれる業務自動化ソフトウェアです。最大の特徴は、現場ユーザーの方が7割を占めていることです。経理、人事、総務といった業務部門の方々が、「この面倒くさい仕事を何とか自動化したい」と思ったときに、その業務を行っている本人が自分でロボオペレータを使いこなして業務自動化を実現しています。現在2,500社、7,000台のPCで稼働している実績があります。ほとんどの会社では手元のExcelファイル、VBAで作られた社内システムなど、様々な環境が混在しているため、業務自動化を実現するためには、パソコン操作と同じレイヤーで支援する必要があり、クラウド型ではなくWindowsでのパソコン定型業務なら大体自動化できるというのが私たちの強みです。
私たちは、一番業務を理解している本人が自分で使いこなし、自分で自動化することが重要だと考えています。現場の方が使うためにUXが重要であることから、私自身もこれまでUXリサーチに500時間以上を費やしています。実際にユーザーにロボオペレータを触ってもらい、どこでつまずくかを観察・インタビューし、つまずきポイントを徹底的に洗い出します。それらを全て改善し、再度UXリサーチを行うというサイクルを何百時間も繰り返すことで、現場の人が自分で使えるレベルまで使いやすさを追求しています。
PKSHAのメリット:AI時代のプロダクトエンジニアとして
当社に入社するエンジニアの多くは、それまで受託開発に従事しプロダクトにこだわりを持って開発できなかった経験から、、「今度は思いを持って開発したい」という想いを抱いていらっしゃいます。そういう方にとって、自分が作ったものを2,500社に届けて喜んでもらえるという体験は、最大の醍醐味だと思います。しかも、UXリサーチを通じて実際にお客様にインタビューしたり、自分が作ったものを触ってもらって感想を見たりと、より近いところでプロダクト開発を行い、「自分が作ってやったぞ」という達成感を直接受けられるのです。
また、PKSHAグループ全体には様々なスペシャリストが在籍しており、エンジニアとして多くのことを学べる環境があります。
特にアルゴリズムエンジニアという職種があり、自然言語処理、画像認識、音声認識などの専門分野の経験を持つスペシャリストが多数在籍しています。彼らとは実際のプロダクト開発で一緒にチームを組むこともあり、自分が知らない技術を使った開発を通じて多くを学べます。また、グループ全体で勉強会が頻繁に開催され、論文段階の最先端技術情報もシェアされるため、技術トレンドをいち早く把握できることも大きなメリットです。
AI時代に求められるプロダクトエンジニアマインド
プロダクトエンジニアとして最も大事なのは、「自分は実装しました」という自己完結の思いではなく、「お客様に価値を届けて喜んでもらえました」という思い、すなわち価値提供をゴールにすることです。
AI時代においては、この視点がさらに重要になってきています。コードを書く作業が5倍速、将来的には100倍速になったとき、コードを書くという仕事は少なくなり、今まで5人のエンジニアが必要だった作業を1人でできるようになるかもしれません。そうなったとき、コードを書くのが自動化されても、お客様に価値を届ける仕事はまだまだたくさんあります。その目線を持っている人は、コードを書くのが楽になったら「もっと自分がここで活躍した方がお客様に価値を届けられる」というところに自然とシフトしていけます。一方で、「自分は綺麗なコードを書く人間です」と定義してしまった瞬間に、キャリアが広がらなくなってしまったり、そのキャリアから抜け出すのに時間がかかったりします。プロダクトエンジニアというポジション取りは、AI時代においてプロダクトエンジニアの仕事の7割が自動化されても「むしろ歓迎すべきことだ」と言える強さがあり、キャリア的にも有利だと思います。
AI活用はあくまで手段の一つです。そういう思いを持った人がAIを使うと非常にパワフルですが、思いがなく、やらされ仕事を効率化するだけでは限界があります。長い目で見ると、思いを持った人が素晴らしい武器を手にしたのがAI時代だと思います。だからこそ、思いを持つことが何より大事なのです。
最後に、AI活用は絶対に必要なスキルです。使うか使わないかで数十倍から100倍の生産性の差が生まれる時代になっています。人とAIの共同作業という新しい働き方を生み出し、以前とは比べ物にならないくらい活躍する人が誕生しはじめています。私たちと一緒にワクワクする未来の働き方を生み出し、全国に価値を届けていく仕事をしませんか。もしAI時代のプロダクトエンジニアに興味をお持ちいただけましたら、気軽にX(@sunazukan)でお声がけいただければと思います。

取材を終えて
今回のインタビューを通じて、砂塚さんの「技術は手段、価値提供がゴール」という一貫した信念に深く感銘を受けました。大学時代の「自分で作っちゃえば良いんだ」という発想から現在まで、常にお客様目線を忘れない姿勢が印象的でした。特に「プロダクトエンジニア」という概念は、AI時代にも通ずるエンジニア像を示しており、多くの技術者にとって示唆に富む内容だったと思います。創業での挫折を糧に現在のミッションへつなげた経験や、個人開発を通じて事業全体の視点を獲得した話は、エンジニアのキャリア形成において非常に参考になるでしょう。「思いを持つことの重要性」についての言葉は、技術が急速に進歩する中で人間としての価値をどこに見出すかという根本的な問いへの明確な答えでした。技術で世界をより良くしたいという思いを持つすべての方に、ぜひ届いてほしいインタビューです。