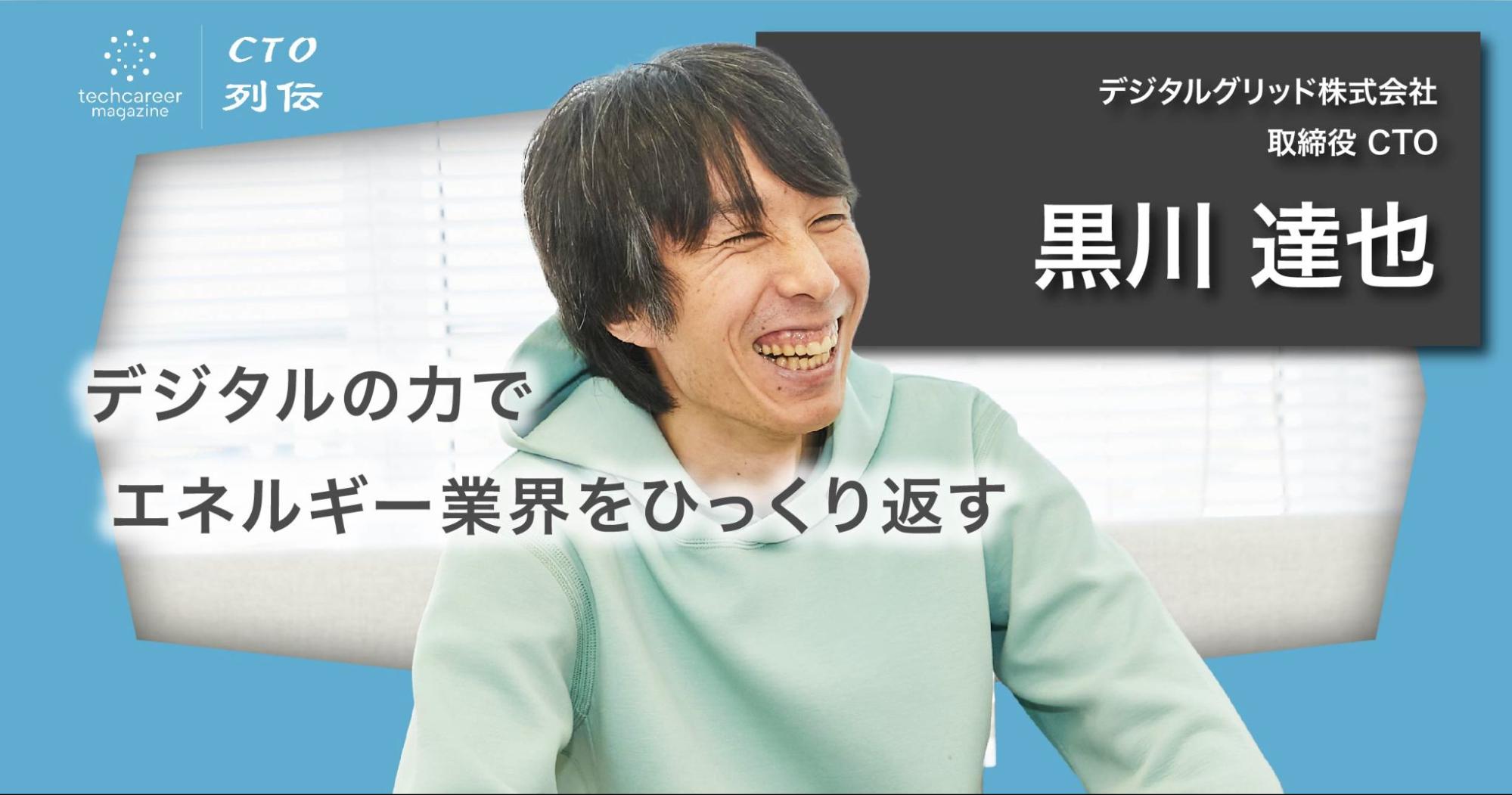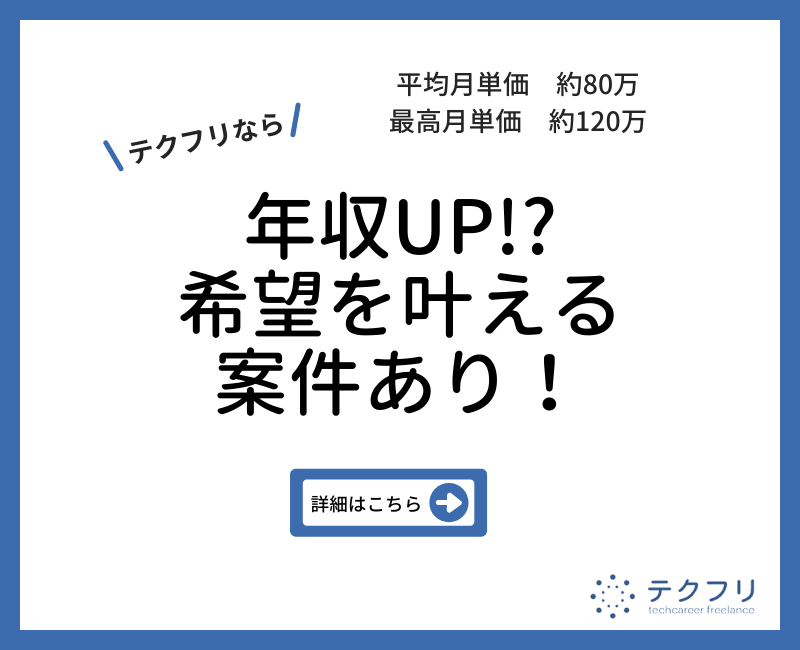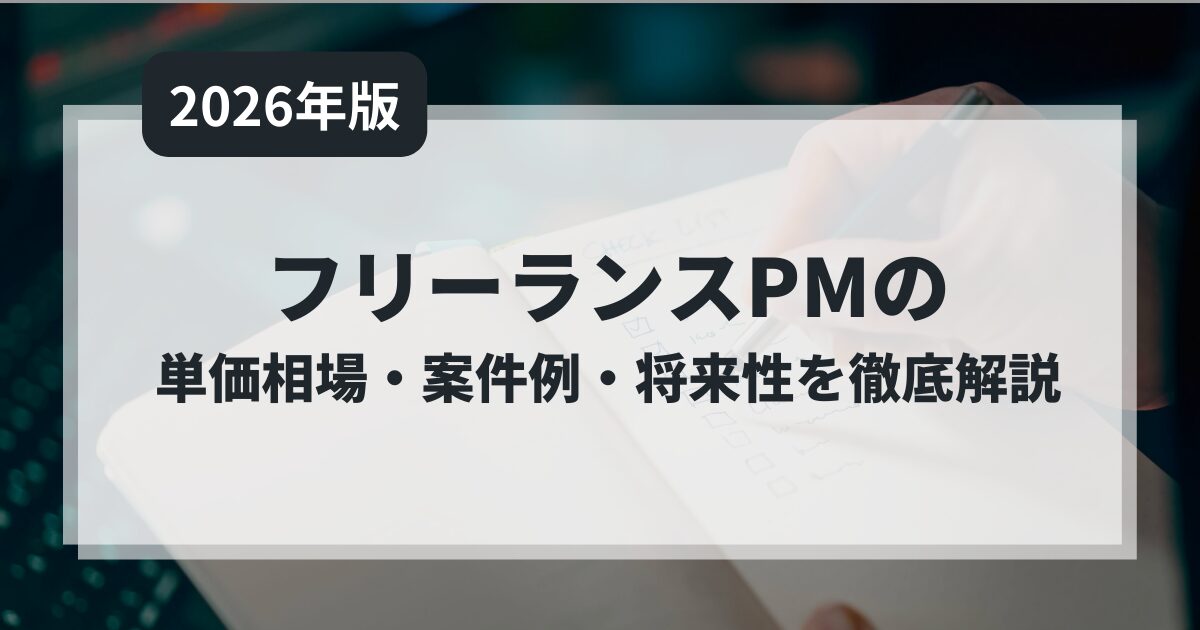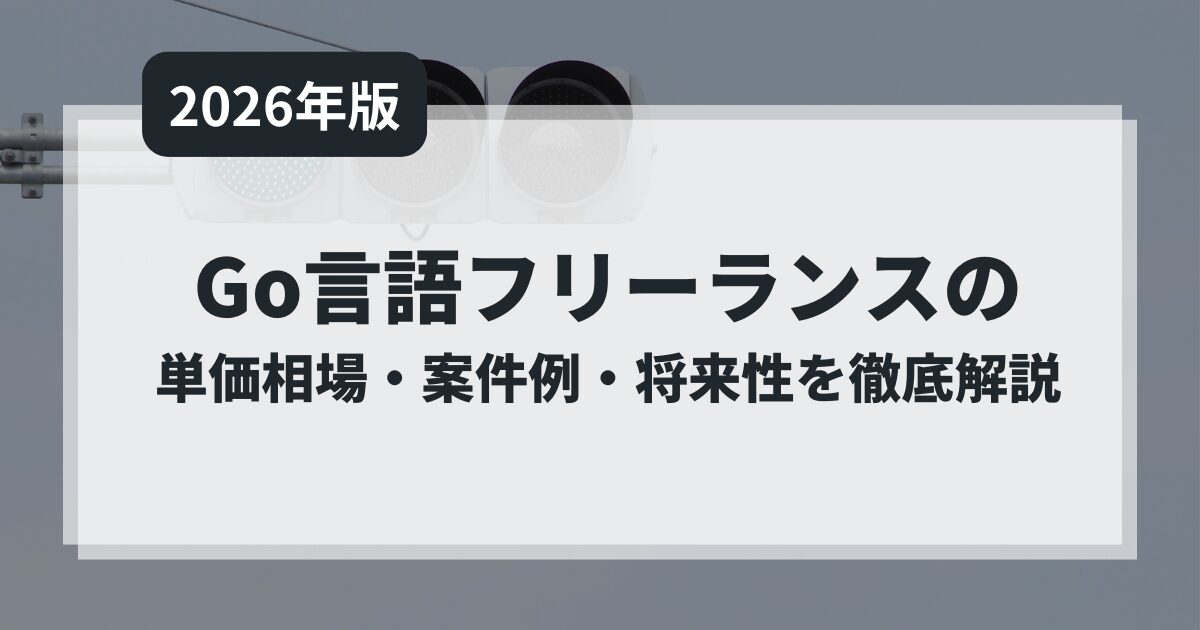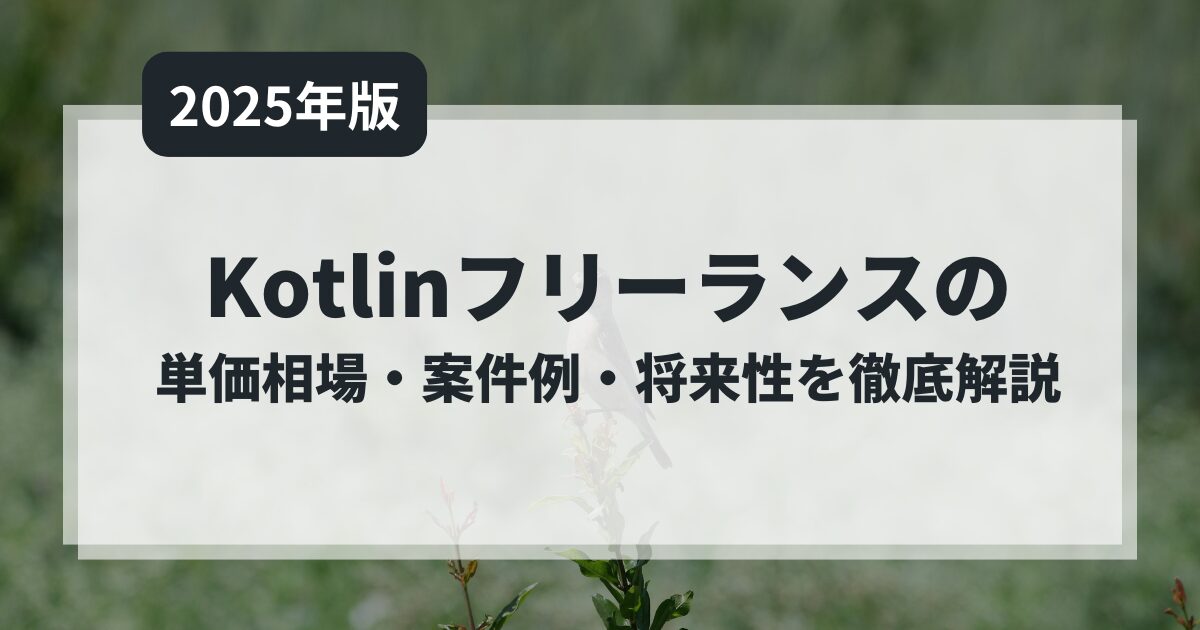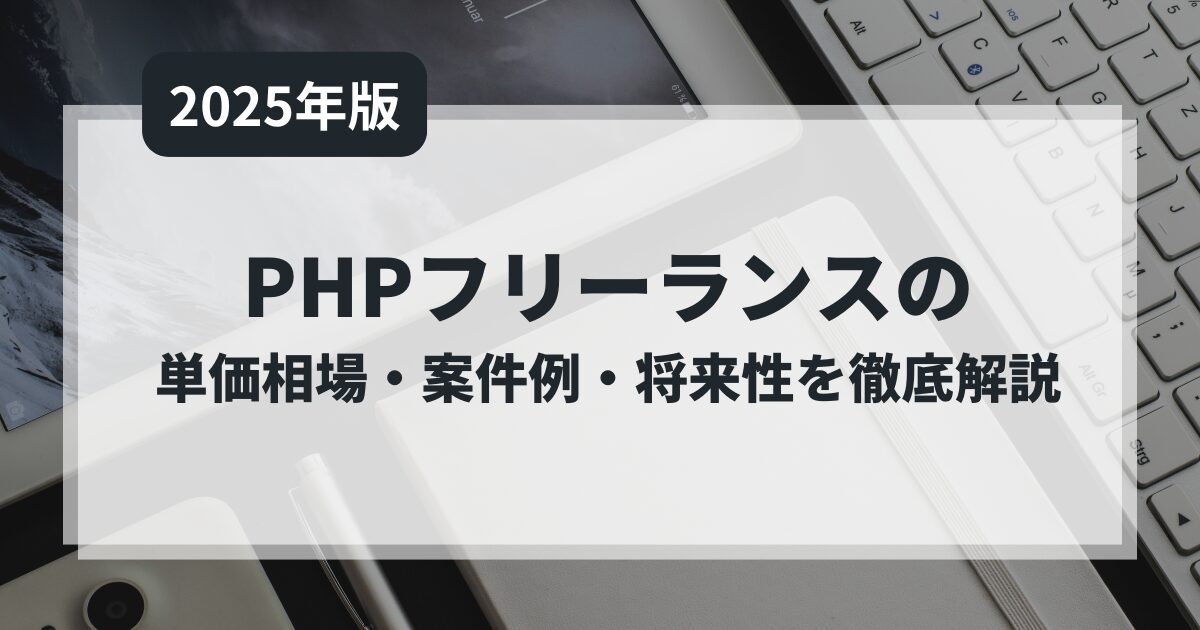今回は、デジタルグリッド株式会社で取締役CTOを務める黒川 達也さんのインタビュー記事をお届けします。DeNA、PKSHA Technologyといった先進的な企業でエンジニアとしての技術を磨かれた黒川さん。現在は、エネルギー領域で事業を展開するデジタルグリッドでCTOを努められています。そんな黒川さんが目指すのは、「エネルギー業界をひっくり返すこと」。大きな野望を持って業界の変革に取り組む黒川さんの、キャリアと価値観に迫ります。
インタビュー概要
お話を伺った企業さま
会社名 :デジタルグリッド株式会社
設立 :2017年10月
資本金 :2,643,690,316円
代表者 :豊田 祐介
所在地 :東京都港区
ミッション:エネルギーの民主化を実現する
事業内容 :電力及び環境価値取引プラットフォームの開発・運営
URL :https://www.digitalgrid.com/
お話を伺ったご担当者さま
部署 / 役職:取締役 CTO
氏名 :黒川 達也
2015年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了(技術経営戦略学)。
株式会社ディー・エヌ・エーに入社、スマートフォンゲームの開発、ウェブメディアの開発に従事。
2017年株式会社 PKSHA Technology に入社、対話エンジンを用いた自動応答システムの開発に従事
2020年8月よりデジタルグリッド株式会社に入社、デジタルグリッドプラットフォームの開発に従事。
2023年10月30日に取締役に就任。
キャリアについて
Web2.0の時代に友人と趣味でWebアプリを開発
エンジニアとしての原体験は、中学・高校生時代に遡ります。HTMLで掲示板を作ったり、友人とプログラミングをして遊んだりしていました。通っていた高校がスーパーサイエンスハイスクールに指定されていたこともあり、学校活動の一環として数学の研究でプログラミングをする機会も少しありました。しかしその頃は、「エンジニアになりたい」という思いは特になかったです。
本格的にエンジニアを目指し始めたのは、就職を考え始めたタイミングでした。東京大学のシステム創成学科に進学したのですが、どちらかというと外資系企業やコンサルに就職する人が多く、情報系に特化しているような学科ではありません。しかし、当時はWeb2.0まっただ中の時代だったこともあり、友人と興味本位で国会の議事録をクローリングして対話形式で可視化するWebアプリを作ってみました。すると、案外このWebアプリ開発がおもしろかったんです。この経験でエンジニアに興味を持ち始め、リクルートやDeNAで簡単なWebアプリやゲーム開発のインターンに参加し、最終的にはDeNAにエンジニアとして入社することにしました。
DeNA・PKSHA Technologyで高レベルのエンジニアリングを経験
DeNAでは最初、Webメディアの立ち上げを行いました。学生時代にもWebアプリ開発の経験があったので、その延長線上のスクラム開発ではあったのですが、DeNAの開発は規模感が全く異なります。ライターやデザイナーともコミュニケーションを取りながら開発を進める必要性があり、大規模プロジェクトの進め方を学ぶことができました。その後は、ガンダムやファイナルファンタジーなど、既存ゲームの機能開発を担当。ゲーム開発はWebアプリ開発と違って、イベントなど期日を絶対にずらせない開発が発生するという特性があります。イベントまでにコーディングやマークアップ、QAも絶対に終わらせないといけないので、とても大変でしたね。また、イベントをリリースした瞬間には膨大なアクセス数が発生します。そのため、この高トラフィックを捌くために、DBの使い方や開発プロセス・コーディングのルールが社内で定められているんです。この仕事ぶりはまさにプロフェッショナルだと感銘を受けましたし、エンジニアとして貴重な経験になりました。
DeNAで約2年働き、PKSHA Technologyに転職しました。大学時代の友人がチャットボットサービスを立ち上げるとのことで、誘われたのがきっかけです。私は主に、バックエンド開発を担当。当時はLINEベースのシステムだったのですが、外部の情報を取り入れながらWeb上でも機能するように実装しました。機械学習などの最新技術を用いながら開発を行い、こちらもエンジニアとして良い経験になりました。
30代での新たな挑戦:デジタルグリッドのCTOに就任
実は、PKSHA Technology時代から、デジタルグリッド代表の豊田とは交流がありました。豊田とは、共通の知人の紹介で知り合ったんです。「電気のドメインで新しく事業を始めたい」とのことで、そのシステム開発の相談に乗っていました。当時の開発業務はSIerに外注していたのですが、テクニカルなレビューやコンポーネントの作成を1〜2年ほど手伝いました。そんな中、私に転機が訪れます。子どもができ、改めてこれからの30代に何をするかを考え直したんです。豊田からかねてより誘いを受けていたこともあって、「エネルギー業界をひっくり返すのもおもしろい」と思い、デジタルグリッドのCTOとしてジョインすることに決めました。
入社当初は社内でがっつりエンジニアリングをやっていたメンバーがいなかったので、「デジタルグリッドをテックカンパニーにしてやる」という気概で業務に当たりました。ほとんど外注していたので、まず取り組んだことは、開発の内製化です。しかし、エネルギー業界の特性上、新しい機能を追加する際に膨大な時間とお金が発生してしまいます。電気の消費量を予測して、国の機関に報告し、取引を作って生産するといったフローを踏まなければなりません。また、コンポーネントの数が多かったこともあって、完全な内製化を実現するのに2〜3年近くかかりました。現在は、アジャイル開発にて、新しい機能の実装やリファクタリングに取り組んでおり、私もまだ手を動かしてバックエンドの開発をしています。チームとしては10人もおらず各々が自律的に動けるメンバーなので、手がほとんどかからず助かっています。
エンジニアとしての大きな成長ポイントは、DeNAでのゲーム開発
これまでエンジニアとして様々な経験をしましたが、特に大きく成長できたと思えたのは、DeNAでのゲーム開発に携わっていた時です。新しいものを作るタイミングで、PoCから運用までの全てのフェーズを見据えて実装に取り組む姿勢は、今でもとても役に立っています。ゲームの場合、新機能をオープンしてエラーがでると、金銭的にも大きな機会損失が発生してしまいます。だからこそ、DeNAのクオリティに対するこだわりはすさまじく、いちエンジニアとして大変勉強になりました。
時間をかけてでも、エネルギー業界の変革を成し遂げる
今後の展望としては、現場とプロダクトを行き来したいと考えています。やはり現場のほうが入ってくるエンジニアの知識量は多いですし、何よりやっていて楽しいです。一方で、プロダクトの方向性や技術を駆使してどのように成長させるかを考える人がいないと、事業としてうまくいきません。そのため、エンジニアとしての腕をなまらないよう現場にも関わりながら、プロダクトをどんどん世の中に出していきたいと思っています。そして最終的には、エネルギー業界の変革をやりきりたいです。業界の構造としてどうしても1つ1つの物事を進めるのに時間がかかってしまいます。しかし、だからといって途中で諦めるのではなく、化石燃料の代わりとなる再生エネルギーの使用促進など、何年後になるかはわかりませんが忍耐力を持って改革を成し遂げるつもりです。
考え方・マインドについて
エンジニアリングでユーザーの課題を解決するのが、「本当の価値提供」
私がエンジニアとして大切にしている価値観は、「自分の価値をしっかり発揮できているか」と「エンジンの大きさ」の2つです。前者に関しては、「やり切り力」とも言い換えられます。単にコードを書いて終わりではなく、デプロイ・リリースして、本当にユーザーに使われるのかまでを考えて開発を進めるということです。そのためには、業務プロセス全体の理解が欠かせません。自分がデプロイしたものが誰にどのように使われるのかを把握し、バグがあるかどうかをしっかり確認する。このように最後までやり切って課題解決を達成してこそ、「本当の価値提供」だといえるでしょう。後者に関してわかりやすく言うと、「やりたいことに突き進むパワフルさ」です。スタートアップでは、エンジンが大きい人が何人いて、それをどうビジネスに当ててベクトルを合わせるかが事業成長においてとても重要だと思います。当社でもそのような「強いチーム」を作っていきたいです。
「好奇心」がエンジニアとしての成長の源泉
チーム開発が当たり前の状況では、他のエンジニアとコミュニケーションを取りながら協力して開発ができるスキルはマストと言えるでしょう。その上で、技術的に成長したいという思いを持っている人は強いです。さらにそのような方は、成長したいから成長するというより、技術への好奇心が強い人が多いと感じています。その好奇心が、最終的なエンジニアとしての成長につながっているんです。また、単にハードスキルを身につけるだけではなく、業務に落とし込んで実践し、課題解決までできるエンジニアは強いと思います。
ITフリーランスの活用が、新規・既存事業の成長につながる
現在、ITエンジニアはとても不足しています。そのため当社では、正社員だけでなく、フリーランスにも参画していただいています。フリーランスには、新規・既存プロダクト問わず業務をお任せしている状況です。特に、新規プロダクトの開発では重宝しています。既存プロダクトの開発もあるので、そもそも新規プロダクトにそれほど多くのリソースを割けません。その上、1〜2人で開発しないといけないので、フロントエンド・バックエンド・インフラと幅広い知識を持った人材が不可欠です。また、業界の特性上、専門知識の習熟に半年〜1年ほど要します。そのため、一定のドメイン知識を持つ社員は既存プロダクトチームに置いておきたいという経営的な事情もあったりします。そういった状況では、リソース調整がしやすく、幅広い知識や技術力を持ち合わせたフリーランスの存在は非常に貴重です。実際に、フリーランスに新規プロダクトのモック作成を依頼したこともあります。また、既存プロダクトの開発にも参画していただいており、社員と同じようにチケット管理されたタスク処理をお任せしています。
デジタルグリッドで働きたい方へ
「デジタルグリッド」でエネルギーの民主化を実現する
当社は「エネルギーの民主化を実現する」をミッションに、電力取引プラットフォーム「デジタルグリッド」の開発・運営を行っています。具体的には、電力会社などの電気の売り手と、工場などの買い手のマッチングをプラットフォーム上で実現させています。近年は、再生可能エネルギーなどの普及により、電気を持つ主体が電力会社だけではなくなりました。ただ、再生可能エネルギーは価格が高く、変動リスクもあります。そこでデジタルグリッドでは、電気の需要がある事業者がそれぞれのリスク許容度に合わせて電力調達のメニューを作り、取引をできるサービスを提供しています。仮に電気の売り手を自分たちで探すとなった場合、膨大な手間が発生します。売り手の選定、使用量の決定や国への申請など、取引を成立させるまで煩雑なプロセスを踏まないといけません。しかし、デジタルグリッドを利用すれば、その取引を全てまるっと当社が代行します。電気の売り手を見つけ、契約内容さえ決めてしまえば自動で取引が成立するので、よりスムーズに電力調達が可能になります。
その他、直近では蓄電池事業にも力を入れています。電気の受給はほっておいたら一致するのではなく、調整が必要です。マーケットの指標をもとに調整をするのですが、その際に蓄電池の制御も実施します。発電所が電気を償却するスパンは短いので、扱える電源を増やして、適切に電力を供給できる仕組みの構築に取り組んでいます。
会社として、エンジニアの成長環境に大きく投資
当社のエンジニアチームは、事業ごとに5つのチームにわかれています。横串でソフトウェアエンジニアチームを構築し、その中で各部署へメンバーのアサインを実施。1チーム4名ほどの体制で、技術的な意思決定は各チームが行います。
また、会社としてエンジニアのスキルアップやリソースへ大きく投資しており、各メンバーが主体的に挑戦できる環境が当社の魅力です。特に伸ばせるスキルでいうと、「DevOps」や「システムのパフォーマンス改善」、「ビジネスのモデリング能力」があります。生産性を高めることにはかなり重きを置いており、DevOpsの改善は常に考えています。お客さんも日々増加しており、それに伴ってシステムのパフォーマンス改善もしなければいけません。モデリング能力に関しては、法制度が毎年変わる中で送電線を持っている事業者とどのようにシステム連携を行うかなど、ビジネス的な観点も伸ばすことが可能です。
楽しみながら課題解決ができる人を募集しています!
電気は日常で当たり前にある存在なので、最初からエネルギー自体に興味がある人は珍しいと思います。しかし実際には、再生エネルギーの活用などエネルギー業界にはとても大きな課題があるんです。そのため当社としては、このような難しい課題をわからないながらも楽しみながら一緒に解決していける方に来て欲しいと考えています。当社の事業や働く環境に興味を持っていただけた方は、ぜひエントリーをお待ちしております!
取材を終えて
黒川さんは、常に目的志向で考え、行動されている方なのだとインタビューを通して実感しました。私たちは、日々当たり前のように電気を使っています。しかし、その業界には課題が山積みだと聞いて私も驚きました。人間の生活に不可欠な電気という領域だからこそ、解決できたときのインパクトは計り知れないものがありますし、そういった部分が黒川さんに「本気で変革をやり遂げたい」と思わせるほど熱くさせているのではと、勝手ながら拝察しました。そんな黒川さんであれば、エネルギー業界をひっくり返し、私たちの未来をより明るくしてくれると思わせてくれます。人間生活に深く関わる領域で、大きな挑戦をしてみたいという方は、ぜひデジタルグリッドの門を叩いてみてはいかがでしょうか。