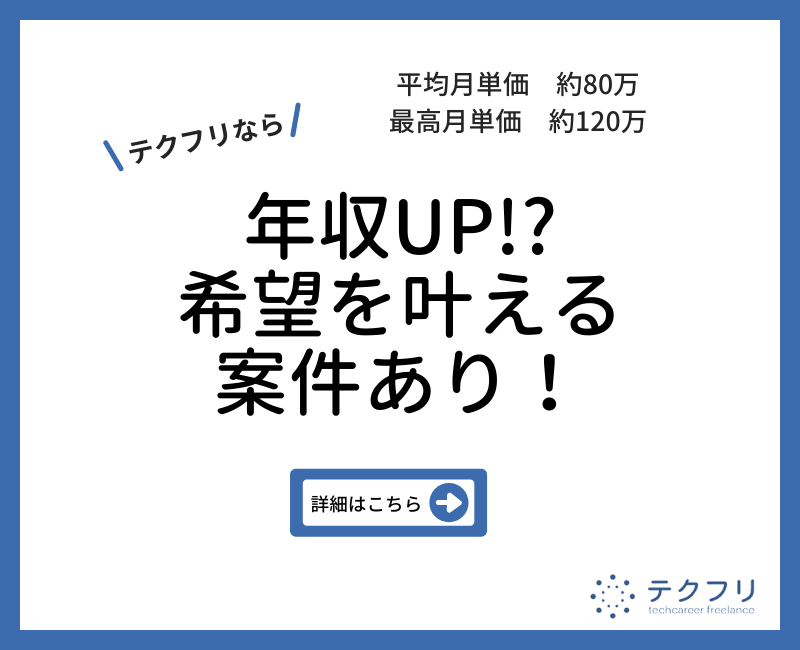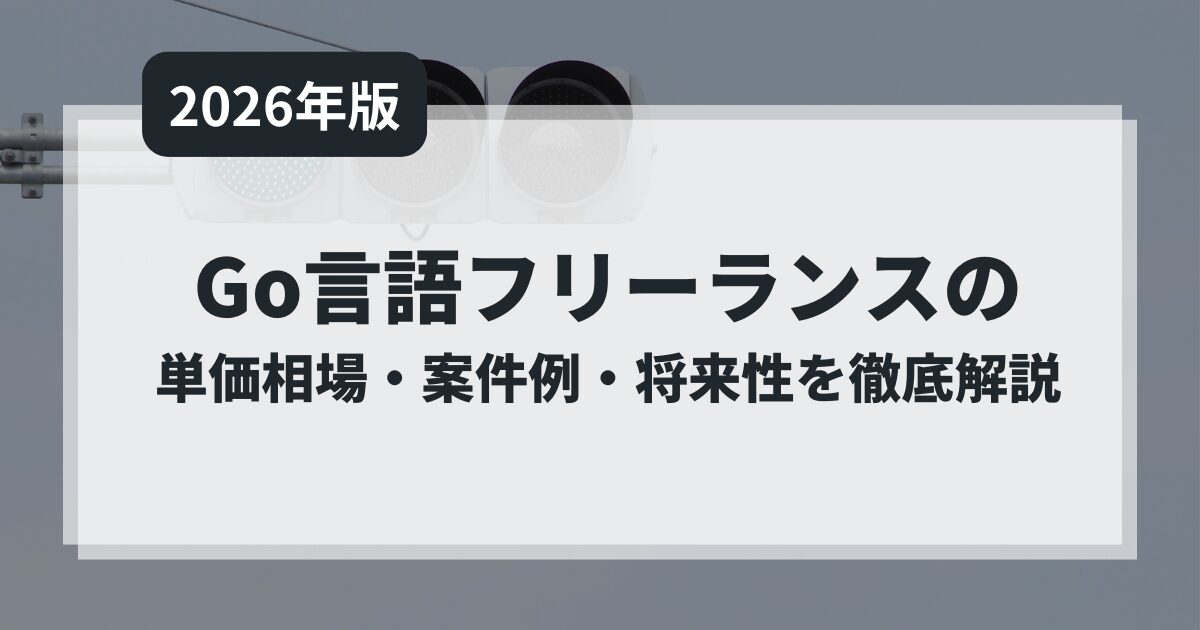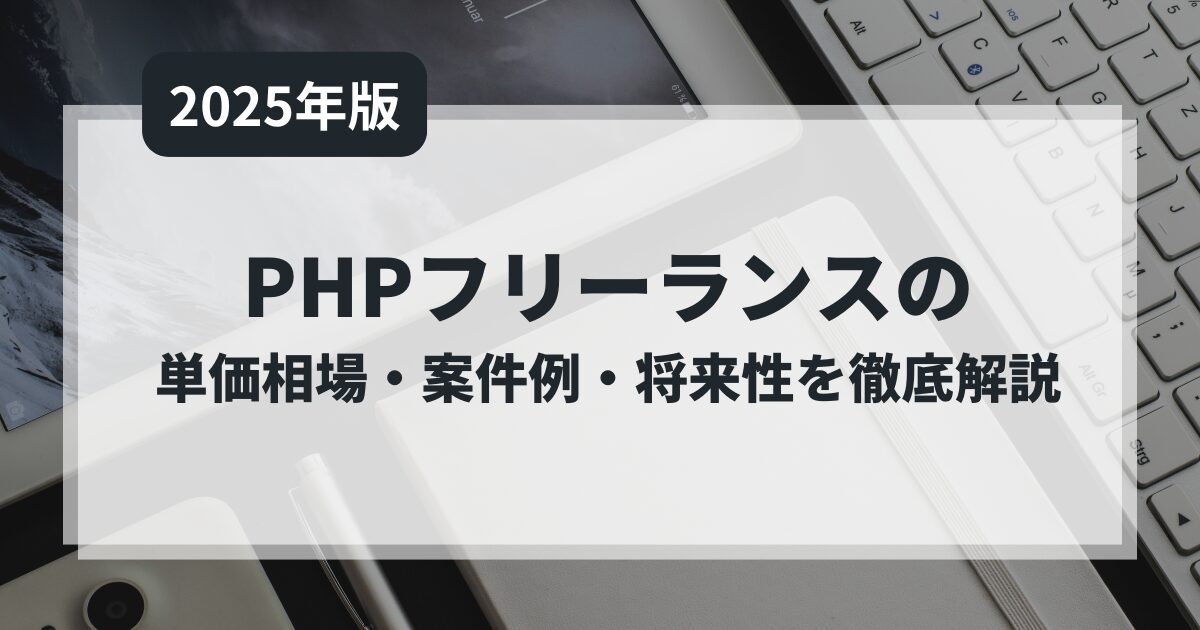定年とはそもそも何? SE(システムエンジニア)の観点から再定義する
システムエンジニア(SE)の定年の考え方は基本的に『プログラマーの定年 一生プログラマーでいられるか?』で書かせていただいた、プログラマーの定年の考え方と同じです。
つまり、定年という考え方はサラリーマンの雇用と結びついた考えであり、65歳になって、サラリーマンとしては定年退職となっても、今まで培ってきたSE(システムエンジニア)としてのスキル・技術が定年退職した翌日から通用しなくなるわけではないので、本人の意思さえあれば、SE(システムエンジニア)として働き続けることは可能です。
▼ SE(システムエンジニア)は定年後もフリーランスとして働ける
実際、定年を迎えてサラリーマン生活を終えたものの、フリーランスになって、現場でバリバリ活躍しているSE(システムエンジニア)を私は何人も知っています。
私はもともとユーザー系システムインテグレーターに新卒で採用され、サラリーマンSE(システムエンジニア)をしていましたが、その当時、パートナー要員として、ベンダー系システムインテグレーターを定年退職後にフリーランスへと転向したおじいちゃんSE(システムエンジニア)がいたことを鮮明に覚えています。
自分はこの方にSE(システムエンジニア)の仕事の基礎を教え込んでもらえたからこそ、今もSE(システムエンジニア)として仕事ができているのだと思っています。
話が脱線しましたが、そのおじいちゃんSE(システムエンジニア)がリタイアしたのは79歳でした。
本人は80歳まで現役SE(システムエンジニア)を続ける気で、クライアントであった当時の自社とも、そのように契約していたのですが、奥様に先立たれて、地方に住む娘夫婦の家でお世話になることになり、契約終了になったのです。
この方のように、求められる能力があれば、何歳になってもSE(システムエンジニア)という働き方はできるのです。
プログラマーの定年と同様にSE(システムエンジニア)の定年も「SE(システムエンジニア)という生き方を辞めようと思ったとき」で間違いないと思います。
SE(システムエンジニア)の35歳の定年説 都市伝説なのか?
上でご紹介したように、定年退職後でも活躍するSE(システムエンジニア)も少なくないので、SE(システムエンジニア)の35歳定年説は真実でないと断言できます。
ただし、『プログラマーの定年 一生プログラマーでいられるか?』にも書かせていただいた通りですが、30台半ばでキャリアの転換が発生する、という意味では「SE、35歳定年説」は的外れではないかもしれません。
サラリーマン経験者であればお分かりになると思いますが、社内の地位が上がって管理職に近づくほど、現場から離れがちになります。
また、そもそもSE(システムエンジニア)とはシステム開発の中では上流工程を担うポジションですが、プロジェクトマネージャー(PM)やITコンサルティングといった、より上流工程に特化したポジションに進む方もいるでしょう。
あるいは、国家資格である「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」を取得しCSIRT(読み方は“シーサート”。インシデント対応部隊のこと)へ配属されたり、ITシステムの安定稼働に責任を持つサービスマネージャーや、システム監査人など、案件に参加しない“専門家タイプ”のSE(システムエンジニア)になる方も少なくありません。
そういう意味で、35歳前後で“脱現場SE”となる方は少なくないのかもしれません。
なお、流布されている35歳定年説にあるような、肉体的限界・スキル的な限界が来る、というのは、不適切なように感じます。
たしかにIT業界は新たな技術の登場が多く、どんどん覚えなくてはいけないこと、習得が必要な知識は増えていくため、それに対応するのは大変である、という指摘は正しいです。
生涯現役を貫くならば、生涯学習し続ける必要は当然あります。
▼ SE(システムエンジニア)はベテランの方が重宝される
しかし、SE(システムエンジニア)は“年の功”が活きる部分が多く、むしろ、百戦錬磨のベテランSE(システムエンジニア)が重宝される傾向にあるように思います。
例えば、クライアントの要望を「要件」に落とし込むためには、クライアントのビジネスモデルやビジネス課題を正しく理解する必要がありますが、若い人だとクライアント担当者の断片的な言葉から、誤ったビジネス課題を設定したり、真の問題に気が付かない、ということもあります。
一方で、現場をいくつも渡ってきたベテランSE(システムエンジニア)だと、過去の経験を活用しながら、クライアントのビジネスモデルを再検討し、クライアントさえ気が付いていない、より根本的な問題に気が付くこともあります。

また、プロジェクトを回すために必要なステークホルダー(クライアントだけでなく、プログラマーなども含みます)とのコミュニケーションスキルなどは、現場経験を重ねれば重ねるほど洗練され、巧みになるものです。
CSIRTやシステム監査人など専門家タイプのSE(システムエンジニア)の場合、「若い人の方が教科書的な知識量は多いかもしれないが、現場経験がない分、実際の業務状況に応じて適切な対処ができない可能性が高い」という考えから、余程の実績・功績がなければ、20代の若いSEがそういったポジションに採用・配属されることはまずないです。
このように、上流工程を担うSE(システムエンジニア)は、若ければ若いほど良いというものでもない、という考え方が広く業界全体に浸透しているように感じます。
35歳以上のSE(システムエンジニア)の役割を調べてみた
上でも、多少触れましたが、35歳以上(つまりは年長者)のSE(システムエンジニア)が現場にアサインされる際のポジションや求められている役割について、もう少し深く分析したいと思います。
そもそも、SE(システムエンジニア)が案件へのアサインのされたときの役割は大きく分けて二つに分かれると感じています。
普通の担当者レベルのSE(システムエンジニア)としてアサインされ、要件定義書の作成など純粋なSE(システムエンジニア)業務を行うパターンと、もう一つはPMやPMの活動支援を行うPMO(プロジェクトマネージャーオフィサー)に任命され、案件全体の管理業務を担うパターンです。
年長者のSE(システムエンジニア)が純粋なSE(システムエンジニア)業務要員として案件へアサインされた際は、担当者レベルのSE(システムエンジニア)たちのリーダーとしての役割が求められている、と考えて良いでしょう。
逆にPMやPMO(事務局スタッフなんて言い方をするところもありますね)は案件スコープの確定など、文字通り案件の統括者として案件がより良い方向に進むために必要な物事を整理しながら、案件を回していくのが仕事になります。
PMには自身の持つ専門的な知識を活用し決断する力が必要になりますし、PMOはPMの懐刀として、案件がより良い方向に進むようフットワーク軽くアクションすることを求められています。
なお、PMOとしてアサインされたSE(システムエンジニア)は、単にPMのために資料を作ったり、工数を数えるだけでなく、場合によっては、担当者レベルのSE(システムエンジニア)たちに直接的な支援(一緒に要件定義書を作成するなど)を行うこともあります。
実際の案件を見ていると、PMはクライアントの担当者や一次受けIT企業のプロパー社員から任命し、実際のキーマンとして、PMOにフリーランスの中から見つけた、百戦錬磨のベテランSE(システムエンジニア)を配置する組織構成が散見されるように思います。
まとめ:SE(システムエンジニア)は老人になっても続けられる
今回はSE(システムエンジニア)として何歳まで働くことができるかを見てきました。
すでにお伝えした通り、「SE(システムエンジニア)は若いほど良い」という考え方は、必ずしも肯定されておらず、経験がある人、現場が長い人を重宝される傾向にあります。
そのため、本人がSE(システムエンジニア)として社会に求められる知識の習得を続ける限り、何歳になってもSE(システムエンジニア)として働き続けることは難しくありません。
なお、これは余談ですが、プログラマーに対してSE(システムエンジニア)へのキャリアアップを推奨する人が少なくないのは、「プログラミングは集中的や気力の仕事であるため、プログラマーは若い人の方が良い」という考え方を持っているクライアントがいる一方で、SE(システムエンジニア)は年長であることがハンディキャップにならないどころか、場合によっては有利に働く、というのも理由の一つです。
現在、プログラマーで年収や待遇に不満のある方、将来に不安のある方は、SE(システムエンジニア)へのキャリアアップを検討してみてはいかがでしょうか。