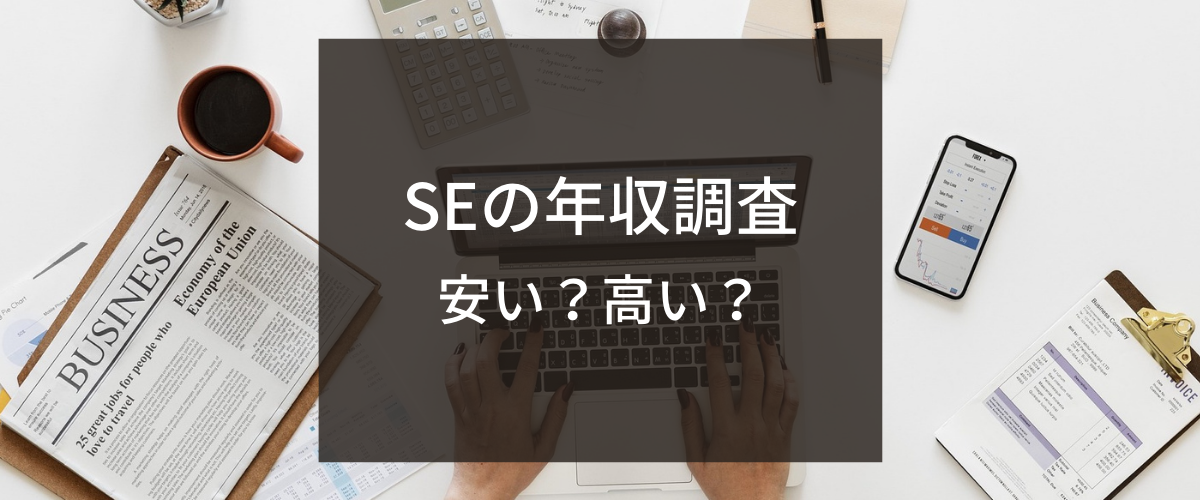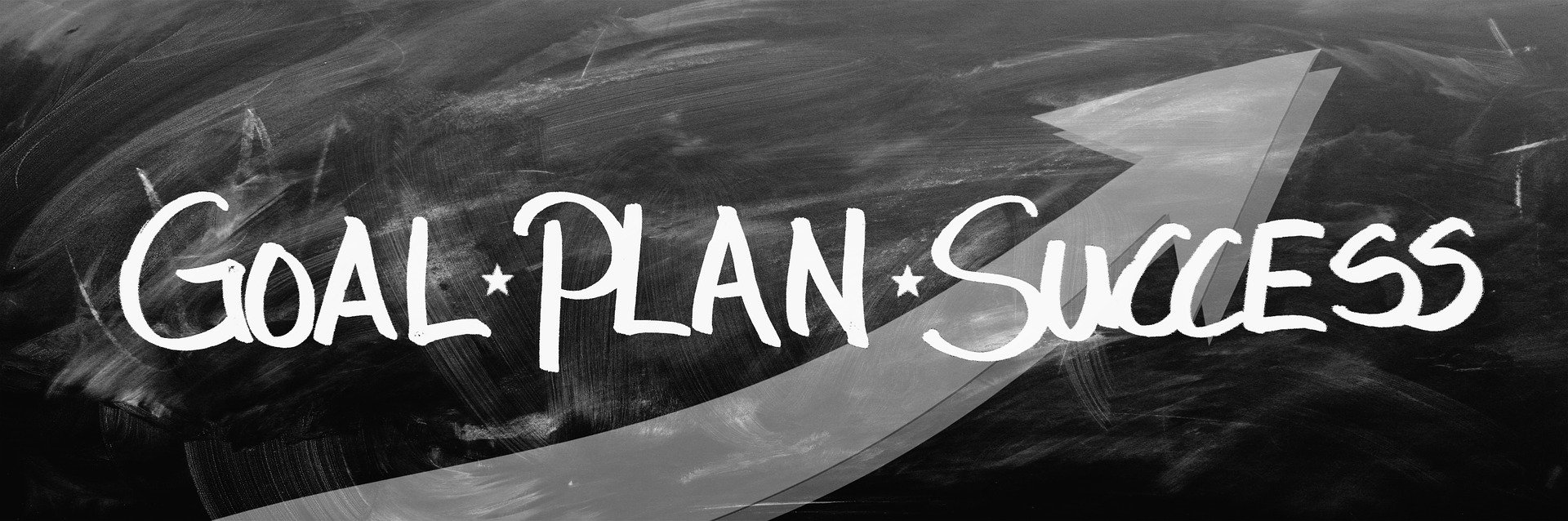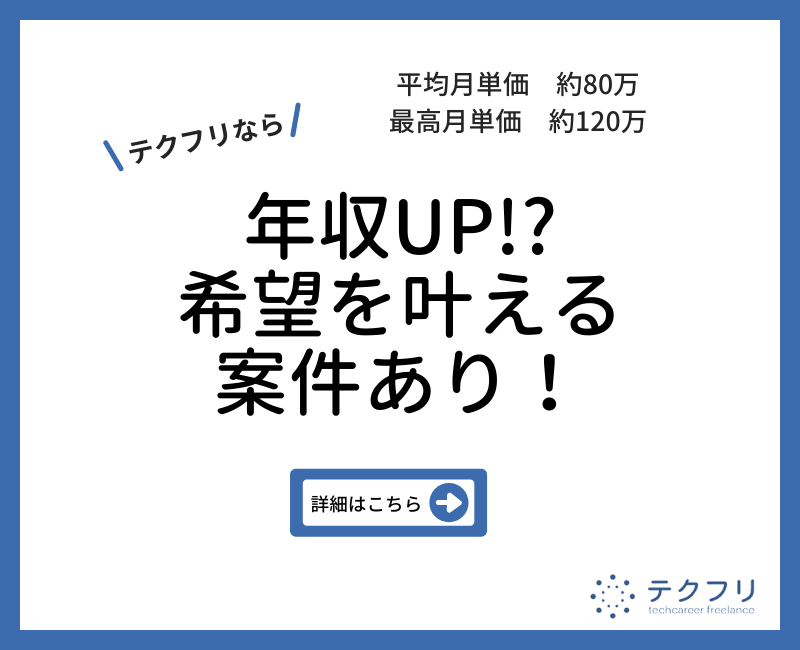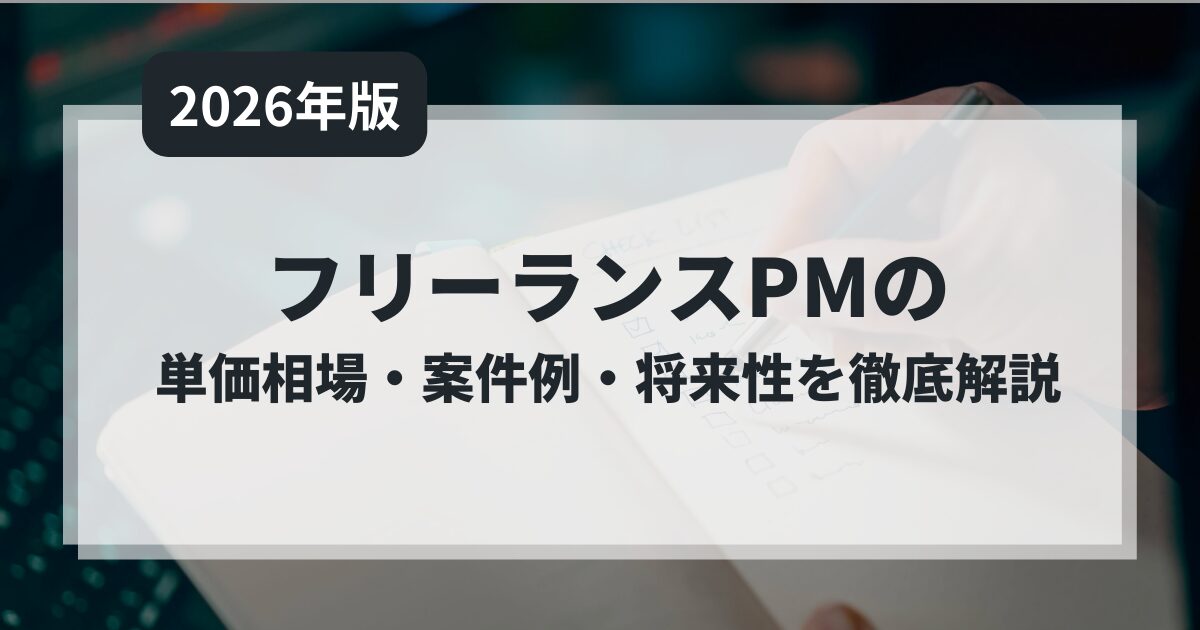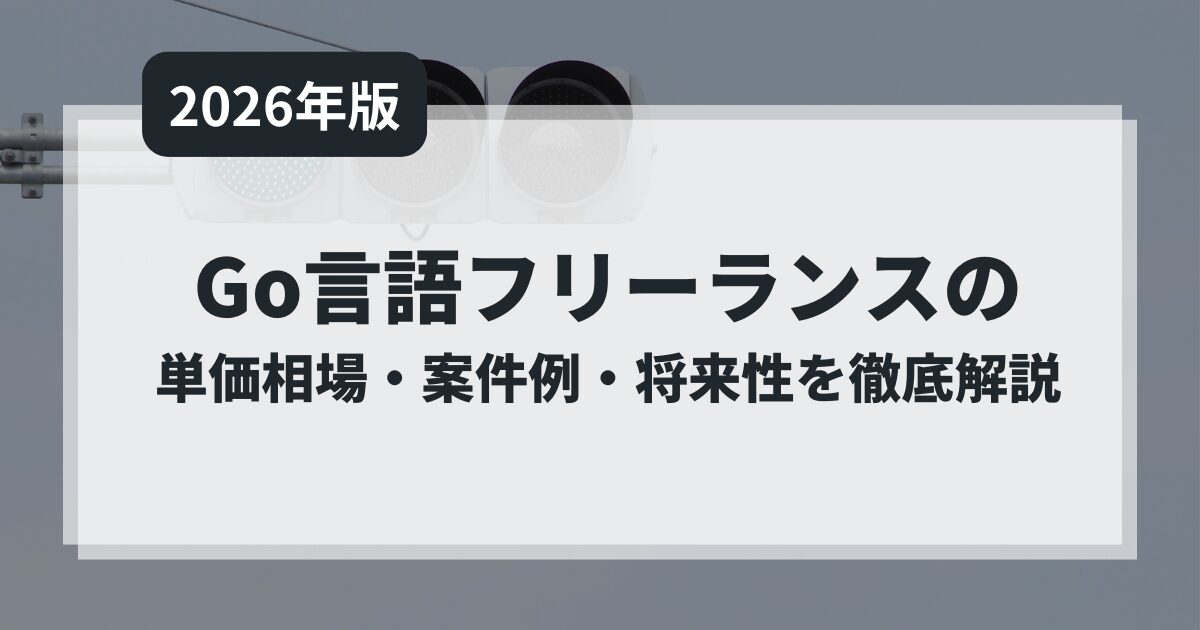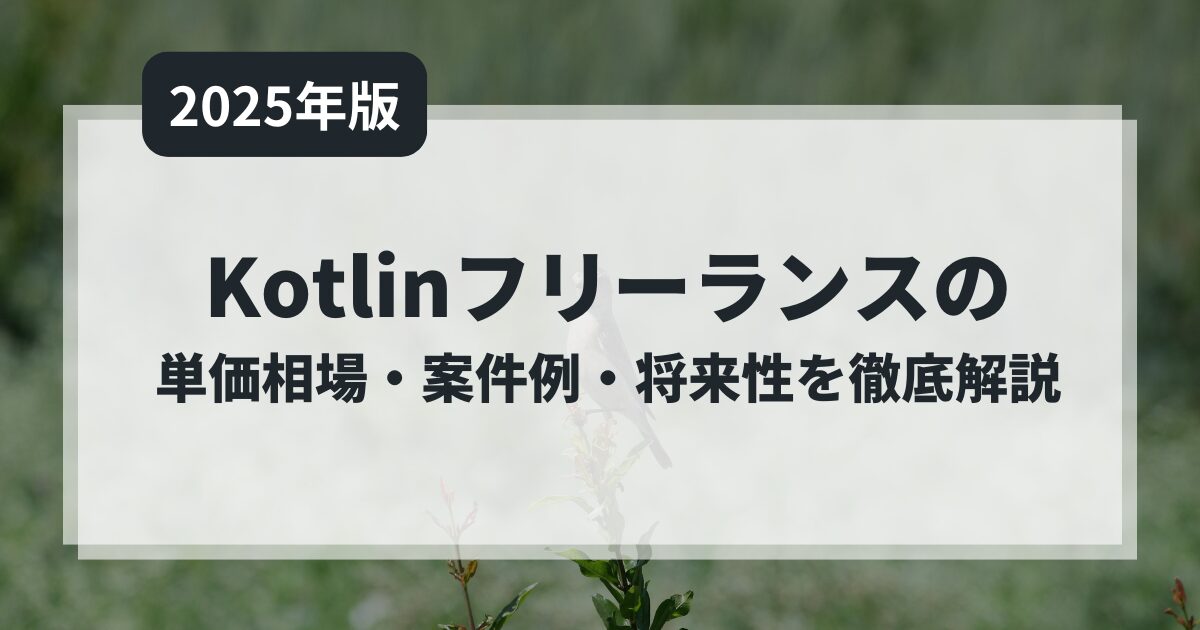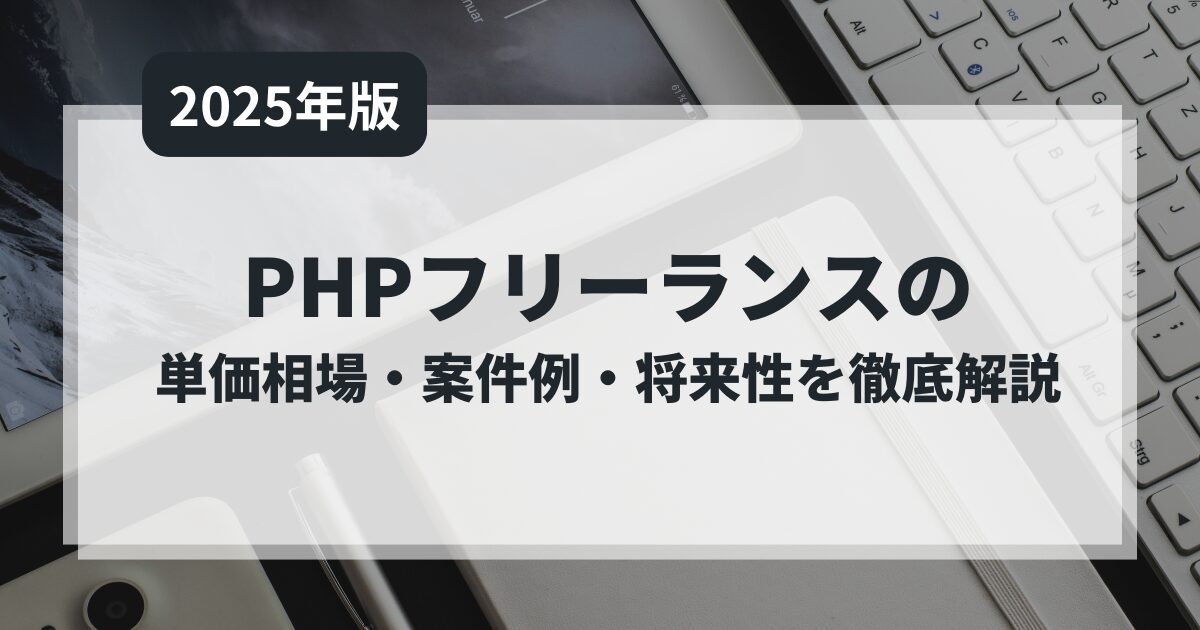IT業界で求人を探そうとすると、「Web系」「オープン系」「汎用系」といった聞きなれない言葉が並び、「どれがどんな仕事をやるんだろう?」と疑問に思ったことがある人はおおいかもしれません。
実はIT業界の中にもいくつかの系統があり、どの系統の企業に入社するかによって携わる仕事も大きく異なってくるのです。
ここではWeb系に焦点を絞り、この系統で活躍するコーダー・プログラマーの仕事内容について解説していきます。
Web系って何?その業種と職種を俯瞰
「Web系」とは、WebページやWebサービスといった、Web上のシステム・アプリケーションを開発することを指します。スマホアプリやパソコン向けのソフトウェアではなく、Webサイトの構築に特化して仕事を手がけていることが特徴です。
Web系の中でも、「フロントエンド」「バックエンド」の大きく2つの分野に分かれています。フロントエンドはWebサイトの見た目の構築を担当し、HTMLやCSSといったマークアップ言語を使用します。
一方のバックエンドとは、Webサイトの裏方でサーバーやミドルウェアを開発する仕事です。JavaやPHPといったプログラミング言語を使用して作業を行ないます。
WebサイトやWebサービスは今後も需要が増していくと考えられることから、Web系は高い将来性を持つ業界でもあります。Web系のコーダーやプログラマーも人手不足状態にあることから、未経験でも採用されやすいという特徴も持ちます。
Web系の業界で働く人材としては、次のような職種があげられます。「コーダー」「Webデザイナー」「フロントエンドエンジニア」「Webコーダー」「マークアップエンジニア」「プログラマー」「バックエンドエンジニア」「システムエンジニア」などです。
とはいっても、Web系の会社では肩書きを明確に区分することなく仕事に携わっていることも珍しくありません。一般的に見た目をつくるのがコーダー、裏方を支えるのがプログラマーとされていますが、プログラマーがコーダーの仕事を兼任することもよくある話です。
だからといってコーダーの重要性が低いというわけではなく、たとえばWeb制作会社のようにWebページをつくることを専門としているところだと、兼任のプログラマーよりも、高いスキルを持ったフロントエンド専門のコーダーのほうが重宝される傾向にあります。
Web系のコーダーはどんな仕事?

フロントエンドと呼ばれる、Webサイトの見た目をつくるのがWeb系のコーダーの役割です。具体的にはHTMLやCSSといったマークアップ言語を使い、文章や画像を表示させたり、ページの見やすさを向上させたりといった作業を担当します。
プログラマーが習得するプログラミング言語とは異なり、マークアップ言語は、比較的習得が容易という特性を持っています。そのため学生アルバイトに仕事を任せているというケースも珍しいことではありません。
近年ではプログラマーがコーダーの仕事も兼ねる場合も多くなっていることから、「仕事がなくなるのではないか」「需要が減っている」という声もよく聞かれます。プログラマーが兼任できる仕事であると考えると、「あまり必要とされていないのでは?」と考える人も多いかもしれません。
しかしコーダーはWebサイトの見た目を整える仕事であり、デザインスキルやセンスが問われるポジションでもあります。裏方ではいくら処理速度の高いシステムを組んでいたとしても、見た目がダサくて使いづらいWebサイトだったら、誰も使いたいとは思いませんよね。
確かに「コーダー」という職種で求人を出しているところは少ないため、需要が減っているような錯覚に陥ることは多いかもしれません。しかし「Webデザイナー」「フロントエンドエンジニア」と呼ばれる職種も、基本的にはコーダーと同じ仕事を担当します。
Webサイトの見た目を整えるフロントエンド担当のコーダーが、その呼び方を変えて募集されているということなので、需要が減っているという見方は正しくありません。ちなみに、ほかにも「Webコーダー」「マークアップエンジニア」という呼称で募集している求人もありますので、よくチェックしてみるようにしてください。
Web系のプログラマーはどんな仕事?
フロントエンドを担当するコーダーに対し、バックエンドを担当するのがプログラマーです。裏方を支える仕事とあって、地味で目立たないことから重要性を意識する機会は多くないかもしれません。
しかしコーダーと同じくプログラマーもWeb系には欠かせない存在で、時にはフロントエンド・バックエンドのどちらにも対応できるスキルを持った、フルスタックエンジニアが活躍しているケースもよくあります。
HTMLやCSSといったコーダーが扱うマークアップ言語よりも、JavaやPHPといったプログラマーが扱うプログラミング言語のほうが、習得するまでの難易度が高く、レベルの高いスキルとされています。
コーダーの仕事も兼任するプログラマーが多いこともあってか、コーダーよりもプログラマーのほうが地位が高いと考える人も少なくないようです。しかしコーダーとプログラマーは、担当する領域が異なるだけで対等な立場のポジションです。
Web系の企業にプログラマーとして入社したとしても、決してコーダーを下に見ることがないよう注意したいものです。
コーダーとプログラマー スキルの違いを解説
フロントエンドとバックエンド、それぞれ担当する領域が異なりますので、コーダーとプログラマーは求められるスキルも大きく異なってきます。コーダーはマークアップ言語と呼ばれるスキルが必要とされ、プログラマーはプログラミング言語の知識が不可欠となります。
「どちらを目指したらいいのかいいのかわからない」という場合には、見た目を重視するか、中身を重視するかという基準で職種選びを進めてもいいかもしれません。見た目を構築するのはコーダー、中身をつくるのがプログラマーとなりますので、どちらが自分の目指すものに近いかを考えると、理想のキャリアパスの一助となるでしょう。
一般的にプログラマーのほうが求められるスキルレベルが高いことから、高い年収が設定されることが多くなります。IT業界でガッツリ稼ぎたいと考えるのであれば、プログラマーを重視するという手も考えられます。ただしプログラミング言語の習得に大きな手間と時間がかかることも念頭に置いておきましょう。
コーダーまたはプログラマーのどちらを歩むとしても、開発言語のスキル以外にも磨いておきたいスキルが1つあります。それは「コミュニケーション能力」です。
コードやプログラムを書く仕事といえば、ひたすらパソコンに向かってキーボードを叩いているエンジニアの姿が思い浮かぶかもしれません。しかしWebディレクターやシステムエンジニアのような職種へステップアップすると、必然的にお客さんとの打ち合わせに参加することが多くなってきます。
ここでコミュニケーションが苦手なままだと、いつまで経ってもキャリアアップが叶わないというケースも考えられます。したがってIT業界でこれからも活躍していきたいと考えるなら、開発言語のみをマスターしようと考えるのではなく、周囲の人々とも積極的に交流していこうとする姿勢が大切になるのです。
まとめ:IT業界に欠かせない存在
Web系とは、Web上で動くシステムやWeb上で表示されるページをつくる仕事です。見た目をつくるフロントエンドではコーダーが、裏方のバックエンドではプログラマーがそれぞれ活躍し、IT業界に欠かせない存在として力を発揮しています。
職種によって必要とされるスキルは異なりますが、開発言語とともにコミュニケーションスキルも磨くようにすると、これからのキャリアパスが大きく開けてくることになるでしょう。
Web系に関心がある方、コーダーやプログラマーになりたいと考えている方は、これからのキャリアを考えるうえでの参考としてみてくださいね。