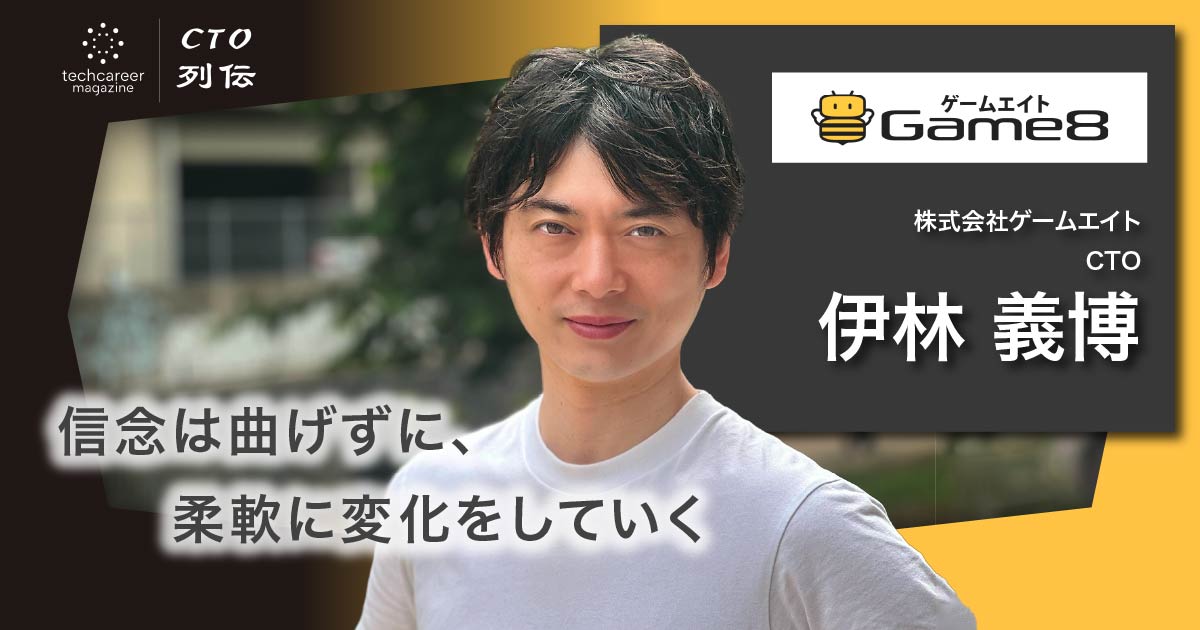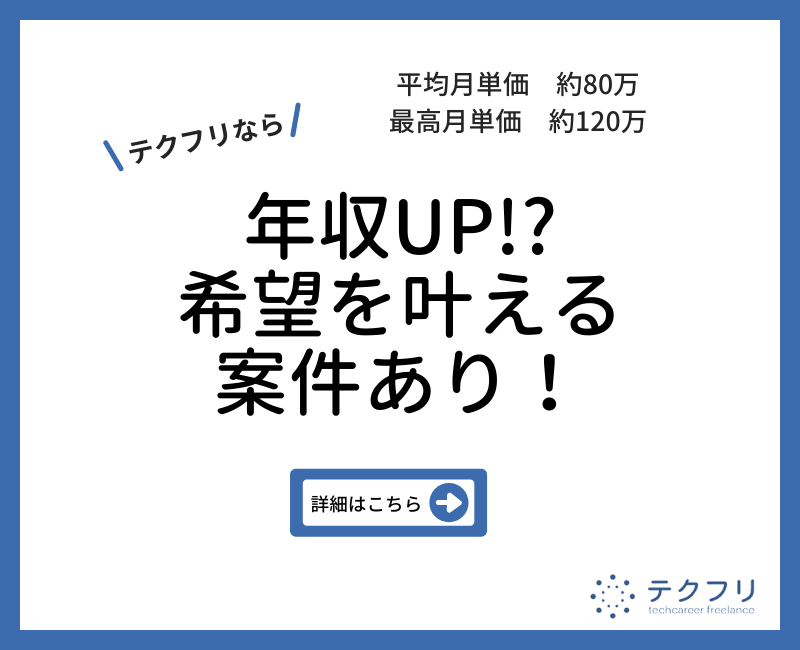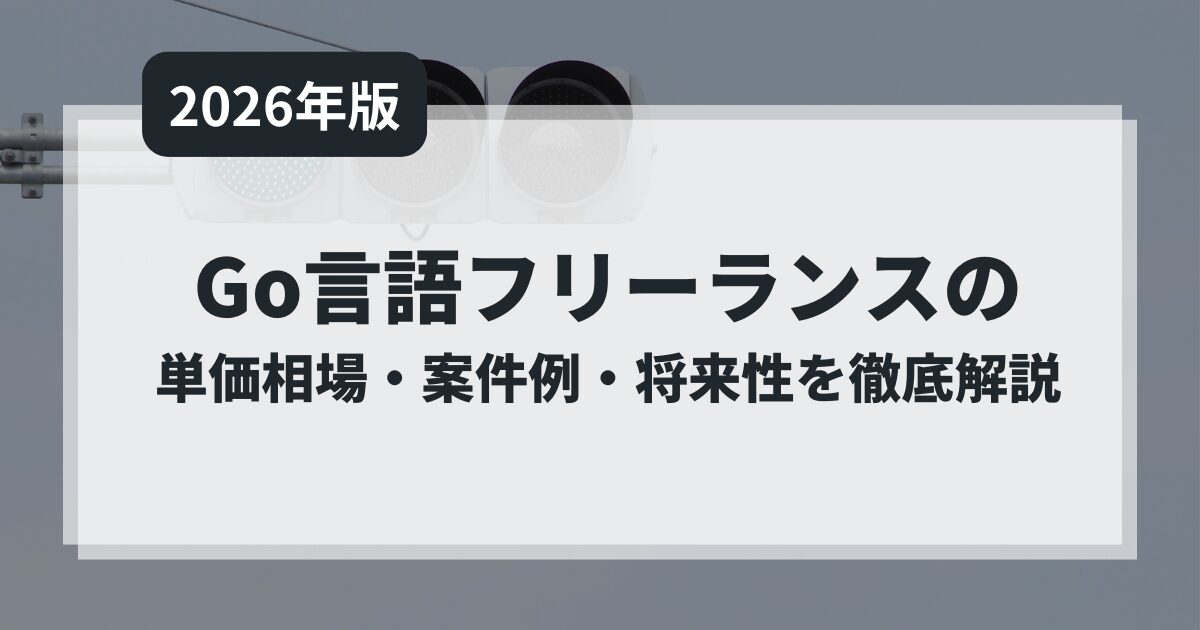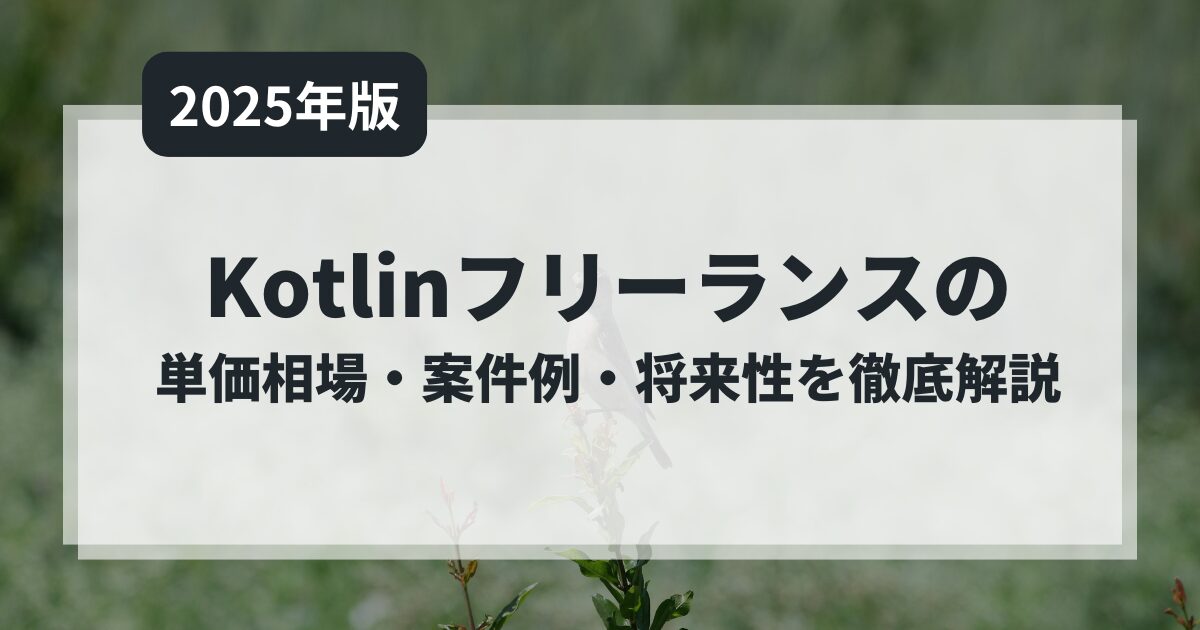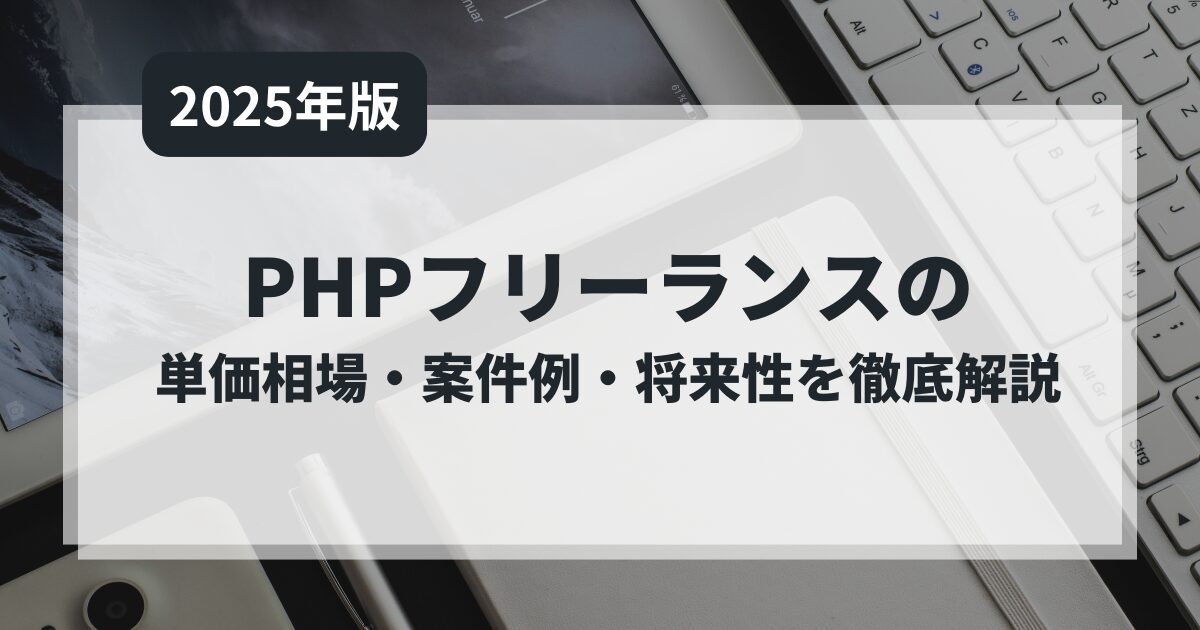今回は、株式会社iCAREでCTOを務める工藤 大弥さんのインタビュー記事をお届けします。工藤さんは、小学生の頃から父親の自作PCに触れてプログラミングに興味を持ち、工業高校からIT系の専門学校へと進みました。ベンチャー企業での受託開発、フリーランス、複数のスタートアップでのCTO経験を経て、現在はiCARE社でCTOとして法人向け健康管理サービスの開発に携わられています。そんな工藤さんが仕事をするうえで大切にされていることは、「楽しむこと」。数々の経験を積まれてきた工藤さんのキャリアや仕事の価値観に迫ります。
インタビュー概要
お話を伺った企業さま
会社名 :株式会社iCARE
設立 :2011年6月
資本金 :100,000,000円
上場市場 :未上場
代表者 :山田 洋太
所在地 :東京都品川区
ミッション :働くひとの健康を世界中に創る
事業内容 :法人向け健康管理ソリューションサービス「Carely(ケアリィ)」の開発・運営
URL :https://www.icare-carely.co.jp/
お話を伺ったご担当者さま
部署 / 役職 :CTO
氏名 :工藤 大弥
1990年生まれ、茨城県水戸市出身。IT系専門学校卒業後、受託開発を行うベンチャー企業にてWebエンジニアの道を歩み始める。0→1の新規Webサービス開発を得意とし、シード期のスタートアップのリードエンジニアやCTOを経験。過労により休職をした経験から、自身や組織の健康づくりに対して関心が高く、2020年11月より業務委託としてiCAREに参画。2022年1月より正社員となり、開発プロジェクトのリードやチームビルディングを担う。2022年11月にVPoE、2023年8月より現職。
キャリアについて
小学生時代にパソコンに出会う:工業高校からIT系専門学校へ
私がはじめてパソコンに触れたのは、小学4年生の時に遡ります。父親が趣味で自作PCを作っており、お下がりをもらったことがきっかけです。当時はペイントやタイピングゲームで遊んだり、インターネットでゲームの攻略法を調べたりしていましたね。
中学生になると周りの友達もパソコンを持つようになり、放課後にオンラインチャットで集まって遊んでいました。当時卓球部だったので、卓球用具のレビューを掲載するWebサイトを作ったりもしていて、これがすごく楽しかったんです。この経験からプログラミングに興味を持ったので、工業高校からIT系専門学校に進学しました。
専門学校ではWeb系ではなく、組み込み系のシステム開発を学びました。プログラミングは好きでしたが、実は当時、エンジニアとして就職する気は一切なくて、就活もしていませんでした。インディーズバンドなどのライブにハマっていて、年間100日以上ライブハウスに行くような生活をしていたので、卒業後はフリーターとしてライブハウスで働こうと思ってました。しかし、プログラマーとして働いていたアルバイト先のベンチャー企業から誘いを受け、その企業にエンジニアとして就職することになりました。
ベンチャー企業でエンジニアの基礎力を身につける
2010年に新卒で入社した企業は、5名規模のベンチャー企業でした。エンジニアは社長と私だけで、当時の主な事業内容はソーシャルゲームの受託開発です。アルバイトの頃はちょっとしたプログラムの修正程度でしたが、社員になってからはがっつりプロジェクトに入るようになりました。当時は、何がわからないかがわからない状況。毎日必死で食らいつこうと働いていました。入社3年目からは自社でもソーシャルゲーム開発を始めることになります。私は今でいうプロダクトマネージャーのような役割も担わせてもらい、企画から実装、運用まで幅広く携わりました。
スタートアップでの挑戦と挫折:リードエンジニアとCTOを担う
その後は、フリーランスエンジニアとして働くことにしました。1社目に在籍していた頃に一緒に働いた方のご縁で案件を紹介いただき、ソーシャルゲーム開発を中心にフリーランスとしてお仕事をさせていただくことになったんです。
2014年、フリーランス2年目のタイミングで、スタートアップの正社員として働き始めることになりました。その会社の代表とはライブハウスで出会い、半年ほど事業アイデアの壁打ちに関わっていたら資金調達が決まり、1人目のエンジニアとしてジョインしました。開発したプロダクトは、「友達作りのマッチングアプリ」と「音声チャットアプリ」の2つです。リードエンジニアとして主にアプリのバックエンド側の開発をリードしながらも、3〜4名規模だったので、企画段階からあらゆる業務を担当しました。
そのスタートアップは残念ながら事業がスケールできず会社を畳むことになりました。その後またフリーランスの期間を経て、2017年に創業期のスタートアップでCTOに就任しました。事業内容は、物置版のAirbnbのような、家やオフィスの空きスペースを貸し出すtoCのマッチングプラットフォームです。創業期なのでガンガン手を動かすCTOとしてプロダクト開発に専念していまして、サービスも少しずつ伸びていきました。しかしコロナの影響で大幅に事業戦略を見直さねばならなくなり、それがきっかけで退任に至りました。
iCAREのパーパスに強く共感し、入社
その後またフリーランス期間を経て、2020年11月にiCAREにジョインしました。最初は業務委託で関わっており、社員になる気はありませんでした。しかし業務委託として1年ほど働いたタイミングで社員転向のお誘いをいただきまして、当時のCTOを始めとする経営陣からの熱烈な誘いに心を動かされてしまったんです。今後のキャリアをどう築いていくか悩んでいたタイミングでもあり、自分のことを必要としてくれている環境で仕事をしようと入社を決意しました。
また、iCAREの「働くひとの健康を世界中に創る」というパーパスへの共感も入社の決め手の1つです。iCAREは、法人向けに健康管理を支援するサービスを提供しています。私自身も過去に過労で心身を壊してしまったことがあったり、飲食業界で働いていた父も激務によって40代半ばで脳梗塞になってしまったりという過去があります。iCAREであれば、自分の持つエンジニアリングの力で「働くひとの健康づくり」という大きな社会課題の解決に挑戦できると感じました。
2022年1月に正社員となり最初は、開発チームのリーダーとして4名のチームを率いました。Carely健康管理クラウドの新機能の開発プロジェクトをリードしたり、社内の請求業務オペレーションを改善するための社内システム開発の推進も担いました。そういったプロジェクトでの実績を評価いただき、2022年11月からはVPoEとして開発組織全体のマネジメントを担当させてもらうことになりました。
その後2023年8月にCTOに就任させていただき、経営戦略と技術戦略を繋ぐ役割を担っています。2025年1月までCTOと開発部長を兼務していましたが、2月より新任のVPoEに開発組織のマネジメントを引き継ぎました。その分私は技術へのコミットメントを高め、現在はR&DチームでLLMを活用した新規サービスの研究開発に励んでいます。
リードエンジニアの経験を通して大きく成長
エンジニアとして一番大きく成長できたと感じたのは、1人目社員として入ったスタートアップでリードエンジニアとしてtoCアプリの開発を担った時です。マネタイズが難しく、最終的には事業をクローズすることになりました。当時は「良いものを作れば売れる」と思っていて「どう売るか」を深く考えていなかった点が大きな反省です。しかし、リードエンジニアとして裁量を持ってやれる環境だったので、その上で様々な失敗・成功体験を積むことができました。この経験が、エンジニアとしての今の自分の基盤になっています。
企業の健康管理をDXする
今後の目標として、企業が取り扱う健康データを正確でスピーディにお客様に活用していただける状態を実現したいと考えています。例えば紙の健康診断結果をデジタル化するには、すごく労力がかかるんです。エンタープライズ企業だと、データ化するための専門チームがあったりするくらいです。この領域はテクノロジーで解決できる伸びしろが大きいと感じています。現在弊社ではOCR(Optical Character Recognition/Reader:光学的文字認識)やAIを掛け合わせて、紙の健康診断結果の写真からのデータ化を正確でスピーディに実現しようとしています。現在は、R&Dチームで研究開発に取り組んでいるのですが、早く実用化をさせて、ユーザーへ便利なものを届けていきたいです。
また個人的には、夢のひとつであった技術書を出そうと動き始めています。先日、Ruby技術書執筆助成金のプログラムに応募をしたら、採択していただいたんです。こういった活動を通して、今後は、後進育成にも力を入れていくつもりです。16年のエンジニア歴やCTOとしての経験も含めて、次の世代に伝えられることがあると思っています。
考え方・マインドについて
仕事を楽しむために、自ら裁量を取りに行く
私が仕事をするうえで大切にしていることは、「楽しむこと」です。フリーランスから社員になった一つの理由に、「楽な仕事」と「楽しい仕事」は全然違うと感じたことがあります。私は多趣味なこともあり、ワークライフバランスの最適化を検証しようと思いフリーランス時代に週3日だけ働くライフスタイルを1年ほどやっていました。趣味にあてる時間が大幅に増えて楽しむことができました。しかし、仕事で担える役割がどうしても限定的になってしまうので働くことがあまり楽しくなかったんです。今では、CTOとして大きい役割を任せてもらえていて、仕事もすごく充実しています。CTOというポジションは楽ではありませんが、とても楽しいです。一人では達成できない大きな目標に対して、裁量を持って意思決定をし、うまくいった時に大きなやりがいを感じます。その楽しさ、やりがいを得るために、裁量・責任をあえて取りに行くことが私のキャリアで重視していることかもしれません。言われたことをただこなすってのが出来ないんですよね(笑)。
AI時代に価値あるエンジニア:打席に立つことを恐れない
AIコーディングエージェントの進化が著しい昨今において、人の手で地道にコードを書くことはもはや趣味の領域になっていくはずです。業務でエンジニアに求められるスキルが急速に変化していく中、そんな環境でも活躍できるエンジニアの重要な要素が、私は3つあると考えています。
1つ目は、「打席に立つことを恐れないこと」です。生成AIの進歩により、プロトタイプの開発コストやドキュメンテーションのコストはすごく下がりました。アイデアがあれば、プロンプトを書くだけで試すことができます。アイデアをアイデアで終わらせずにプロトタイプやドキュメントにする。周囲を巻き込んで動かす。まずは打席に立つ回数を増やす。空振り三振(失敗)しても良いんです。量がいつしか質に繋がります。だからこそ、量をこなしてどれだけ試行錯誤できるかが成果を出す上で重要だと考えています。
2つ目は、「コミュニケーション能力」です。エンジニアの役割は変わりますが、AIも含めたチームで「コミュニケーション」を取りながらソフトウェア開発をするというのは変わらないと思います。AIに指示を出して成果物を出してもらいながら、人が評価をし、ステークホルダーと連携をして開発を進めていく。その過程でのコミュニケーション能力や「いいやつでいること」は、今までも大事でしたし、これからも変わらず大切だと考えています。
3つ目は「技術好奇心」です。実行力も技術への好奇心から生まれるものがあります。生成AIのように新しい技術が出てきた時に「これはどう活かせるのだろうか?」といった好奇心を持って試し、何が得意で、何が苦手な技術なのか、肌感覚を掴むことがとても重要です。これまでも最新技術のキャッチアップはエンジニアとして活躍し続ける上で大切な要素でしたが、より重要性が増していて「やる人/やらない人」でとても大きな差がつく時代になってきていると考えています。
フリーランス活用:多様な関わり方で価値創造
現在弊社では、8名のITフリーランスのパートナーの方々に入っていただいています。フルコミットに近いかたちで入っている方は、開発チームに加わっていただき、新機能開発や機能改善をお任せしています。その他のポジションとしては、技術顧問の方もいます。勉強会を開いていただいたり、技術的な相談に乗ってもらっています。フリーランスの方々に入っていただくことで組織のケイパビリティとして不足しているスキルセット・経験を補うことができ、様々な関わり方で一緒に価値を創造していけるのが良いところだと感じています。
iCAREで働きたい方へ
働くひとの健康を世界中に創る
弊社は、「働くひとの健康を世界中に創る」をパーパスとして掲げ、企業の健康経営・産業保健活動を支援するソリューションサービスを提供しています。代表の山田は産業医で、社員にも保健師の資格を持つメンバーが複数在籍しています。我々エンジニアが開発している主力サービスは、「Carely健康管理クラウド」です。健康診断結果やストレスチェックのデータなど、従業員の方々の健康情報を一元管理できるSaaSです。また、例えば健康診断においては「就業判定」と呼ばれる、健診結果を元に従業員が就業を継続しても問題ないか確認するプロセスが労働安全衛生法によって義務付けられています。その際に、Carely健康管理クラウドを使っていただくと、業務オペレーションがスムーズになり、その後の健診結果データ活用もしやすくなります。また、クラウドサービスだけではなく専門家によるサポートサービスも提供しており、産業保健・健康経営に関する専門知識を活かして、企業の健康課題の解決に寄与しています。システムと専門家の両軸でサービス展開をすることで、最前線で企業の健康課題解決に取り組む専門家からのフィードバックを受けながら、プロダクト開発を進められることが弊社の大きな強みだと思っています。
「健康づくり」という身近な課題解決に取り組める魅力
弊社で働いていただく際に一番やりがいを感じていただけるポイントは、「働くひとの健康づくり」という多くの人々にとって身近な、自分ごと化しやすい社会課題の解決に取り組めることです。社員の中にも、自身や周囲の人が働くことで不調となってしまった経験がある人も多く、事業への共感度合いが高いメンバーが多く集まっています。
技術面では、Carely健康管理クラウドが来年でリリース10周年を迎えることもあることや、生成AIの進化も鑑みて、システム基盤の大幅なリファクタリング・リアーキテクチャに取り組んでいこうとしています。こういった経験は、エンジニアリングスキルを伸ばせる良い経験になると思います。
組織横断な連携で、お客様の課題解決にあたる
弊社の開発組織は、正社員が22名、業務委託8名の合計30名の規模感です。プロダクト開発は1チームあたり4〜6名で新規機能開発や既存機能の改善プロジェクトに取り組んでいます。エンジニアも開発の上流から積極的に関わり、どんな機能を作ることが顧客にとって本質的な価値に繋がるのか真剣に向き合っています。組織横断な連携を大切にしながら開発を進めており、PdMやCS、セールス、保健師など様々なメンバーと一体となってお客様の課題を特定し、仕様を詰めていっています。
「エンジニアとして生きている方」を募集中!
弊社では、やはりパーパスへの共感が強い方が活躍しやすいと感じています。日本の産業保健の歴史は1972年に労働安全衛生法の誕生とともに始まりましたが、テクノロジーを活用できる領域はまだまだたくさんあります。弊社はフラットに経営陣に対しても意見を話しやすい環境です。「AIが進化していく中でどうやって新たな価値を生み出せるか?」といった妄想を一緒に膨らませながら、実際に行動に移せるチャレンジ精神の強い方と一緒に働きたいですね。
また、私が時折使う表現なのですが、普段から「エンジニアとして生きている方」にはすごく魅力を感じます。例えばプライベートでも勉強会やカンファレンスで登壇されていたり、SNSやブログで技術情報の発信をされていたり、個人開発やOSS活動をされているような方ですね。常にエンジニアとしてのアイデンティティがあって、仕事としてもエンジニアリングをしているという方です。こういった価値観を持つ方と働きながら技術談義ができるとすごく刺激的なので、ぜひ弊社に来ていただきたいと思っています。
取材を終えて
工藤さんのインタビューからは、「楽しむこと」を軸にしたエンジニアとしての生き方が強く印象に残りました。フリーランス時代の経験を通じて、楽な仕事と楽しい仕事の違いを見極め、裁量を持って挑戦できる環境を求めて歩んできたキャリアは、多くのエンジニアにとって参考になると思います。「健康づくり」という身近で重要な社会課題を、テクノロジーの力で解決しようと取り組まれているiCAREさん。そんな彼らの事業や目指す世界に共感をされた方は、ぜひ一度話を聞いてみてはいかがでしょうか?