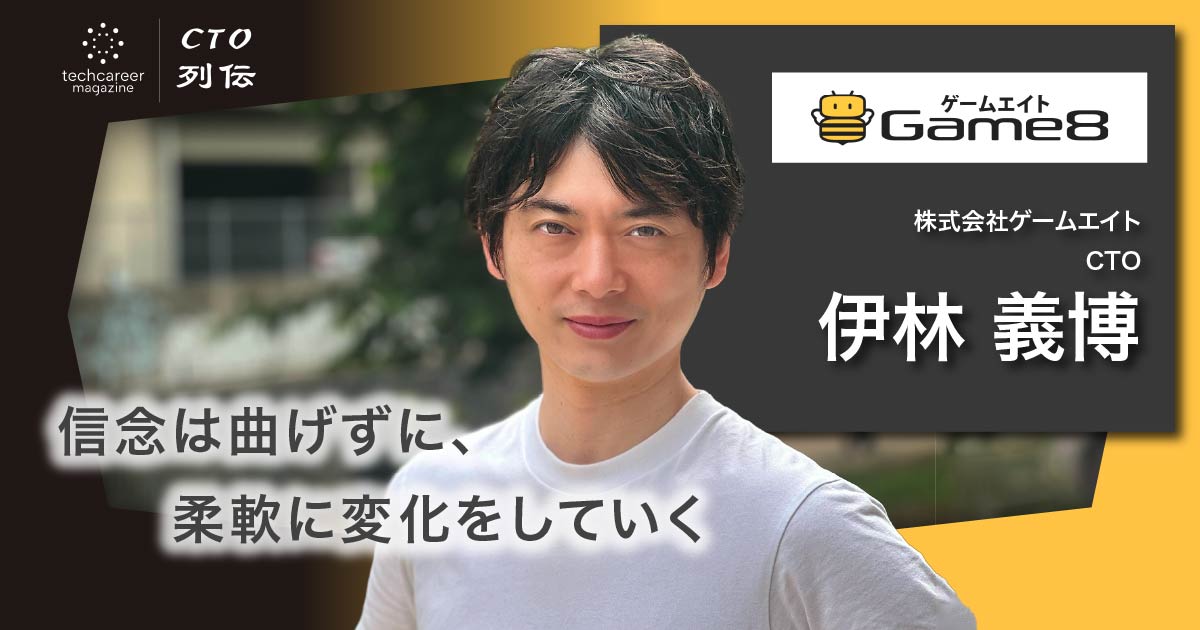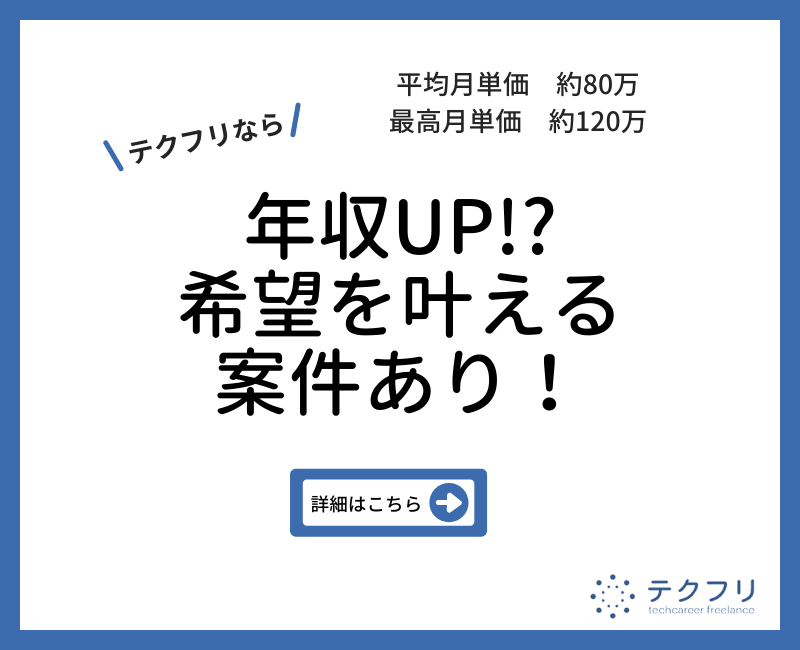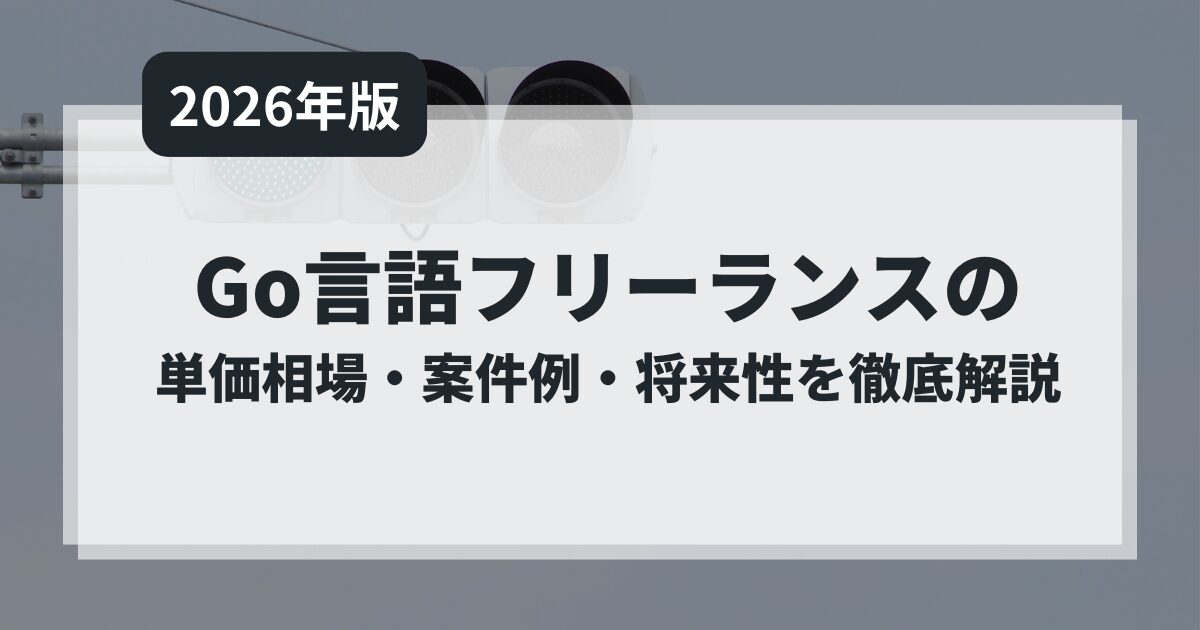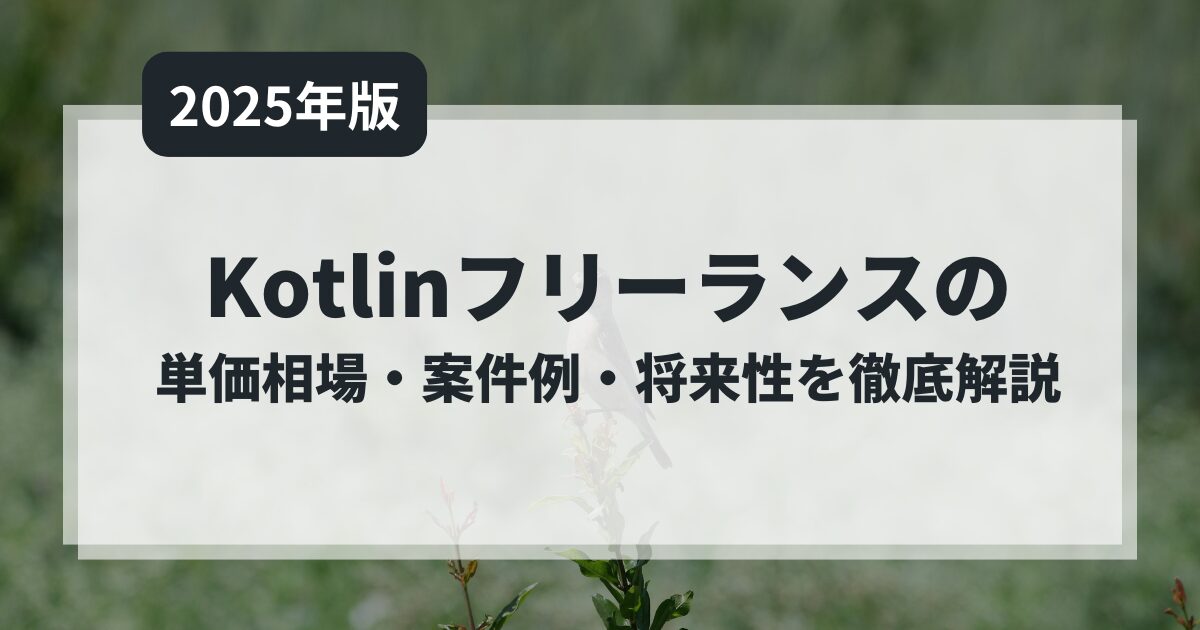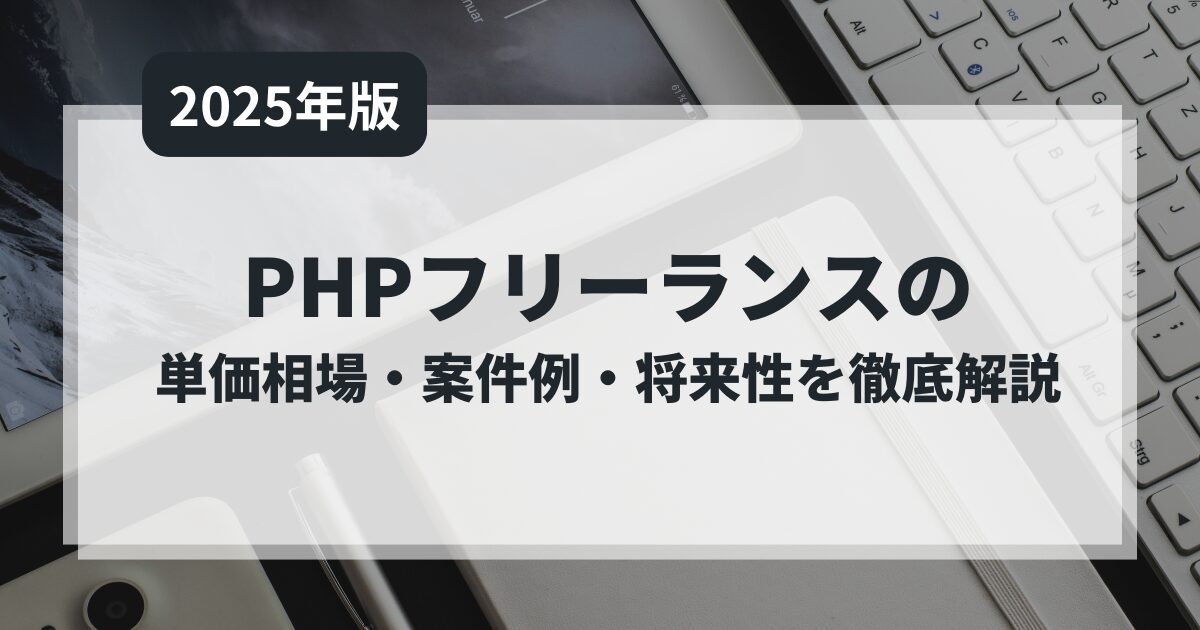今回は、MOSH株式会社でCTOを務める村井亮介さんのインタビュー記事をお届けします。村井さんは、8歳からプログラミングに触れ、大学時代のインターンを経て新卒でプロシーズに入社。その後Rettyで経験を積み、2017年にMOSHを共同創業されました。現在は、「情熱が巡る経済を作る。」というミッションのもと、サービスクリエイター向けのプラットフォームを開発しています。そんな村井さんが大切にされていることは、「自分が作ったもので、人の役に立ちたい」という想い。失敗を重ねながらも熱い思いでプロダクト開発と向き合う村井さんのキャリアと価値観に迫ります。
インタビュー概要
お話を伺った企業さま
会社名 :MOSH株式会社
設立 :2017年7月
資本金 :100,000,000円
上場市場 :未上場
代表者 :籔 和弥
所在地 :東京都渋谷区
ミッション:情熱がめぐる経済をつくる。
事業内容 :インターネットビジネスの企画・開発・運営
URL :https://corp.mosh.jp/
お話を伺ったご担当者さま
部署 / 役職:共同創業者兼CTO
氏名 :村井 亮介
学生インターンを経て株式会社プロシーズに入社。エンジニアとしてのキャリアをスタートさせ、この時に籔と出会う。その後入社したRetty株式会社ではアプリ・ウェブの企画開発に従事。2017年、籔・村山とともにMOSHを創業。趣味はログの記入。
キャリアについて
8歳からのプログラミング体験:漫画管理からWeb開発へ
私がはじめてパソコンに触れたのは、8歳くらいの頃です。興味本位で最初に「漫画の管理システム」を作ってみました。漫画が好きで本棚にたくさん入れていたのですが、何を何巻まで買ったかがわからない状態だったんです。そこで、マクロを組んでどの漫画を何巻まで買ったかを管理できるシステムを作ってみました。これが私にとって最初のプログラミング体験ですね。
高校卒業後は情報系の大学に進学しました。プログラミングの授業もありましたが、「将来はエンジニアになろう」とは全く思っていませんでした。そんな私がエンジニアを目指すきっかけになったのが、引っ越しのアルバイトです。猛暑の中でも過酷な作業をしないといけず、始めたての頃は慣れないこともあって他の作業員にかなり強く注意されることもありました。「仕事ってこんなにしんどいのか」と絶望していた時に、プログラミングを書いてお金がもらえることを知ったんです。安直ではありますがその時に、「エンジニアであれば、炎天下で作業をしなくても良いし、身体的にきつい仕事ではない」と思ったんです(笑)。そこで、プログラミングのインターンを募集していたプロシーズで2年ほど働き、大学をやめる判断とともに正社員として就職しました。
プロシーズで「労働王」になる
プロシーズではEラーニングのマネジメントシステムを作っていました。開発チームメンバーとして入りましたが、大学ではWeb開発を学んでいなかったので、Web独特のものを1からキャッチアップしていきました。プロシーズ含め当時の中小ベンチャー企業の多くは、システムエンジニアリングやマネジメントなどが体系化されておらず、1からキャッチアップしないといけなかったので大変でした。
プロシーズ時代はとにかくずっと働いていましたね。そんなことをしていると、会社から「労働王」という称号をつけられました。でも、長時間労働は全く苦ではなかったです。アルバイトに比べたら理不尽もないですし、むしろ楽しんで仕事をしていました。
MOSH代表籔さんと出会い、Rettyへ転職
MOSH代表の籔と初めて出会ったのは、プロシーズ時代です。彼はインターン生として3ヶ月ほどプロシーズで働き、大学卒業後はRettyに入社していました。その後も連絡を取っていると籔から、「Rettyに来ませんか?」と誘われたんです。Rettyは、私と同年代の技術者が熱量高く働いている会社でした。そんな環境に魅力を感じ、転職することに決めました。
Rettyでは、アプリ開発やWeb開発、採用、グローバル展開などの幅広い業務を担当しました。前職との環境の違いに戸惑うことも多かったです。例えば、トイレに行くときに上司に許可を貰いに行って笑われたり。今思えば笑えますが、当時の私にはそれが当たり前だったんです。周りからは山から猿が降りてきたみたいと言われ、「珍獣」と呼ばれていました(笑)。
また、優秀な人の多さにも驚きましたね。技術的にもレベルが高いのはもちろん、仕事に対する姿勢も学びになることが多く、刺激的な毎日でした。私はエンジニアとして特別優秀ではなかったですが、とにかく誰よりも量をこなすことを意識して働いていると、「ソルジャー賞」というものを受賞できました。
MOSH創業:自分らしい生き方を支援したい
その後2017年に、籔と村山と3人でMOSHを立ち上げます。私にはもともと起業意欲がありました。1社目の代表や同僚を尊敬していたことと、代表が言っていた「創業者の気持ちは創業者にしかわからない」ということに興味があったんです。また、いつか彼らと同じ目線で話せるようになりたかったという思いもありました。
籔は、Rettyを退職してから数ヶ月間世界を回っていました。その中で、クリエイター向けのプラットフォーム事業を思いついたんです。日本人だけでなく海外の人たちも「自分らしい生き方の模索に苦しんでいる」という共通した課題を感じたそうです。SNSの影響で無用に人と比較して、自分が本当に熱中できるものが何かわからない。マサイ族ですら同じ悩みを持っていたそうです。一方で、情熱を持って働いている人はそういう悩みとは無縁でエネルギッシュです。しかし、彼らの多くは儲かっていないという課題がありました。この社会のアンバランスを解決したいと思い、クリエイター向けのプラットフォーム事業を開始しました。
創業期の苦闘とコロナ禍での転機
実は、2017年の創業から2020年までの3年間は、何の成果も出せませんでした。村山がフロントエンドを開発し、私がそれ以外の部分を担うといったかたちで、ひたすら開発し続けました。
そんな状況を一変させたのが、コロナです。人々の生活習慣が大きく変わり、ITに疎い人でもオンラインでサービスを受けるようになりました。コロナ以前であれば、オフラインじゃないとサービス業が成り立たない状況から一気にオンラインに切り替わりました。それまでサービス紹介のDMをいくら送っても反応がなかったのにも関わらず、コロナ禍になって突然大量の問い合わせが来るようになったんです。
事業拡大に伴い数億円の資金調達を実施し、私の業務内容も少しずつ変化していきました。開発はサポートに回り、採用業務に多くの時間を割くようになりました。スカウトを丁寧に送ったりエージェントと密にコミュニケーションを取ったりと、1日の半分くらいは採用業務に使っていたと思います。
採用活動が回るようになってからは、チーム作りに時間をかけるようになりました。チームの力学づくり、制度設計、評価設計を実施。今では、チーム作りも権限委譲が進んできています。開発できる余裕ができてきたので、直近は技術的負債の解消にも取り組み始めました。
成長の転機:Rettyでのギャップ体験
これまでのキャリアで一番技術者として成長したと感じたのは、Rettyでの経験です。プロシーズ時代はひたすら仕事をしていたので、インプットの時間を取れていませんでした。一方でRettyは、開発チームに一定の余白と自由を与えてクリエイティビティで事業を大きくする環境だったんです。そのため、1つ1つの取り組みのインパクトや関係各所への連携など、何事も自分で考えて動かないといけませんでした。また、周りのレベルも高いので常に新しい情報にキャッチアップしていく必要があります。「自分が知らないことがたくさんある」と学べた良い経験だったと感じています。
個人の夢・目標:海外展開で世界を舞台に
私の目標は、MOSHの事業目標を達成していくことと、その上で仲間が幸せになることです。また、2027年までに海外進出していきたいです。MOSHはオンラインサービスなので、国境を超えやすいという特徴があります。クリエイターにとっては、日本国内だけだとすぐにマーケットが限界を迎えてしまいます。しかし、海外という選択肢が入ることでマーケットが格段に大きくなりますよね。それが実現できると、クリエイターの人生が変わる可能性があります。島国の日本で生きる感覚から、世界で生きる感覚に変えたいと考えています。
考え方・マインドについて
大切にしている3つの考え方
私が仕事をするうえで大切にしていることは3つあります。1つ目は、「自分が作ったもので人の役に立つこと」です。プロダクトだけでなく、制度や文化も含めて、何らかのアウトプットで価値を出したいと考えています。現場感を失って的外れなことをやりたくないので、今でも自ら手を動かすことを厭いません。
2つ目は、「仲間の思いを理解し、チームで課題を解決する」です。私はCTOとして、常にメンバーの困りごとを解消したいと思っています。そのため、常にコミュニケーションを取ることを意識しています。もちろん、データなどの定量的な指標も大切です。しかし、個別具体の事象に目を向けるためにも、定性的な情報も用いて組織づくりをしています。そのような取り組みを通じて組織力を高め、チームで課題解決ができる組織を目指しています。
3つ目は「失敗すること」です。弊社はフルリモート体制なので、組織の心理的安全性が高まりづらい側面があります。だからこそ、「失敗を許容していく組織」を意識的に作る必要があるんです。AIなどの新しい技術が出てきたときに、まずは試してみることを大事にしています。ベストプラクティスが固まっていない状態でも構わないので、自分たちなりにやってみて、失敗をしながら学んでいこうとしています。
AI時代に価値あるエンジニア:ビジネス・事業から考える
今後は、「ビジネス・事業から物事を考えられるエンジニア」の価値が高まると考えています。MOSHでは、集客や決済、ファイナンスなどいろんなシステム基盤を作らないといけません。その中で、顧客に最適化されたUXを作っていく必要があり、この部分をAIによってさらに加速させようとしています。すると、基盤を作る人と、基盤の上でUXを作る人に分かれることになります。
一般的に、ソフトウェアを個別最適化しようとすると難易度は上がってしまうので、これまでは汎用化されたものを提供することが多かったと思います。つまり、UIやUXは多少妥協して作れたわけです。しかし、AIによって個別最適化されたサービスを提供できるようになってきており、システムに求められる速度やクオリティがどんどん上がっていくと考えられます。そのためUXを作る人たちは今後、一人ひとりの顧客に向き合って、自分たちで事業を作る視点でやることが求められるようになると考えています。
フリーランス活用:社員との垣根がない環境
弊社では、20名いるエンジニアのうち3割くらいがフリーランスです。社員とフリーランスの業務内容に差はなく、リーダーを任せているフリーランスの方々もいます。違いというとストック・オプション付与の有無くらいで、福利厚生やデータへのアクセス権限も同じです。こうしている理由は、社員もフリーランスも同じ時間をかけてくれているからです。そんな中で、「社員は大事だけどフリーランスは…」と言うのは違うと考えています。
多くのフリーランスには、主にエンジニアのメンバーとして開発を担っていただいています。フルリモート・フルフレックスで、週3日稼働できれば採用の検討が可能です。その際もスキルだけでなく、社員と同じようにカルチャーフィットを重要視しています。
MOSHで働きたい方へ
MOSHのサービス:情熱がめぐる経済をつくる。
弊社は、「情熱がめぐる経済をつくる。」をミッションに、サービスクリエイター向けのプラットフォーム「MOSH」を開発しています。予約や決済、CRM、コンテンツのホスティング、メッセージの配信などの機能を提供し、クリエイターのみなさんがサービス提供に集中できるようサポートをしています。
最近のリリースでは、個人のクリエイターが集客をする時によく使うLINEの機能を強化しました。彼らの悩みの1つとして、集客用の動画や資料の作成に苦労しているというものがあります。そこで、普段のレッスン風景をティザー化して、本番動画を見るためにLINE登録を促すといった機能を追加しました。
また、クリエイターの事業規模によって悩みは様々です。売上規模の大きい方は、オペレーションの自動化や運用負荷の軽減などにニーズがあります。そのような課題を解決するために彼らと直接対話をし、弊社でオペレーションの運用代行をするといったハイタッチな支援もしています。
チーム体制:自立と裁量を重視
弊社の開発組織には、「プロダクトチーム」と「プロダクティビティチーム」といった2つのチームがあります。プロダクトチームはさらに3つのチームに分かれており、1チーム3人ほどです。デザイナー、PdM、BizDevが1つのチームに所属してミッションの達成に取り組んでいます。各チームには自立と裁量を求めており、プロダクトのロードマップを敷いてどのように動いていくのかを考えてもらい、経営からフィードバックをして開発を進めてもらっています。また、フルサイクルのエンジニアリングを実践していて、企画(ニーズ調査)、提案、設計、MVP制作、ユーザー調査、開発、運用まですべて担当できるのが特徴の1つです。
一方のプロダクティビティチームには、システム開発における横断的な技術力に強みがある人たちが所属しています。老朽化している技術スタックのイネーブルメントなど、プロダクト全体の品質担保を担当します。
働くメリット:AI時代の事業創造とモダン技術
プロダクトチームでは、技術面から事業を作れる機会があります。今後、機能を作ることがどんどんAIに置き換わっていく中で、伸ばしておいて損はない重要なスキルです。「このプロダクトを作って、売上がいくら上がるのか?」といったことを考えていただくので、「自分で事業を作れるエンジニア」になれると思います。
プロダクティビティチームでは、技術スタックのモダン化に携わっていただけます。システムの安定化というよりは積み上げているフェーズで、新しい技術を使って、権限基盤や認証基盤、通知基盤などのたくさんの基盤を作っていくことができます。まるっと一個の基盤を自由度高く担っていただくので、やりがいを感じていただけると思います。
また、チームに関わらず最近は、1人あたり毎月2万円分のAIツールを使ってくださいと言っています。簡単なことではありませんが、2万円分をうまく使うことができれば生産性が格段に上がり、ペイできる成果が出ているはずです。
周囲へのリスペクトを大事にできるエンジニアを募集中!
弊社では、考え方は違えど、敬意を持って理解し合おうとする人を採用したいと思っています。傾聴し、理解する姿勢は社内のメンバーに対してだけでなく、クリエイターさんに対しても同じです。また、マーケットがかなり面白く、まさに今パラダイムシフトの瞬間にいます。2年後に振り返った時に、「すごいことをしていたな」と思っていただけるはずです。そんな成長著しい領域で、一緒に成長していける方を弊社は求めています!
取材を終えて
村井さんのインタビューからは、「人と向き合い、自分の価値を届ける」という強い思いを感じました。AI時代においては、エンジニアにもより事業的な視点が必要になってくるという視点は、多くのエンジニアにとって参考になるものだと思います。創業後3年間の苦労を乗り越え、2025年2月には22.5億円の資金調達を実施し、まさにこれからグローバルを目指して成長していこうとされているMOSHさん。そんな勢いあるスタートアップで挑戦してみたい方は、ぜひ一度お話を聞かれてみてはいかがでしょうか?